隈栄二郎作品集
ってほどでもないけど。
※ 『変革の機制』 行為論を基軸にすえた社会学の基礎理論
※ 『〈自由〉を探した靴』 前著のエッセンスを読みやすく書き直したもの。
※ 『光の国のダンサー』 前々著には載せなかった行為論的イデオロギー基礎論について読みやすく記述したもの。
※ 『光と影とネズミの王様』 前々々著には載せなかった行為論的社会関係基礎論について読みやすく記述したもの。
※ 『風とベイシティ・キャット』 行為論的知識社会学の基礎論について読みやすく記述したもの。
※ 『パリの爆薬』 国家と革命の基礎理論について読みやすく記述したもの。
※ 『行為の集成』 上記すべての著作のエッセンスを詰めて、お徳用ではあるが、相当読みづらい理論書。
※ 『歴史としての支配』 上記著作を基礎とした具体的歴史への応用理論の著
※ 『「上部構造」の社会学』 上記2作に続き、現実の構造ではなく、人間の観念の秘密とその現実への役割を明らかにした理論書。
※ 『資本主義と支配システム』 社会学というより経済学書や社会思想書を思わせる科学の書。
※ 『解放行動の原理』 そのまんまですが、闘いの季節を終えた者たちの人生を祝福せんがための書。
![]()
![]()
 |
私的個人を社会分析の準拠点とし、個人行為の原理・原則から社会システムの編成と変動の機制を明らかにする。 とりわけ社会システムの変動について、私的個人が意思的に社会の変更を生じさせうる諸方式の一般的な基礎理論を展開している。 |
![]()
(石原睦仁氏の解説より) ……… 本書はマルクスを踏まえ、しかしそれを前提として乗り越えた、真に社会科学を100年越しに前進させたといえる書物である。 ……… ソ連・東欧にみる国家社会主義経済の崩壊は、マルクス・レーニン主義への幻滅を引き起こすに十分であろう。しかし、それゆえにマルクス主義の理論構成に論理的困難が惹起されたわけではなんらない。マルクスが述べたように、問題はイデオロギーではなく現実の経済過程なのである。 ……… それは体系の総合性においてパーソンズに比肩されるべき、しかし、より簡明であることにより、全人民的な財産となしうるものである。いわば、唯物論に観念論的基礎を与えた、(あるいは「その逆」であろうか)ともいえるジンテーゼである。社会学上の伝統的な表現をもってすれば、個人と社会とのアポリアを初めて乗り越えた著と評することもできよう。さらにその独創性と社会理論が負うべき歴史的課題への志向性を比較するには、古くデュルケームにまで遡る必要もあろうか。昨今の日本思想界は一度は獲得しかけた主体的立場を忘れ、「誰某によれば」の外国思想紹介で埋め尽くされる体たらくであるが、世間には持続する運動者がいるのと同様に持続する思想者もい続けるのだといえることは最後の救いである。 まず著者は序において、あくまで行為し歴史を作っていく主体として、個人としての「私」にこだわる立場を明らかにする。 この社会を見れば複数いるはずの個人としての「私主体」は、第1章において、人間として行為の原理・原則を普遍的に持つことで、社会と支配関係を作り上げてしまうことが述べられる。 ついで第2章では、協同生活で生ずる規制が行為共同性(=いわゆる共同性)を生じさせること、またこの行為共同性が支配規制とあいまって社会の構造を作り上げることが明らかにされる。 第3章では、資本主義社会という歴史的に規定された社会にあって、そうした普遍的=形式社会学的な規定がどのような社会学的な規定に姿を変えるのか、そしてそれはどのような行為者個人的意義を持つのか、という点が解明される。 著者は資本主義社会という概念規定においてマルクスに異論を持つわけではないようだが、その資本主義規定から導き出される、いわばわれわれにとっての資本主義社会の意義の解釈に異論があるようである。 そうはいっても、著者は今流行のポスト・モダニズムに走るわけではない。彼は第4章において、「マルクスの復権」ならぬ「マルクスの正しさの再確認」を行なう。彼は宇野弘蔵に(彼の言によれば)「依拠」し、マルクスには経済学上は何も間違ったところはないという、われわれマルクス主義者にとってさえ過激な論を展開する。しかし著者の主張の眼目はその先にあり、彼はマルクス経済学と現実の経済との裂け目を彼の行為理論で埋めていくのである。 そして第5章において著者は、本来の社会変動理論とは、過去、社会学がマルクシズムに対抗して作り上げた社会システムの記述理論ではなく、社会を変動させる理論のことでなければならない、と説く。このあたりは、アカデミズム社会学に慣れた目には、驚愕するほど過激である。 彼は、資本主義の歴史経過を行為論的に概観した後、第6章において社会変動を引き起こす社会運動の理論を展開する。それは相当舌足らずでもあり、またわれわれ実践者がそのまま横引きできるほど具体的なものではないが、一方豊かすぎるほどの示唆に富むものである。 本書の特異な点は、とりわけ、事実認知、生理性(身体存在の確保)、賞賛、優越という行為論的キータームによって主要な社会科学事象のすべてを説明し尽くした点にある。 これらのキータームの科学的妥当性については専門外のこととしておくとして、しかし、誤解を与える怖れをあえて甘受して簡潔化した体系的説明と、追利用可能な使用法は、見事というべきである。「真理は存在しない」などと空語を続けるポストモダン派や社会科学「序説」に冗長なお喋りを続ける人々とは、そもそも生きる地盤が違うというべきであろう。 さらに付け加えれば、キリスト教的な当為に脅迫された西欧文化人には、たとえ彼らが反発的に「無神論」にまで脱自化していようと、人間の行為の動因として「世俗的」な優越・賞賛という概念を承認することは、恐怖に等しいであろう。著者にはキリスト教的学問世界への独特な感受性があるのだが、この意味で、本書が切り開いた地平は、人間知識のアジア・アフリカ的勝利と言えるかもしれない。……… (なお、目次が、万能書店の本の紹介コーナーにあります) ⇒あったんですけど、消えちゃいましたね。まあ、専門家用の本です。 |
|
![]()
![]()
−行為論的社会学要論
 |
上記「変革の機制」の内容を専門外の人にもわかりやすく読んでもらえるように、小説形式にしたもの。 就職にも男にも失敗した由実。気晴らしに来たヨコハマではハイヒールの踵が取れ歩けなくなってしまった……。ふんだりけったりの由実が靴を直してくれた「彼」と語りながらヨコハマを歩く……。 |
![]()
(著者解説より) ……… この本は、読まれる方のためとしては、人間の自由とはどういうものか、それを実現していくにはどうしたらいいのかを、比較的にやさしい言葉で書いた(つもりの)ものです。 と同時に、この本は、僕個人にとっては、今までの社会科学が、一方では、社会の構成をあたかも社会が機械のように出来上がったもののように、他方では、人間をその心が感ずるままに生活しているかのように、とらえている間違いを正すためにも書かれています。 ここでは、生きている1人の人間のそれぞれが主人公です。 でも、彼は制度の中で生きています。 それでも彼は、その制度を変えていくやり方も知っています。 そんな視角から社会を分析するとどうなるか、社会科学上のいくつかのテーマを各章に分けて書いてみました。題にある〈自由〉とは、お読みになった方はお分かりのように、人間個人の本来の行為そのもののことです。 1章では、社会を形作っている個人を考える際に、具体的には何をみていったらいいのかが書かれています。 人の幸せも不幸せも、結局、人の行為によって決まります。その行為をみていくポイントを誰にでも考えやすく述べてみました。 本当はこの点は、専門家には細かく厳密に書かないと説得力に欠けるところですが、一般的には関係ありませんのでそれは避けました。 2章では、人間1人1人にとって、現代日本の社会、つまり資本主義社会とはどのような意味のあるものかが書かれています。 結論だけからすれば、フツウの社会主義的な本の資本主義批判と変わりません。ただ、個人からしたらどうなのか、という点が、論理の内部にいくつかの修正点を出すことになります。 なお、この本では、あまり『搾取』について書いてありません。それは日本では『搾取』がないからではなく、今日本で必要なのが新しい社会ビジョンであり、そのビジョンをつくるための原理原則だからです。すでに『搾取のない社会をつくろう』という初めの一歩の地点は過ぎています。それは具体的にどんな社会なのか、というそこからの次の一歩を始めるために、今、別の視角が必要なのです。 そういう意味では、もう少し経済原論に即して展開したほうが専門家には分かりやすいのかもしれません。経済学は、諸統計の調査・現実の分析技術などはさておき、経済原論としては僕たち生活している庶民にはきわめて不十分なものです。マルクス経済学は、ひたすら資本論解釈でのささいなタテマエ論議をするばかり。近代経済学には、そもそも原理論があるとは思えません。 でも、やはりそうした展開は場違いなので、少しだけでやめました。 3章では、階層とは、差別とは何か、が書かれています。 人間が他人と生きていくことを考えるなら、この点はどうしてもはずせません。 あるいは国と国との関係でもそれは同じことなのですが、そこまでいくとそれこそ経済学的な関係付けが必要ですので、ここでは略しました。まだ、そうした国家間の経済関連を、モノのやりとりや権力者の思惑以上のレベルで明らかにしてくれたマルクス経済学者もいまだかつていらっしゃらず、偉そうにいう僕もそこまではいっていないので。 4章では、運動とは何かが書かれています。 言語(的発言)、思想についても述べてあげまりが、同じ趣旨です。 だいたい運動の基礎理論ていうのは、政治集団の人が説く願望度の高すぎるものか、機能主義的っていいますか、運動はただウサを発散してるだけみたいな病理現象論、になってしまっています。 運動の持つ限界や意義が本当はどこまでのものなのか、は、もともと言葉の限界と意義から始めないといけません。 5章では、望まれる社会主義とは何かが書かれています。 ここでの趣旨は、例示に使った具体的な結論がどうということではなくて、誰でもいいのですが望ましい社会を考えられた人は、その形成を決して人の善意や努力に託してはならない、ということです。それは制度的に確保していかなければならない。それができない社会ビジョンは、絵に描いたモチ。真に受けた者だけがバカをみるという、結局間違ったものです。 社会は、決して目覚めた大衆が作り上げたり、良い政治家や政治集団が実現できるとか、ってもんじゃない。 そういう意味では大衆は決して政治家にはなりませんし、政治家なんてたかだか口のうまい隣のオジサンにすぎません。 一方、もしも制度的にコントロールしながら実現される望ましい社会ができるとすれば、今の先進資本主義国ではそれを十分実現できる。制度的にコントロールするというのは、すでにその国の人々全部が認知している、ということです。したがって大衆がどんなでも政治家がどんなでも、それに沿った政治が実現する。そういう意味ではただの理論が社会を変えられる。人はそこまで賢い生物だということです。 ……… |
|
![]()
![]()
−イデオロギー基礎論
| 幸せを求めて人は争いを形作る、ように私達に思わせる、世界に渦巻く論争や闘争。イデオロギーは人の頭の中 でそれを支配しているように見える。しかし実はイデオロギーと呼ばれるものは、行為する個人や集団の頭の中に ある「観念」ではなく、社会関係の中の権力的な状況において使用される「表現」である。本著は、人が生きた「 れきし」を個人の信条としてのイデオロギーの意義に還元する考えを否定しつつ、一方で、行為論による分析の 光をイデオロギーを道具とした人間の解放への道程に照射する。 |
|
![]()
![]()
― 社会関係基礎論
 |
アパートの一室で気がついたえりかは、自分の記憶を失っていた。「えりか」とは誰か。見え隠れする黒い影……。就職した会社を辞め、東北、岩手への旅に出たえりかは森のネズミの王に招待されるが……。 童話「青い鳥」のその後を追う第1弾。 |
(著者注釈より) 1 本書の紹介 「青い鳥」。妖婆ベリーリウンヌの病気の娘を助けるために、妖婆に命ぜられてチルチルとミチルは「光の精」や「水の精」「火の精」たちとともに幸せの青い鳥を探しに行きます。思い出の国、夜の国、幸福の国、未来の国……。でも幸せの青い鳥は見つかりません。そして、その旅が終わるとき、精霊たちは死んで「沈黙の国」へ行かなくてはならないのでした……。 しかし、この本は、おとなの童話ではありません。 これは、社会関係についての社会学的基礎理論です。 と同時に、制度の変更についての議論です。 ある国の制度を変えることについて、あるいは、今の日本の制度を変えることについて、それをどうやったらいいのか、について踏み込んでいくための考え方の基本用具について書いてあります。 でも、やっぱり童話かな、という誤解があるといけないんで、誰にでも見分けがつくように物語と理論部分ははっきり分けて書きました。……うそです。どうもストーリーと理屈が一体化しづらいんで、あきらめてスムーズに理論にはいれる努力をしませんでした。ただ、そのデメリットは多々あるとは思いますが、メリットも少しはあるんじゃないか、と思ってます。つまんなかったらそこは無視すればいい、とか。 まあ〈関係〉の基本用具を提示すること自体は、今までの小説風2冊と違って、普通の人の普段の生活には直接は関係しないんじゃないかと思うんです。だから普通の出来事の中には埋め込めなくて当然だろうと。 でも直接は関係しなくとも根本的には必要な知識だと思います。 ある国では、今の日本では、現在起こっているように制度は変わって行きます。 それは運動を続けている人がいるからです。 ただ、日本、ないし多くの(資本主義)先進諸国内での運動は、生理的レベルが勝ち取られた上での運動です。 そこでは第1に、資本主義を傷つけない範囲で、運動が進められ、その結果が勝ち取られていくでしょう。 第2に、その運動は、資本主義の生理性に保障されているから、社会の賞賛も得られています。 その意味でも、この運動はその国の制度を資本主義の変化に沿うように変えていくでしょう。 第3に、それでは、それらの運動はどこまで日本の制度を変えていくのだろうか。 その答えは、運動が国家権力を手に入れながら続けられるのかどうか、で違って来ます。 資本主義には、経済の条件と人間の存在との間で変えられない原理がある。 しかし、国家権力は、国家間の条件が許すなら自由にこれに制限を加えることができる。 さてそこで、社会にはどんな下地があって生産関係と国家の力はせめぎあうんだろうか? 前の本では、社会関係については、人の関係は生産関係で規定されているんだ、目にみえない経済の仕組みが大切なんだ、と強調して終わってしまいました。それを変えるのは運動なんだよ、と。 それで「今」の分析は済むけど、それだけだとこれからの社会の変更がどうも考えづらい。運動をしたらどんなふうな過程が起きて社会は変わるのか。 そこで本書では、「人と人との関係」「人と国家との関係」について考えてみました。それによって、制度を変えるにはどう動けばいいかを浮き彫りにするために。 本論は、もとはといえば、1996年、7年前に『規範原論』として、これはほんとに一部の人に、というか一人だけに、発表したものがもとになっております。 中にも書いておきましたが、「規範」は関係の拘束的部分の結果なので、結局関係論でもあったわけです。 本論部分は目次でいうと2以下、3章で5つの部分に分かれています。 第2章では、まず、人を取り巻く関係について書いてあります。 関係には視点の取り方で3通りに分けられること。この3つを「社会関連」「行為関係」「生産関係」と呼びます。いってみれば「人が自分を取り巻く環境について抱く認識」と「環境の自分にとっての意味」と「周りの環境自体が持ってると想定せざるをえない因果連関」の3つを視点にして、人は自分と外界との因果=こうすれば周りはこう動くというつながりを、関係と呼んでるわけです。 次に、人と国との関係についてが書いてあります。 それは、国家は「社会関係」と呼ばれることは少ないのですが、「関係」と類似した独自の動きをするからです。 基本的には国家は暴力(武力)と共同性の歴史でできています。 もっとも、暴力をとりしきる意思決定者は、一般庶民とは別の回路で存在するため、一般庶民は権力に関しては行為の想定可能性を持っていません。代議士を選挙で選ぶことはできるが、自分のある行為が国家の武力を変えることはできない、と思ってしまのです。 ここは、第4章の導入のような部分でそう発展的なことは書いてありません。 なおついでに、弁証法という、社会を見るときの考え方について少しだけ触れておきました。転向した人たちを中心に、何も自分でモノを考え出したことがない人たちが、マルクス主義憎さに弁証法さえ攻撃するのが我慢ならないからです。まあ攻撃されても仕方のないむちゃくちゃな議論も中には(多々)ありますが。 第3章では、まず国の中での関係について書いてあります。 簡単にいえば「社会の形態」というか、世界の国々の色々な社会が、なんで違ってみえるか、みたいなことです。それは行為の原理・原則をめぐって、種々の社会関係が存在してるからですが、それを類型に分けてそのよって立つ部分を示してあります。 あまりにも筋から浮いてますが、「国民性」や国民の生活様式の差異なんかを考える機会がある方には、その理解の足しになることと思います。 それから国と国との関係が書いてあります。 結論的に現在の資本主義が優越している世界では、ある国の社会関係は、 第1に、そのおりの世界経済=指導資本主義諸国の要求環境によって 第2に、当該国家の物的、人的資源によって 第3に、当該国家の階級状況によって 1)国家に一体性がある場合は、その国家の存続条件の認識によって 2)国家に一体性がない=支配階級が階級的である場合にはその階級の利害によって それぞれに変わることになります。 第4章では関係を変更することについて書いてあります。 まず、生産関係の変化が国家のような権力関係内部の変化に結びつく仕方が書いてあります。 ついで、全体的な運動が社会を変革していくことは過去3書でしつこく書いたので、ここでは私たちが具体的に関わる一つ一つの個別の運動が、どんな関係で生産関係・権力関係に結びついていくか書きました。残念ながら個別の運動にはあまりできることはありませんが、それは逆にいえば全体的な運動がどれだけ大事か、ということを意味しています。 全体的な運動とは、いわば「生産関係」を使うのではなく、運動が持つ自分の権力とイデオロギー等のアピールを利用して、社会の賞賛や優越を変えていく運動のことです。 そして、生産関係ではなく、国家権力に食い込んでいくことです。 普通のコトバや情報は具体的な関係に拘束されるので、結局関係をとりしきる生産関係や国家の持つ権力関係に操られてしまいます。しかし、運動のアピールは具体的な関係から離れることができるのです。こうして、運動のアピールが、同じ利害関係にない社会の諸層の力を吸収して社会を変えていくのです。……… |
|
![]()
― 言語情報基礎論
| 光の精の逃走(「光と影とネズミの王様」参照)の混乱に乗じて逃げ出したネコの精。 着いた東京ベイエリアで人間の繁栄の秘密を探る。人間の繁栄は、権力の使い方によるのか、知恵の使い方によるのか、、、 探るネコの前に現れた「風の精」とネズミの王様。そして、ネコの精霊を連れ戻そうとする追っ手。東京ベイエリアを舞台にネズミはネコを追い、ネコはネズミを追う……。 童話「青い鳥」のその後、第2弾。 |
|
| (あとがきより) 1 本書の内容 本書は「情報」、特に言語情報という人間行為の環境要因についての基礎理論です。 ちょっと年代の古い人たちには「知識社会学」といったほうがイメージがつかみやすいかもしれませんが、知識ー社会学、つまり「知識」に関する社会学なんて応用分野があるわけではありません。「政治」や「経済」のような分野では行為者の行為の場を舞台とする社会学が存在もしましょうが、知識や情報というのは人間が行為する「場」などではありません。そんなハイフン(−)社会学が存在するわけがない。 また、世には「基礎情報学」などと銘打って、観念的な情報学を観念的に基礎付けようとする人もいます。そういう人に限って気持ちはまっすぐなのでケチをつけるのははばかられるんですが、心を鬼にしてほんとうのことをいえば、真実というのはそうではない。情報に対して揺れ動く感情を描いて社会を理解しようなんて試みは、絶対に法則科学とはならない。 で、本書は情報が人間行為者にどのような位置を持ちながらそれが再生産されていくのか、それを明らかにしつつ、例によって情報の再生産の社会変化への関連を明らかにしていったものです。 言葉を使って人間が考えを伝えていく主題には、「こんなことがあるよ、どうしよう」という問いかけと、これに対して「こういうときはこうすればいいよ」という応答の2通りがあります。 (人間が個人としてすることでは、難しい言葉を使わなければ表現できないことはありません) そして、良心的な学者ほど世界に生じている事象を自らの手で把握し、問いかけの形で世に問い、人々の次の行為を促すために著作を発表していくものといえます。 大部分の社会学者の著作と、一部分の経済学者の著作とは、そういうものです。 (ごく一部の社会学者と相当数の経済学者は「今こうだから、こうすればいい」と発言しますが、自分のそんな発言が実はどんな社会的役割を持ったかトータルとして反省したらどうかと思います。そんな反省をして耐えられるのは、まあ3人かなあ。……そんなことはいいとして) そんな学者の営みと同様に、世界を自分の著作の中で構成することには「こんなことがあるよ、どうしよう」という問いかけが含まれているものが多いものです。 たとえば前著から引き続き今回も尾を引いている宮沢賢治のものがそうです。 ただ、それでは社会科学にはならない。私はあくまで「こういうときはこうすればいいよ」を追求する。今回は、まず、社会に動かされないために、「結論のある情報なんてみんなウソだよ」ということを知っていただきます。次に、社会を動かすためには、「特定の行為について、それをする行為者が社会の中で賞賛されるという具体的な情報を社会の事実として累積させるんだよ」ということを知っていただきます。 第1章は、既存の社会科学者の名著、大理論というものが、どれだけ真理と関係がないかを述べてあります。 とはいえ、私の関心はそういう有名学者の批判にあるわけではなく、いったい真理と世間で呼ばれるものがどれだけいい加減なものか、どれだけ世間の権力=賞賛と優越に規定されているか、を見るところにあるので、本書ではごく短くしました。読んで「そんなはずがあるものか」という義憤にかられた方は、私のホームページに例文付きの批判が載ってますのでご覧ください。 それでも納得いかない方には、いつでももう少し詳しいやりとりにお付き合いいたします。 世間の学者関係者の目から言えば大問題であるはずの第1章はそんなところで、誰だってそんなもんさ、と分かってくれればおしまいです。 第2章は、まず、情報を扱う人間を3通りに分けます。情報の発信者、これを広めるメディア、これを受け取る人間、です。 情報の発信者が、まず書く。 情報メディアは、資本主義経済の中で売れるものを広める。 情報の受け取り手は、自分が受け取って有用なものを受け取る。 そこで、新たに情報の受け取り手は、社会の中の自分にとって有用なものが手に入る形で、発信する。 シンプルに図式化すれば、情報の動きはこの繰り返しという形態を取ります。 これが資本主義社会の中に生きる人間の間での情報のあり方です。 情報には歴史的に普遍的なあり方など存在しないことが、情報を扱うのが人間である限り、普遍的な真理です。 また、ここで、自分にとって有用なものとは、それぞれの立場の人間たちが得られる賞賛や優越、(まれに生理的利害への関連情報)のことです。 第3章は、それでは、情報を有用なものとし、情報の売れ行きを決め、情報の色を決める行為への賞賛や優越が、どんな理由でその時代時代にある決まった形をとるのか、ということが問題です。 シンプルな姿で、情報の当初の発信者とメディアは「売れる情報」を扱います。 しかし、情報の受け手は、そして2次的な情報の発信者は、権力が姿を変えた賞賛と優越に規定されて情報を自分のものにしていきます。 そして、ある1人の個人にとって、どんな社会の局面から賞賛を取り出してくるか、は制限されたことなのです。 この賞賛が制限されている、ということが、支配的な思想は支配者の思想であることを決定付けているのです。 人は、まず生きていかなければならない。その生理性に賞賛と優越は規定され、自分の思想を作ります。もちろんそこで知識を使う。しかし、人間は知識さえ、自分が賞賛と優越を獲得できる知識を使うのです。 もちろん、思想など頭の中にある限りは何の意味もありません。 しかし、こうした生理性を基盤とした賞賛・優越は、それで大衆を巻き込もうとする限り、国家支配者のコースと同一となります。それが、支配者の思想の具体的な姿です。 大衆自体に矛盾がある場合にのみ、対抗的なイデオロギーが、新しい共同体のコースを作ることができるのです。 第4章は、とはいえ、情報が持つ大きな意義、ウソでない事実、技術=自然科学的な事実が行為者に与えてくれる意義を、物語として例示しています。 技術といっても、本当の問題は産業技術ではありません。まあ、歴史評価としてそんな事実認識=技術が大切だ、というのは知ってさえいればいいことで。 そうではなくて、事実は行為者にとっての事実でなければならない。教科書で教わったことなんか行為者にとって事実ではない。 ナマで体が覚えた戦争被害体験、差別体験、それらはその人間が生きている限りは圧倒的な意義を持ちます。しかし、体験を情報化するには、技術として、自分の手で扱うことができ、その結果が自分で確認できる事実として、把握されるしかない。 たとえば、消火器訓練、障害の体験学習、そんな行為主体が持つ技術のみが意義がある、あるいは教科書なりの情報は「ここに至って」意義があるのです。 という筋立てですが、実は本書の意義の大半は、なぜ思想が生産関係や権力の仕組みに規定されるかを個別に照明を当てたところにある、と考えています。平たく言えば上部構造が下部構造に規定されることを証明した、ということですが、なにしろ証明するための定義・法則が世間に周知されていないので、ちょっと遠慮して言いました。 いずれにしても、この仕事は昔ならマルクスの経験的洞察の卓越性を証明する重要さがあったものですが、左翼が敗北を続ける現在では理論社会学専門の人以外にはほとんど興味が持たれないでしょう。で、それでは読んだ方に申し訳がないので、ずいぶん物語に力(とページ)を使いました。前著同様、つまんない理屈の部分は飛ばして読んでも筋がわかるように配慮してあります(?)。せめて、ま、面白かったかな、と思ってもらえれば幸いです。 |

−国家と変革の基礎理論
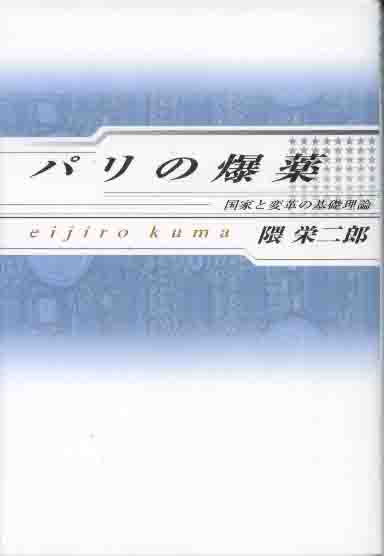 |
新宿で飲んでいたはずが、ふと気づけばそこはパリのテロリストの弾薬庫。逃げてそのままビストロの酒蔵に倒れこんだ可南子は、イスラムの青年と孤児に出会い、思いもかけぬ冒険に巻き込まれる。 フランス官憲が勝つか、テロリストが勝つか。可南子は無事に日本に戻れるのか。 ビストロの女主人由実と、おなじみ、ネズミと猫の冒険の結末は??? 童話「青い鳥」のその後、第3弾。 |
| (あとがきより) 1 本書の内容 本書は、国家のシステムとこれに対抗する組織の体制について書かれた著作です。 本の題は、有名なレーニンの国家論の名著から取って、〈国家と革命・2007〉というのが一番正しいんではないか、と思うぐらいです。まあ、かっちりした理論書でもないので止めましたが。 で、読者の皆様へのお奨めの言葉で、社会科学研究者の方々には、これが真正の国家論ですよ、これが本物の組織論ですよ、みたいにいえばいいのですが、一般の方にはどうしましょう、というところで、これは社会変革のための諸技術をめぐって書いた著作ですよ、みたいになります。 さて、ここではたと困ってしまいます。 私の読者に社会変革者なんているか? (中略) 今、40歳以下の人間の頭には、「国家社会の矛盾」なんて存在しません。 でも、幸か不幸か、社会は変わる。変わらざるを得ない。 20年後、今、30歳以下のニート、フリーターを先頭層とする巨大な貧困階層が成立したとき、彼らが頼るのはやはりすでに60年前のものとなったマルクス主義の誤った革命理論でしかないはずです。そこで生ずるのは、やはり過去あったのと同じく、そして今も旧過激派の胸のうちで生きている誤った諸活動の再生産に違いありません。 日本でなければ? 本書を含めた私の理論は、少なくとも英語化することを視野に入れています。 現代では、諸国で、マルクス主義など名前しか知らない無文字層が、イスラム教という、マルクス主義以前の教条を受け入れるしかありません。そこでは、同一の共同性内での平等主義的性格によって、あるいは欧米支配層への対抗的性格によって、誤っていようともその巨大な影響力によって、人民は教団指導者に取り込まれ苦しんでいます。 本書は、現在の皆様という読者を念頭におきつつ、その知識の継承者として、皆様の将来、あるいはお子さん方、あるいは現在の非抑圧人民と彼らに味方するその民族の一部知識階層の方々を設定した著作です。 第1章は、科学の方法について書いてあります。弁証法ですね。第2章の社会の体系の把握のための導入部分です。 弁証法っていうのは、生きている人間の現実を表した表現ですので、私たちにとって3つの役割を持ちます。 1つ目は、実践の倫理。形式論理的には矛盾している被支配者の行動を、それでいいんだよ、と確認するためのもの。 支配者の実践は、支配の現状を維持することが前提だし、資本の論理の行使に人間としての倫理なんかいらない。他は考える必要もない権力の行使、つまり武力の行使や経営権の行使だけだから、実践を否定する形式論理は大歓迎。 それでよければ論理なんていらない。倫理なんていりません。 そんな支配者の現状維持の論理に対して、『被支配者は、現実を生きることが倫理だ』っていう、ただの真実を語る必要があるわけです。 2つ目は、思考の方法論。複雑な現実っていうのは、漠然と見ても何もつかめない。一つの言葉っていうのはある現象を表す流れの中の一つのイメージだから、それを取り出して考えても、その言葉が出てきた関係しか考えられない。そういうときは、ある現象の根本を探る。始元っていいますが。そこで、これなら今のところ動かない本質だ、というものを取り出す。 3つ目は表現方法の論理。このように現実は分かったけれど、一つの言葉を取り出して使っただけでは一つの関係しか表現できない。ところが、現実というものは、いろいろな現象が絡み合ってできている。 この絡み合った現実を言葉で言い表すには、どこかで初めの一歩を決めて、そこから順番に一つの流れにして表現しないといけない。これが表現としての弁証法。これも、そのまま読むと変だから、自分で考えたことのない人には、その必要性も含めて理解されませんけどね。 そして、一番大事なことは、弁証法は現実認識の方法論ではない、ということ。 現実は生きている人間が目で見えるもの。論理というのは、それを跡づけるに過ぎない。これを忘れると宗教家になってしまう。 これは、弁証法を持ち上げる者も、これを否定する者も等しく、似非哲学者のイデオローグに過ぎないと書いてあるのかもしれません。 いずれにしても、昔から思っているのですが、私の本は原稿用紙1枚分ごとに新しいことが書いてありますので、こういうまとめ方には納得できない気持ちもあります。この本ですと300項目は新しいことが書いてあります。 第2章では、国家とは何か、について書いてあります。本当のところ、私の著作には多かれ少なかれ問題意識として出ておりましたものですが。 国家とは何か。私が高校生のときとは、そんなことが話題になる季節でした。 「国家は共同幻想である。」吉本隆明。まあそうかもしれないが、いまいち観念的過ぎる、国家はもっと現実的に私たちを規制するじゃないか。 「国家意志論」、とりあえずは三浦つとむ。大同小異で観念的な話です。 滝村隆一の「国家意志論」。こちらはうって変わって、しかし同様に、私たちとは関係のない政治論でした。 「国家とは幻想の共同体である。」私には、マルクスだかエンゲルスだかが書いたドイツイデオロギーの表現が一番あっていたようです。吉本とは違って、「共同体」と実体化して表現してくれたのがうれしいところです。 とはいえ、それ以上に国家の規定因をさぐるには堂々巡りをするほかない、なにしろ高校1年生の社会知識はそのくらいのものだったのです。 実際、問題はそうではないということです。幻想は、実体的な規定性の上に生ずるということです。マルクスやエンゲルスが「漠然と」は考えたのでしょうが、きっちり考えていたら「国家とは幻想の共同体」だのとはいわなかったでしょう。 というわけで、今回は、相当実用的なレベルに踏み込んで書きました。 国家とは、支配権力者が、武力を生産関係と折り合いをつけながらシステム化してきたものです。要するに、国家は支配の暴力装置ですね。これは別に自慢するほどの結論じゃありませんが、その展開過程はなかなか自慢するほどのもんだなと思うのですが。 要するに、でユニークなのは、ここから先です。 国家は武力だが、これを変改するものは武力ではない。 何回か聞いた? うん、何回か言ったな。ただまあ、展開過程が重要ですから。なんといっても、世の中、戦争で革命ができると思っている人がほとんどですから。 第3章では、運動組織の問題を取り上げています。といっても、本来は、組織構造や組織過程ではなくて、思想と組織、あるいは逆に、組織と思想の問題です。組織構造論とかは会社組織の理論がたくさんあるし、これ以上世の中に増やす必要もない。一方、運動組織論は、組織主宰者のご都合主義しか存在しないですしね。 運動組織とは、社会システムの中でどういう位置にあるか。こういう理論の展開は、いままで稀有に近いと思うんですけどねえ。自称組織論を表す方々は、みんな自分たちは、特別にマルクス主義の法則外の生き物だ、と思ってらっしゃるから。 この章は、運動組織は賞賛の雲の中から生まれるものであって、唯一の正しい(!)組織が、先に存在するものではない。と読んで貰っていいです。 ついでに、変革に必要なものは、権力へ対抗する言辞であると共に、権力へ対抗する言辞を支える攻撃的な武力であると共に、この武力を支える生活大衆の無言の指示であると共に、この言辞と武力と無言の指示を支える広範な現実局面での反権力表現なのだ、読んでもらってもいいです。 これも聞いた? だから、本の値段は、結論じゃなくて展開過程なんですよね。 というにしては、相変わらず読みづらそうですが。 第4章には、「過渡期社会とは」、という題がついています。これも微妙な話で、この本が普通の人向けとすると、そういう題になる。何しろ、いまどきの若い人たちは、過渡期社会なんて、言葉も知らないはずですから。 といって、私としても40年前の過渡期社会論をお話ししてページを埋める気もありません。 ここは、メッセージの章というんですかね。 社会科学研究者を含めた普通の人には、「資本主義は腐朽しているんだ、これから共産主義社会に向かうしかない、その前には過渡期社会が必要なんだ」、という40年前の論を書いているように見えます。これはこれですごいことだと自分で思いますね。どんなゴリゴリの共産主義者でも、いまどき、党派新聞以外では、資本主義は腐朽してるなんて言いませんがな。なんて突然関西弁。ましてや共産主義社会に向かうなどと。私は、いわないほうが悪い、と思うだけですけどね。 他方で、こちらは専門家向け。 「たとえば、過渡期社会論を口にする者は、モンゴルの草原砂漠に、アフリカのサバンナ、そういう自然的な条件によって低生産力でしかありえない地域について語らなければならない。従って、そうした地域の人間が、生産方式上も、人口的にも、必要に応じた配分を受けるためには、何百年単位のプロセスを覚悟しなければならない」、といった確認をしていく章です。 この章でも、専門的には細かいテーマが多くて、ここではまとめきれないわけですが、ということは展開が不十分で伝わらないということに通じそうで、ちょっと残念ですけどね。そういう時代だから妥協もしないと。 さて全章を通じまして、基本的に国家というものは武力権力者が生産関係を掴んだものだ、という認識に立って論が進んでおります。スローガン的に言うと暴力とカネですね。カネといっても守銭奴の欲しがるカネじゃなくて、生きるための消費物の入手手段のことですが。 実は私は学生の折はそういう認識を持っておりませんで、社会システムとは、経済的関係だと学者が間違って言う生産関係を基礎とする実体的な(≒具体的な)社会関係をその現実態として存在するものだ、その変化は、運動によって媒介され、運動は社会関係(生産関係)から生ずる思想によって現実となるんだ、という認識で、国家というのは、その上部関係に過ぎない、みたいなところでした。 で、大学院のとき、今もどこかでがんばってらっしゃると思うんですが、藤田厚子さんという人が同じように運動論をやっていまして、この人が「世の中は暴力とカネよ」と強く主張されるんですね。なんという俗世間的なことを。世の中は、生産関係と思想なのに、と自信を持っていた私ですが、結局、国家を扱ったら、こんなとこに議論が落ち着いてしまった、ということが残念です(?)。というわけで、ここんとこ数年、常に「暴力とカネ」論者として裏に隠れてらした旧友に感謝させていただきます。 |

−行為論的社会学基礎理論
| (あとがきより) 本著は、人間の行為がいかに社会を形作っていくか、という観点から、社会の行為への規定性を解明し、逆に行為による社会の規定性の変更過程を解明したものである。 本書執筆の意図は多面的である。もちろん、行為理論に基づいた社会学基礎理論の提出が第一義的な意図であるが、それが本書のような形態をとるにいたったことには、それなりの筆者のより多面的な意図が関係している。 筆者の第1の意図は、本書をもって行為と社会をつなぐ本来の社会科学理論を提示することにある。 大学学部1年のときに、予備ゼミで「行為の総合理論をめざして」のさわりを読まされたときの刺激は、マルクスに慣らされた私の目には当然のように社会科学に存在すべきものではあった。しかし、その著者たちの企てがついえたまま打ち捨てられることも、社会学的にはやはり当然でありもした。本書は、その意図を引き継ぎ、社会科学の帝王としての社会学の確立を宣言するものである。社会学の教科書にある「個人と社会」の問題は、こうして本論に表したごとく解決されるべきである。 第2には、本書によって、行為者であるわれわれ個人が、自己の行為によって社会を変える道筋を示すことにある。 科学とは、真実を人々に提出するところに意義があるのではない。赤いバラを赤いと教えてもらおうなどと誰が望んでいようか。科学とは、それが解明した知識によって、新たな自己の将来を行為者が作り出せるようになる、その1点において意義があるのである。人はバラの色を変えられる自分やそれを他人に教える自分を夢見て、バラの色とは何かを調べ、色素なるものの生成過程という事実を認知し、あるいはバラの吸い上げる物質、あるいは作成する物質、バラを取り巻く環境のバラの生活への影響、等々の事実を認知し、それらの事実を統合してバラの色を自由に変えられるようになる。その総体が、科学の美名で呼ばれるのである。 本書は社会科学の書である。従って、究極的には、行為者に社会を変える方法を提示しなくてはならない。 第3は、上記に関わりはするが、そうした一般論ではなく、具体的に世界の抑圧された人々について、威勢のいい掛け声や手前勝手な組織擁護論ではなく、本当の社会変革の理論を提出する、という願望を含んだ意図をもつ。 本書は基礎理論であるので具体的な変革理論を表すものではないが、しかし、個別具体的な展望への道筋というものは、出せたものと考える。 そうは言うものの第4に、既存の社会変更の理論は、革命論という名の政治理論と、組織論という名の革命運動への動員言説のみで占められているものだ。現実の生活行為に結びついた社会変更の理論を人々が作り直す際には、これらはいったん否定される必要がある。本書はその中の、とりわけ上部構造相対的独立説への反立言に重点をおき、これを否定している。いわば、前衛主義の否定である。社会科学は真実を述べればよいというものではないが、かといって虚偽を述べることは許されない。前衛は存在すべきではあるが、それは歴史の一要素に過ぎない。 結果としては、このような意図が、100%実現されたとは到底いいがたいけれども、本書が他の社会学の研究と異なる点は、主としてこのような意図のうちにあるので、読者はこの意図をくんで本書を評価してほしいと考える。 (中略) 本書は序を除き3部、7章に分かれる。 第1部は、歴史性をある程度まで捨象したレベルでの、行為者に関わる要素を取り上げている。 第2部は、現代の行為者を規定している社会的な諸要因である、経済的な規定因であるいわゆる「生産関係」と、暴力的な規定因である国家権力について、それらが行為の諸原理と原則をどのように規定しているかを取り上げている。ここで、両者は歴史の産物であり、歴史性を捨象してはほとんど意味がない。このため、資本主義的生産関係と資本主義的近代国家に焦点を当てながら述べることとなる。 第3部は、行為者が行為者を規定する経済的な規定因、あるいは暴力的な規定因を変更しようとするにあたっての法則的立言はどのようなものとなるか、が検討されている。 ついで、各章別の意図を述べれば、 第1章は、この理論の基礎である個人の行為の原理と原則を述べている。 詳細は本文に任せるとして、その実質は、行為者が次の行為の先に将来のイメージとして次に掲げるものを抱ける、という点にある。それはこれからの自己の諸行為によって、第1に、行為者の身体的存在を確保できること。第2に、行為者への社会的賞賛が得られること。第3に、行為者に他者からの優越を根拠にとして自由を与えられるということ、である。さらに、これらのイメージの根拠は、それが社会的事実として存在する、という認知にある。 これらの概念は、人間が行為する場合の行為の次にみている将来イメージの評価基準の構成素を指すものであるが、この意義は、これらの概念をもって、人間行為を説明し、さらにそれ以上に、私たち人間行為者がその結果を自身の行為の前に把握することができる、ということにある。このことによって、私たちは、未来の社会に生ずべき障害を避けるとともに、新しい社会を自前の力で作っていくことができる。 本章で示す立言は、そうしたプラグマチックな意義をもつものであって、個々の概念の衒学的な意味を示すことに意味があるわけではない。つまり、ここにあげた「賞賛」なりの用語の漢字が持つ意味が、それそのままに構成素の本質を指すというわけではない。人間行為には当該用語が代表する反応群が存在するということであり、別の言葉が適当だというならそれはそれで構わない.一括変換して読めばよいだけである。筆者はそのような瑣末な事情にこだわる気持ちはない。 なお、本章は、とりわけ、拙著『変革の機制』において展開されたものである。 第2章は、社会関係内での行為の原則について、行為者から見た行為の諸要素が、社会関係の中でどのような意義を持った要素に変わるかを述べている。 とりわけ、社会関係の中で「支配」が現れる状況と、その支配が、第1章で示した行為の原理と原則を通して、社会にどのような特徴を形成しうるか、という点について、この規定性を「行為共同性」と呼び、立言化している。 本章に限らず、展開されている論理では、本論中の一々の立言に意味があるので、それ以上の要約はしない。 なお、本章は、とりわけ、『変革の機制』において展開されたものである。 第3章は、行為の原理のうち、事実認知という側面について、これが社会関係の中でどのような意義を持った諸要素に変わるかを述べている。いわば、人間における観念性の由来を記述している。 それは規範やイデオロギーといった、人間の生活を分析する科学へ夾雑物を増やすものではあるが、一方、そうした夾雑物に合わせた弁証法という方法を、人間にもたらすものでもある。 なお、本章中「情報一般」に関わる部分については、とりわけ、拙著『風とベイシティ・キャット』において、また「イデオロギー」に関わる部分については、拙著『光の国のダンサー』において、展開されているものである。 第4章は、生産をめぐる関係についての基礎的な概念整理と、資本主義的生産関係が行為者にどのような規定性を与えているか、を述べる。それは、第1部で述べた、いわば行為本来に由来する事象が、とりわけ、資本主義的経済法則の中でどのような社会的表出をするか、という点について述べることでもあり、逆にいえば、資本主義社会という体制が、衣食住という人間の身体的諸条件の確保を通して、一般的行為者をどのように取り込んでいくか、という点を述べることでもある。 なお、本章中、関係一般に関わる事項は、とりわけ、拙著『光と影とネズミの王様』において、また「生産関係」に関わる部分は、とりわけ、『変革の機制』において、展開されているものである。 第5章は、国家についてである。国家は、行為の原則のうち身体的諸条件の確保=生理性について、その武力的暴力性において行為者を規定する。 それは、もともとは、一般的行為性のうち、「支配」を通じて成立しうる社会事象ではあるが、その国家が、資本主義経済において、経済的諸条件を取り込みながら、さらに事実認知に関わる諸制度を取り込みつつ、自己の権力を継続させていく過程を立言化している。 同時に、そこでの行為共同性が、各種の具体的国家の諸特徴を規定する点について、追記している。 なお、本章中「国家」に関わる事項は、とりわけ、拙著『パリの爆薬』において、また国家の形態に関わる部分については『光と影とネズミの王様』において、展開されているものである。 第6章は、行為の原理のうち事実認知に関わる諸制度が、資本主義的生産関係および近代国家の中でどのように規定され、あるいは、行為者をどのように規制するかを述べている。 いわば、上部構造が、資本主義的生産関係によってどのように規定されているかを述べるものである。その結果は、マルクス主義で最も教条的と思われる類の土台‐上部構造論を追認するものである。 なお、本章中「情報」に関わる事項は、とりわけ、『風とベイシティ・キャット』において展開されているものである。 第7章は、第3部の社会変更の諸立言を1章でまかなっている。 まず、第1節から第3節までにおいて、いわば全体社会の自生的な変動過程を述べ、第4節において、いわゆる社会運動の一般規定について述べ、第5節から8節までで、社会運動の本質的な意義を検討し、第9節において、社会を変える要因としての戦争について述べ、第10節において、いわゆる革命について述べる。 本章の諸ポイントは、決して何行かのまとめで総括されるものではない。1センテンス、1センテンスの立言が、人間行為者が将来にわたって使用すべき社会科学的知識の重みを背負っている。 なお、本章中「社会変革」に関わる事項は、とりわけ、『パリの爆薬』において、また運動アピールに関わる部分については『光の国のダンサー』において、展開されているものである。 |
| コラム | それでさ、この出版社、デジタルパブリッシングサービスというのがこの時期とんでもなくてさ、 とにかくメールでせっつかないと何もしない。 言ってる約束は、似たような違う約束、 新刊書籍取次に出すといったって出しゃあしない、 これが一番痛くて許せない。人のマスターピースを。取次に出す=図書館が買う(検討をする)。これがあるから出版契約したのに(この時期、契約料高かった)。その意味がゼロになったのだ。 本来あるほずの出版書籍の概要紹介もゼロ。それでどうやって人が買う気になるのか、教えてくれよ。 もっと言っちゃうか。その後ずいぶん経って、別の担当者がメールで「引っ越したんなら知らせろ」とか偉そうにいうんだね。すでに知らせて新住所で郵便来てるのにさ。でもおとなしく「ご存じのはずですがお知らせします」、といってもウンでもスーでもない。で、もう付き合うのをやめたの。 まあ、わたしも優しいので半分は性格の不一致にしといてあげよう。 ともかく。こんな体たらくでどうやって黙っていろというのかね。 前は担当者がよかったんだよ、大塚正志さんていう、対面だったらお友達になれそうな人。 ところがさ、この時の担当者がこのざまさ。そんなのに限って偉くなるのは世間の習い。 でもこれが私の好きな大学隣級の倫社の教師、木立M敏君の教え子のはずなんだね。いつか木立君に会ったら怒ってやろうと思ってるんだ。 |
−行為論的社会学応用理論
 |
” 本論は、人間が営んできた自由の進展の歴史過程を再構成することで、第1に、全体社会の変更という、人間史に必然的な未来を明らかにし、第2に、人間が獲得すべき支配なき絶対自由の社会の道を示す。 ついで、人間がこれまで受け続けた疎外からの脱却の過程を描くことで、人間が持ちうる二種の意義を明らかにする。第1に普通の生活を続ける人間であることの意義と、第2に、これと等価に存在する、変革の意志を持つ人間であることの意義である。 本書は、社会科学の書であり、従ってなお、人間存在の書であろうとしている。 ” この本も、残念ながら、本格的理論書です。 |
| (あとがきより) 本書は、前著「行為の集成」とはうって変わって実用的な書である。もっとも本人の心の中ではうって変わっているのであるが、相変わらずの読みにくさかもしれない。なんとか「補註」等で補完できればと読みやすくしたつもりであるが。ただ、全部を読みやすくすると、1冊の分量をはるかに超えてしまう。それはどうもよしたほうがいいと考えた。 (略) ということで、本書は、行為の理論を基に、社会システムの変更について、序説から本論、結論まで述べた書である。 (略) 緒論は、まずはじめに、本書の性格と理論枠組を述べる。第1節については、いわば本書の社会科学上の位置づけを記したものであるから、一般の読者の方は、第2節から読まれることで差し支えない。 第1節は、本書が前著『行為の集成』の続編という位置付けであること、前著が基礎理論であるのに対して、本書は応用理論であるということが述べられている。つまり、変更の方向性の行き先は問わなくとも、社会学の応用とは社会を変更していくことにある、その方法を述べるのが本書である、ということである。 ついで、第2節として、著者の作品にはいつも記載している隈行為理論の基礎部分を記している。こちらは本書の基礎であり、隈の行為輪をまだご存知でない方は、ぜひ目を通しておいていただきたい。なにも納得される必要はない。以下の行論と読み合わせながら、その真偽と有効性を検討していただければ、と思う。 次に、第1章は、社会学の対象とする社会とは、歴史的な社会であり、その社会の規定要因は、「支配」である、と述べている。 歴史というものは、人間がおのおのの個人として自由を追求して作り上げてきたものである。そしてそれは、これからもそうである。 しかし、その過程は同時に、他者を不自由にする過程でもあった。すなわち、支配である。世界史は、この支配からの脱却の過程である。 人間を拘束し疎外する根本要因として「支配」を上げ、これを基本的に解明している。 第1節は、普遍的に捉えた場合の社会的な支配について、その由来、その規定性について述べている。 ここでは、国家による武力支配及びこれを基盤とした資本主義システムにつながっていく経済的支配以外に、共同体による支配という要因を忘れてはならないことが指摘される。 ついで、第2節は、支配社会での人間は、それぞれの社会的位置に応じて疎外されていること、「疎外」といってもマルクス主義における「疎外」とは異なり、行為論的に疎外されていることが述べられる。 歴史の中で生きている人間が「支配」により自由の疎外者となっているということである。 すなわち、疎外事象の原因契機は、根源的には私有財産でも資本主義的生産様式でもないこと、それは社会における支配である。 ついで第3節は、そもそも「歴史」とは、生きているわたしたち人間個人にとって何なのか、ということについて述べている。 人間は、主体的に歴史を構築する。である一方、本来の人間行為は、自由気ままである。社会に法則があるわけではない。しかし、社会は法則的に捉えることができる。そう捉えることができることを認識することが、人間が生きる際に重要なのである。なぜなら社会的人間は、他の人々が生きている中で生まれ、他の人々の中でいき、自分が死んだ後も他の人間が生きていく中で、自己の生きている意味を見出すしかないからだ。 なお、マルクス・エンゲルスの唯物史観について、その基本的な誤りを指摘している。 さて、第2章は、そんな歴史法則上、変更の行方の決まった社会から、どうやって人間が意志的に社会を変えてゆけるのか、その諸条件と諸方法を、現在の資本主義社会にいる人間という立ち位置から述べている。 第1節は、資本主義は、階級社会とはいえ、決して自由に関して束縛的な要素ばかりではない。歴史は、それまでの束縛性にしばりをかけ、新たな自由を人間に与え続ける社会であることが述べられている。 人間は生産力の向上を持って、資本主義社会として、自らの自由を作り上げた。わたしたち被支配者が自由を手にしうる可能性を帯びたのが、資本主義社会である。資本主義社会とは、支配権力者が分裂したシステム、すなわち、武力権力者の末裔と、このシステムに食い込んだ経済権力者層との統合システムのことである。自由を手にし得るといってもそれは可能性に過ぎないのだが、それにしてもこれがそれ以前との巨大な違いである。 第2節は、資本主義においては、支配社会下の人間の疎外が、どう存在しているのかについて述べている。資本主義の用意した「自由」の中では、疎外は決してなくならない。その状態に、人間はどう対峙しているのか、について述べている。対峙といっても闘うばかりではない。人間は、環境に耐えつつ、まずはなんとしても自分の生を生きなければならない。 第3節は、資本主義の腐朽について述べている。 資本主義は、人間の歴史上、最後の階級社会である。過去、レーニンによって後進国植民地の「寄生」と喝破された帝国主義は、自立的な経済的システムとしてはすでに崩壊している。 資本主義の腐朽とともに資本主義国家も崩壊の危機に立つ。いいかえれば、資本主義という経済体制の腐朽は、それに依拠した支配者という環境を持った人間の腐朽でもある。この状況の中で、疎外された被支配者と腐朽した社会的位置を背負った支配者の双方が、資本主義に反乱をする。 第3章。ここでは、それでは人間の反逆、つまり全体社会の変革行為がどのように起こるはずになっているのか。またそこで作られるはずの新しい社会とはどういうものか、これらが述べられている。 といっても、具象的なものではない。「本質」のある社会での表現形態というものは、そのときどきの全世界的な関連で動くものであり、今の時点で何を書いても未来ではただのウソになる。本書の叙述は、あくまで、ある歴史的時点で、そのとき生きている人々が押さえておくべき、その当時の現実の規定性のみが述べられている。 第1節は、支配者と被支配者の双方に生ずる、環境への対決の叙述である。 資本主義による疎外状況から発生した不満を認知した行為者は、本項で述べていく引き続く契機の下に、支配への反抗を開始する。それは、自己が生きていく中で培ったその時点での行為の原則の結果の自己認識に反して、しかし、行為の原理・原則のとおり、生理性にひざまづき、自己認識を捻じ曲げられた人間である自分の自己分裂に対する、あるいは自己分裂を引き起こした元凶のはずの社会システムに対する、反逆である。 第2節は、そうした人間がたどる諸過程について述べている。人間の解放の社会とは、これまで検討した支配と自由との2項図式の収斂として、その限りでただ一通り、生ずるものである。それは経済に囚われた必然の王国から、人間の意思により社会を作り変えてゆく自由の王国への旅である。 第3節は、当該国家の世界上の位置で変化するそうした旅を経た後にたどり着く、最後の階級社会である資本主義が用意した限りでの新しい社会について、その論理的予定性を解明する。 ここで扱われる課題は、過去から今まで種々の論者により自在に論じられてきた、未来社会の経済体制がどういうものか、というものではない。疎外の消滅のためには、社会に存する各種の個人行為を規制する要因から、個人の努力ではなく制度の変更によって、個人の行為を守る過程が生ずる必要がある。ここでは、過去論及されていないこの問題について取り上げる。 なお、本節で取り上げるのは将来社会の青写真ではなく、現実に生ずるはずの論理=原理である。それはいわばただの思考実験の想定結果ではあるが、他方、いわば解放への諸条件の解明でもありうる。 (略) というわけで、本論は立言の束によって構成されているわけだが、それでも、トータルとしての意味ないし意義というものもある。 何度も言うように、学問は人の役に立たなければ科学ではない。『人間における室温と布団の掛け方』学は、その中に因果関連は発見できるであろうが、これを人は科学とは認めない。 もっともこの「学」を擁護はできる。「これだって、ロボットによる高齢者の自動看護には役に立つさ」。まことにその通り。人間の役に立てば科学と名乗ってよい、ということである。 では、本論でわたしが意図した、本理論が持つ意義づけはなにか。 本論が描いてきた自由の進展は、第1に、全体社会の変更という、人間史に必然的な未来を明らかにし、第2に、人間が獲得すべき支配なき絶対自由の社会の道を示す。それは、今の時点ではただの論理にすぎないが、マルクス主義の信奉者があたふたとその主義を捨て、さらには「過去の」その自分の主義を否定しまくる惨状の中では、これは大きな意義であろう。それはマルクス主義に身を寄せて言えば、立場こそ違えど、二十代の若きエンゲルスとマルクスが、根拠は不確かにせよ洞察した未来を、理論的に描き直した、といってもよい。 ついで、もう一つ対比して描いた、人間がこれまで受け続けた疎外からの脱却は、普通の生活を続ける人間であることの意義と、にもかかわらず、変革の意志を持つ人間だけが持つ社会の変更に寄与する意義という、それぞれの意義を明らかにする。前衛が偉いわけでもない、誰が偉いわけでもない。しかし、一人の人間が引き受ける自分の人生の意味を明らかにすることが、その時代において同じ社会内で「学」を受け持った、他者である人間がなしうることなのである。 ( 少し時間が経ったのでもう書いてもいいかな、後書きの記載日が1年ずれていて、これは校正時「10月」だったのを編集校正で「1月」にして済んだと思ったんでしょうね。年が変わるとよくあるやつ。自分の仕事でも今年になって他人の同じミスをいくつも直しましたが、これは手元に来たときにはもう本になってたんで何も言いませんでした。どうせ主文は2年前に書いたものだから間を取ってちょうどいい日付かもしれないし。 が、おかげさまで怖くてそれ以上ページを開いていない4/3。まあどうせ1年もすれば全てが済んだことになりますし。) ) |
 |
” およそ社会の経過は唯物史観が示すとおり、人間の主観的意思の如何によるわけではない。下部構造たる経済過程に規定されたものである。 しかしながら、それでは人間は歴史に流されるだけか、といえばそうではない。あるいは人間は歴史の必然を生きることが自由だ、などというマルクス主義者の言が真実であるわけでもない。 逆である。人間は主体的に人間社会を変更することができるから、この移り変わる歴史が不可避的に存在するのである。 本書は、人間が下部構造に規定されている、かのように見える規定性を明らかにしつつ、社会に表れた人間の主観的意思の観念性の秘密を暴き、他方、その下部構造の規定性を形成する行為者としての人間の行為論的自由の意志の歴史過程を明らかにするものである。 この本も、残念ながら、本格的理論書です。 |
| (あとがきより) さて、本論である。筆者としては、前2著によって、思春期以降考え続けてきた論題には全て応えられる「はずだ」、という地点まで達したところだが、この決着を潜在的な「はずだ」から、「実際につけた」と考えるものが本著である。 本書で筆者の理論の積極的な仕事は終了である。筆者としては、行為理論的な社会学原論については、資本主義社会の最後まででは、究極的に結論をつけた、と思っている。「行為の集成」「歴史としての支配」そして本書が、その三部作と考えている。基礎的一般理論である「行為の集成」、応用理論である無政府主義的自由を描く「歴史としての支配」に次いで、個人の「目的」がシステム拘束的な社会過程において、いかにして意味を持つか、を描いたのが本書である。もちろん社会科学的には、上部構造の理論にかかる積年の「疑念」をクリアに解決したものである。 本論に入る前に序論として、これ以降論述される枠組みについて述べておいた。第1に、本論で対象となる社会事象を確定し、第2に、その分析は、主観と客観を統合した方法、すなわち、主体としての行為理論と、客観である主体を拘束する諸関連との東郷として行うこと、そしてその統合を叙述するのは、本来の弁証法ではなく、資本論と同じくただの「概念の弁証法」、いわば「裏の弁証法」で行うことを述べる。ここまでは基礎理論に興味のない方は、目に留まったところだけご覧いただければ良いのかもしれない。なお、本論で利用する隈の行為理論について、最低限を載せておいたが(第3節)、こちらはご存じない方には目を通しておくようお願いしたい。 次いで、第1章。 まず私たちは私たちが生きている、私たち本人の姿を問題にした。ここでは社会には立ち入らない。現実の社会が持つ人間への拘束性は、個人の一般環境としてのみ問題とされる。 ここで扱うのは、個人行為者が社会について行う環境把握の為し方である。人間は観念論者であろうと唯物論者であろうと、同じく頭脳によって環境を把握する。これを観念的と言おうがなんと言おうが、人間に必ず存する生存に必須の観念過程である。この過程を通って初めて、土台は上部構造に反映するのである。 次いで、第2章において個人の一般環境とされた社会の拘束性の、資本主義社会が持つ具体的な私たち全てに対する規定性をみる。資本主義社会の私たちへの規定性は、その具体性としては、いわば釈迦如来の掌の内の孫悟空のように、土台に規定されているさまを記している。相対的に独自な武力を有する支配権力さえ、資本主義的土台に拘束されているからである。 といって、マルクス主義者が主張するような資本家による国家支配が存在するわけではない。支配者は、資本主義を自己の生理的条件の基盤としつつ、しかし人間行為者として自由に振舞う。 しかし、人間が土台に規定されっぱなしになる、というのも少し違うのではないか、と思われる方もおられるに違いない。人間というものは、主体的に動き、そして社会も変わるものだ、と。その通り、人間は主体的に歴史を作り、今日も作り続ける。その人間主体の超越性と、かつまた限定性が第3章に叙述される この第3章においてようやく唯物史観はそれを構成する各構成素の確認のレベルを超えて、統合した、それ自体で評価さるべき、社会視角とみなされる。第2章のように支配者のいいようにされた行為主体の表現行為は、しかし、そのままでは終わらない。被支配者は、行為共同性と対抗権力に支えられながら、自発的行為に沿うように表現行為を整えることが可能である。 この結果、被支配者たる人間Aは自分と同じ行為共同性の中から発する社会運動について、それにより行為共同性内に自分にとっての新たな賞賛と優越を見出す。この賞賛と優越により、人間Aは自分の立場に応じて、決定的な運動を遂行し、制度を変え、さらに次の時代を生きる人間Bは、その制度から次なる社会運動のサイクルを担うのである。 |
 |
” 「有史以後のすべてのこれまでの社会の歴史とは、国家による強奪の歴史である」。マルクスへの根底的な批判と共に今お届けする世界資本主義の過去と未来の真実。 人類の歴史を彩り続ける不幸な、しかし栄光の諸闘争が、営々と形作ってきたこの人間の自由。世界資本主義とはその現象形態であり、この過程を貫く論理を明らかにしたとき、次なる自由の段階と、それらを全世界的に最終解決する未来とが明らかになる。 隈栄二郎が自己の社会学の全論理を傾注して作り上げ、その実現を後に続く者たちに託す、世界についての最後的論究がこれだ! この本も、残念ながら、本格的理論書です。 |
| (序より) 本書は序を除き2部、7章に分かれる。 第1部は、資本主義の本質とその本質の影響力の限界について、社会科学に基づき、つまり行為論的社会学に基づき、その規定性が持つ因果連関を述べている。資本主義がその上に載っている基盤は支配社会のシステムなので、隈の前著とかぶらないようにしながらこのシステムについても述べている。とりわけ本著の焦点は、先進国でマルクス主義者にさえ見えなくなっている階級構造をめぐるシステムである。資本主義とは世界資本主義のことであるから、当然、ここには資本主義に直面した後進国が辿る状況をも含んでいる。 第2部は、将来状況の説明である。つまり第2部の趣旨は、社会科学的因果連関の立言の提出、それ自体ではない。筆者が第1部で解明済みの社会学上の因果連関の立言を将来状況に当てはめればこうなる、という説明である。といってしまうと、あまり科学的価値がなさそうだが、本部の説明内容を積極的に言えば、「資本主義の腐朽過程の存在により、なぜ資本主義が崩壊しなければならないか、を述べ、さらに、なぜその歴史的時点が、人間の有史以来の支配社会の終焉となるのかを述べる」ということになる。 ついで、各章別の意図を述べれば、 本論に入る前に序論として、資本主義論に入る以前の社会科学上の確認事項を述べている。序論では、本論がそうである社会科学と、本論があたかもそのようにも見える箇所がある歴史学と、これを扱うわれわれ主体の位置づけとについて述べる。これら3項はもちろん密接不可分のものであるが、たかだか数十ページの序論なので、この論述には弁証法的な細工は施さず分断して述べる。ただ、だからといって諸項目が絡み合った構造が変わるはずもないことにはご留意願いたい。 わかりづらいので少し解説すれば、行為主体が自由であること、あるいはさらに自由になることへの意思自体が、人間にとっての社会科学の方法に対して、第1に、科学的=因果解明的であり、第2に、主体的であり、第3に、歴史的であり、第4に、人民的であり、第5に、変革的であることを要求する。 これにより、人は、社会科学の研究、叙述に当たっては、3つの課題を意識し、これをクリアしなければならない。第1に、行為としての主体性。これは、これまで隈の行為理論として再三述べてきた。第2に、視えないものを見る、という規定因主義。第3に、この第2の立場は第1の立場をも規定する。視えない自分の場所を見る。時間と空間を越えた自己の場所的立場において、自己の主体性を取り戻す。時空を同じくしているがゆえに、人民は、国家を超えて自己の自由を得られるのである。とりわけ、資本主義の検討は歴史的にされるだろうとお考えの読者が多いだろうことに鑑み、歴史岳と社会学の違いについて焦点を当てている。 ここまでは基礎理論に興味のない方は、目に留まったところだけご覧いただければ良いのかもしれない。なお、本論で利用する隈の行為理論について、最低限を載せておいたが(第3節)、こちらはご存じないで方には目を通しておくようお願いしたい。 次いで、第1章。 ここに、社会の支配システムについての可視と不可視の理論レベルの重大な齟齬、実はそれこそが科学の本質の現象形である2つのレベル間の差異についての議論が押さえられている。支配とは、支配組織のことでも資本家組織のことでもない。人民が刃向かえば困るシステムのことである。この「システム」について、その依って立つ所以、その社会に現れる状況について、基礎的に述べている。 次いで、第2章。 世界資本主義の法則的運動についての論議を淡々と続けていくには、社会科学の歴史に関わる或る障害がある。マルクスの「資本論」である。 第1章において、有史以来の社会に存する支配システムについて述べてきた。これは本来、資本主義社会においても同様なのだが、とりわけ現在の社会科学においては、同様とみなされてはいない。ここで問題なのがほかならぬマルクス主義経済学である。 現実に歴史に起こった変化は、支配者が商業従事者に私的所有という権力を加えたという事象のみである。これだけが、唯一つ、制度上起こった変化である。にもかかわらず、大方の社会科学者の間では、いつの間にか支配者は資本家に代わり、人間の労働を収奪し続けてきた支配者の歴史は、これまた「搾取」と称される「労働力」の「等価交換」なるものに変容され、支配の歴史が継続しつつあることは抽象の闇に隠されてしまった。この事情をもたらしたのが「経済学批判」=資本論である。資本主義社会は資本家が作ったものではない。それはそれまでの支配者が、あるいは国家が作ったものであり、そしてありつづける。これを透視できなかった資本論を、まず批判しておく。 ついで第3章が資本主義的支配システムの成立とその腐朽である。 支配システムが歴史の中で資本主義という経済システムを選択したことで、支配システム自身にどのような性格付けの変化をもたらしたか、を述べる。 ついで、資本主義の進展が、その進展という事実によって、もう一つ別次元の要素を歴史に与えることを述べる。武力と行為共同性である。この過程が、資本の過剰とあいまって、資本主義を腐朽へと導く。 統一的な武力システムが確定した先進国においては、支配権力自体と経済法則は、変わらない、あるいは変われない。が、その中で人民の自由は成長する。その秘密が行為共同性である。もう少し具体的にいえば、不可視のシステムとしての「階級」であり、可視である身分と意識の諸形態である。この行為共同性による歴史の進展を説明する。 第4章は後進国である。 第3章までの先進国の現状の規定性の次に、これまでの純粋資本主義的な議論では語れない世界資本主義の局面を押さえておく必要がある。後進資本主義国の事情である。現在、世界資本主義の中において窮乏化の法則の最底辺を担っている後進資本主義国には、独自的な経済規定、あるいは生産関係規定と、さらにその過程における武力水準と行為共同性の独自性がある。この件について、後進諸国を通じた一般的因果連関の抽出を試みる。これにより資本主義成立以降の世界史的法則性が一貫する。 第5章は資本主義の崩壊である。 現在進行中である世界資本主義上の窮乏化の法則が実現したときに、資本主義は崩壊する。初めに行われるのは資本主義から離脱する革命である。何かを目指した革命ではない。これが歴史的法則の重要な規定性なのである。自由に将来が決められたらそれは資本主義ではない。やむにやまれる進展が、歴史の規定性なのである。 過去の筆者の著作ではこの変更過程についてそれぞれの著作の視角から述べてあるが、本書では、第1に、人々の資本主義否定の動機が運んでいく体制の性格を述べ、第2に、この体制の性格がもたらす、次の体制である「真の」共産主義体制への変更可能性について述べる。 第6章は新社会の規定性、変更される社会の向かうべき地点である。 ここで必要なものは、既存の洞察や思い付きの厳密化ではなく、行為理論という根拠の元での過渡的な理想状態の理論化である。 本書ではそれ以外のことは記さない。過渡的な理想状態とはなにか。それは、悪意ある支配権力者がいたとしても、その悪意を社会の拘束によって発揮させない状態であり、本章ではこれを記すのである。つまり、「国家」という実は「支配者」が行う、人間の自由の拘束行為への制限の方途である。 |

ー主意主義的変革主体論の理路
| (「はじめに」より) 本書は序論を除き5章で構成される。 各章別の意図を述べれば、 本論に入る前に序論として、本論が基づいている諸前提を記すことで、本論の流れを事前にわかってもらえるようにした。 筆者は、過去、もっぱら「社会のシステム」に焦点をあてて議論を続けてきたが、本論はそれとは全く異なり、「具体的な個人」の意思に焦点を当てている。これに伴い、「社会」も全体社会ではなく、個人を直接に取り巻く集団、構成体、要するに「下位体系」に焦点を当てる。その理由をかいつまんで述べている。 同時に、個々の人間の行動に焦点をあてるという個別的な努力が、どうして因果連関の法則を析出すべき「科学」となるのか、を述べる。 この序論は見通しをつけるための議論であり、その後の内容は本論で展開している。従ってざっと眼を通していただければよいかもしれない。なお、本論で利用する隈の行為理論について、最低限を載せておいたが(第2節)、こちらはご存じないで方には目を通して頂いて、必要な折りに振り返っていただくようお願いしたい。 本論に入って第1章である。 ここでは具体的個人の行為、すなわち生きている人間が実際に日々暮らしている下位の社会体系内の行為とは、その内部の行為者にとってどのような規定性を持つのか。そしてその規定性を担った行為が、では上位の社会体系の存在にどんな影響を持ちうるのか、が述べられている。 もっともここで述べているのは社会システムと具体的人間との関連であり、いわば解放行為の因果連関を述べるにあたっての予備的な作業ともいえる。直接に解放行動について述べるものではないので、社会学に興味のない方々は流し読みでも構わないだろう。 その他の章に出てくる概念で既存の社会学にないものを解説している。上位体系と下位体系を「縦断する平面」と、その平面を切り取るための「要素連関」というものである。ただこれも筆者としては他の章では文脈の中に溶け込ませた積りなので、「そういう発想から論述している」と思っていただくだけで、大きな支障はないと思われる。 なお、本章は、具体的人間を扱っているその他の社会学との違いを際立たせるため、他章の簡潔さに比べ、少しボリュームを増やしたところがある。 次いで、第2章。 本章は多くの読者には失望されるはずの、日常の中での「解放」について注意書き的に触れた章である。人が諸集団等の中で生きるにあたっての「解放」である。もちろんそんな「解放」は限定的なのではあるが、ある具体的個人にとっては、その解放こそが彼の「人生」たりうるのである。この点について、人間の存在への敬意をこめて、章として述べるものである。 その結果として、下位体系内で行動する具体的個人への権力の浸透度と、その権力の被支配者個人による利用可能性について述べてあるので、ここはそういう章だ、と理解されたい。 次いで第3章が、具体的個人の「いわゆる解放行動」と上位の社会体系の変更について述べるところである。 読者はここで、社会変更にかかる具体的個人の意思が生む可能性と限界性の理路を、つまりその過程と根拠を、読み取ることができるであろう。そのときにはついでに、社会変革をめぐる常識論や感情論の誤りへの批判も読み取っていただければ幸いである。 内容は個人の行為とそれが全体社会に与える影響とその根拠を、その根拠に即して整理した。本来は羅列的でないほうが個人に即するのであろうが、現実の個人の環境は千差万別なので、羅列的になるのも許していただきたいところである。 第4章は差別である。 筆者は差別は当時の社会システムの直接の規定性に基づくものではなく、2次的な現象であると把握している。 2次的だからその解放はたやすいとか言おうとしているのではないし、2次的だから「1次的な」状態の解消まで差別からの解放はあり得ない、と言っているわけでもない。 しかし、2次的な事象には2次的な規定性もあるものである。つまり、「体制相手の戦いとしては闘いやすい」のである。大まかな話をすればここでの解放行動は、困難ではあるが、解放が上位体系の支配構造に達するまでは勝利しうる、ということはある。ただしその一方で、体制反対ではあっても基底還元主義的な議論を奉ずる差別者とも闘わなければいけない、という側面もある。別枠で論ずる所以である。 さて、第4章までの議論は、具体的行為者の主体的意思の限界を探ったと集約してもよい。残念だが、個人行為者が社会的抑圧の解消を意思しても、その人間の「意志」によって解決できることには限界がある、正しく言うと歴史が人間に架した規定性は乗り越えられないのである。さて、ではそこで人は腕を組んで立ちつくすしかないのか、ということである。 そうではない。人は常に歴史を先導して変更してきたのである。 新たな論理的段階として展開する第5章は、新社会の規定性、変更される社会の向かうべき地点である。 なぜ新社会の規定性が第3章で展開できないのか、それは新社会が具体的人間が作り出す関係を前提として初めて存在しうるからである。 第5章では、ここではその関係を作りだす行為主体の規定性と、彼らが下位体系という環境内の変更ではなく直接に全体社会を変更させる過程について述べてある。 |
お買い求めは、
「「上部構造」の社会学」、「資本主義と支配システム」は、一般の書店やネット書店でも取り寄せてくれるはずです。
「解放行動の原理」は、ネットの”BookWay”、または”Amazon”さんからお買い求めください。
それ以外の書籍はすでに在庫がなさそうですので、著者、隈までメールください(隈へのお問合せのページ)。
あとは本人は残念ながら、古本屋さんになってしまいます。
![]()
| ・ 隈の紹介 | ||
| ・今回のトピック | ||
| ・ (旧)今月の話題 | ||
| ・ 隈へのお問合せ | ||
| ・ 隈からのお答え | ||
| ・ ホーム | ||