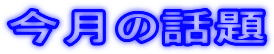

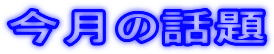

ここは<その2>でして、隈のホームページ「今月の話題」で、03年9月から04年2月まで掲載した分の再掲です。
ページが重くなるので前後で2つに分けました。03年8月分までをご覧になりたいかたは、こちらへどうぞ。
| 《社会の中の社会情報》ーその4 【9月分】 さて、論理には真偽とはもう一つ別なものがあります。「思想」というものです。 真でも偽でもないものなんかに興味がない(私のような)真摯な学者・研究者的な人もおられるかもしれませんが、現実はそう他人事ではない。 そういえば、前々回の丸山真男なんかの関連で、こういう論題があります。この著者は、「政治社会学者」とでもいうところでしょう。 ちょっと長くなりますが、半分は感心できる話なので我慢してください。 中野敏男「大塚久雄と丸山眞男」青土社、2001。 p213 「要するに、戦後啓蒙家=丸山の「日本」批判は「日本を作る」という仕方の批判だったのであり、これは、敗戦という決定的な岐路にあつて「日本」を割る責任を回避させ、内向きに課題を与えることで「日本人」を国民としてまとめるのに役立つていると考えなければならない。だが、近代帝国主義の角逐という時代にある近代日本の侵略戦争や植民地主義が、「日本人」の「未成熟」や「国民性」によって引き起こされたものだと考えることはできないだろう。中心的に問われなければならないのは、むしろ近代日本の帝国主義と植民地主義なのであつて、この批判と清算のためには、近代国家=日本の政治、社会的分析と批判が徹底して遂行され、この近代日本の総力戦体制について責任ある指導者たちの退場と組織の解体の作業がなされなければならなかったはずなのだ。 (読みやすいように私が改行しました) ナルシスティックに内向する丸山の「日本」批判は、しかし、自立した「主体」を求める啓蒙の立場から「未成熟な日本」に批判の眼差しを集中するまさにそのことによって、この近代日本への批判についてはそれを後景に退ける役割を果たしたと見なければない。このことにより戦後啓蒙は、「暗い谷間の時代」を一刻もはやく脱して戦後民主主義を謳歌したいという一般的な気分の中で、「近代化」による「戦後復興」の道に一目散に突き進むことによって脱植民地主義化という課題を自ら直視することがなくなっていく戦後日本の言説シーンを、強カに方向づけたとわたしは思う。すなわち、帝国主義的国民主義という記憶を抹消し「単一民族」的国民主義へとこぞって向かうことで乗り切りをはかる戦後日本への変身は、この戦後啓蒙の言説によって問違いなく加速されたのである。 鹿野政直が明らかに直感しているように、丸山眞男らの戦後啓蒙の言説は、占領軍の主導化で「怒濤のように」進行した制度上の戦後改革と表裏をなしている。だがこの鹿野によっても洞察され切っていないのは、この戦後啓蒙の言説とアメリカのヘゲモニー下での戦後改革とが実は相互補完的に支え合っているということである。考えてもみよう、もしこの戦後啓蒙こそが、「近代化」と「民主化」という第一の目標に戦後日本の人々の意識を集中させることで、日本において近代帝国主義の記憶をむしろ封印し、思想の上でも実際の物質的負担の面でも厳しい試練を課すはずであった帝国主義宗主国の脱植民地主義化という課題を素通りさせるのに貢献したのであれば、それは、「ファシズムvs民主主義」という図式でこの帝国主義戦争を解釈し、「民主主義の教師」という自己了解をもって戦後東アジアにも覇権を求めていくアメリカの戦略思考にとつて、まことに好都合なことであったはずなのである。丸山が描き出す「超国家主義」の「ため息の出るような非合理性」とアメリカから教え諭される「近代」の「軽快な合理性」とがちょうどコントラストをなして「戦後日本の近代化」のイメージが構成され、脱植民地主義化という近代批判の課題よりは、一日も早い近代化と戦後復興へと人々の意識を駆り立て動員するという、この戦後日本の道が開かれてきたのはまず問違いのないところであろう。とすれば、戦後啓蒙としての出発時の丸山眞男の問題性は、戦後日本に総じて問われるべき問題性として今日にまで響いてくることになる。 うーん、長い。こんなに長く書き連ねる必要はないね。 簡単に言えば、丸山真男はみんなが進歩派だっていうけど何もそんなもんじゃない。資本主義推進派そのものであった。ということが一つ。 ま、それはそれでいいです。よくぞ言い切ったと思いますが。(言い切ってない? 多分言い切ってるんじゃないかと、、、、) 問題は次で、せっかくそこまで喝破しているのに、続けて言うのが 「この戦後啓蒙の言説とアメリカのヘゲモニー下での戦後改革とが実は相互補完的に支え合っているということである」という情けない評論言葉。 あんた社会学者でしょう、って。 何が相互補完さ。 そりゃ相互補完的だろうけどね、どこがどうやったから相互補完になるのか書かなきゃ、他の人間が何度でも何度でも繰り返すことになるでしょ、って。 別に丸山にだって悪気はないんだから、気をつけないと自分の話もそうなるよ、ってことです。 丸山なんかの話に何百ページも使わないで、なんで「支配的なイデオロギーは支配階級のイデオロギーになるのか」を明らかにしなさいよ。 まあ悪い人じゃなさそうなんでそれ以上言いませんが、大学教授ってだから不満さ。生活するためには自分の仲間共同体の中の人間(学者)についてしゃべって、なんぼだからね。 で、問題は、そうした思想ないし評論的学術論文?が、本人の意図を越えて?、社会の変動に影響していく、ということです。なので私(たち)もこの思想というやつにしばらく付き合っていく必要があるのです。 ただ、今月はその前段。「本当の思想」っていうのはどういうものかっていう、まあ例示かなあ。夏だし。 本当じゃない思想、でもそっちの方が現実には問題の思想、っていうのは、本屋の政治・ビジネス分類棚に何百冊もある本たちのことですが。 「本当の思想」は、真偽とも趣味ともタテマエ上は関わりなく、人間が生きていくことそのものに関わる知識のことです。人間が生きていくこととは、食べることではありません。人間は食べずに死ぬことを選ぶことができます。思想とは人間が死ぬことそのものに関わる知識といってもいいでしょう。 といっても、知識は実は空中に浮かんでおりまして、あるいは本に付いたシミのようなものでして、人間にとって思想は、そんなただの知識を自分の行為に取り入れたところに現実のものとなるわけです。 こういうと当たり前みたいでしょう? ところが、思想は「本のシミを通して」伝わりますから、現実問題としては全然当たり前ではない。シミそのものが自分にとっても現実であるかのように自分に記憶されるのが、普通そこここにみられる姿なのです。 たとえば本当の思想とは、次の対談にみられる吉本隆明の発言のようなことです。 1.吉本隆明 鶴見俊輔対談集「思想とは何だろうか」晶文社、1996。(対談時点は1967年) p153 「鶴見 どういう状況の分析でも、関係の概念はかならずあいまいになってきます。安保の強行採決の問題でもそうです。そのあいまいさを完全に排除して、それがまるごと自分たちに関係する問題だとして理解できない面はどうしても残ります。」 「吉本 いや、ぽくはそうは思わないですね。あいまいさは残らないのだということが一つの原理として組み込まれていなければ、それは思想じゃない。ぽくに対するいろいろな批判はことごとく、(吉本が主張する過激な意見には)どこにも現実的な基盤がないじゃないかということです。しかし、ぽくは思想というものは、極端に言えば、原理的にあいまいな部分が残らないように世界を包括していれば、潜在的には世界の現実的基盤をちゃんと獲得しているのだというふうに思うんですよ。思想というものは本来そういうものだ、そういうことがなければそれは思想といえないのだと思います。」 鶴見俊輔という自由主義的な思想家が、吉本隆明に、もう少し現実を見なさい、と諭す言葉に応えた部分です。 つまり、現実を見ろという言葉では実は何もできないんだ。人は自分で思うように動くわけではない。まず自分が動けること、それが重要なのだ。自分に動けない点があれば他人も動けない。自分を解放しようとする吉本は自分が戦争時には愛国青年であったことを深く認識し、それを引き受けつつそんな自分がどこから来たか、そんな大衆はどこへいくのか、を納得しなければ何ができよう、と思い至ったわけです。 たとえば、理論上、選挙で選ばれた代議士は国家を正しく動かすでしょう。それなら正しい代議士を選挙で選ぼう、と。 しかし、それではならない。そんな大衆の存在形態では以前の私(吉本)のように戦争になれば国家に押しつぶされるだけだ。じゃあどうする。私はこうしたい、だからこうする。これを突き詰める。それが愛国青年であった私の取らなければならない道だ。 ということです。 それが、自分の行為となった「思想」であり、人間はそういうただずまいからしか本当の思想は学べないのです。 吉本の考えた内容というのは実は他人にとってみればたいしたものではない。特に戦後生まれの者たちには、(「言語にとって美とは何か」という書物を除いて)そう引き継いでいくものがあるわけではない。しかし、吉本の存在というのは、思想がインテリの高踏的遊び事や政治行動の錦の御旗からようやく一般大衆のものとなった、その初めの一歩なのです。 もう一つ載せておきましょう。 吉本隆明「擬制の終焉」『民主主義の神話』所収、谷川雁他著、現代思潮社、1963。 P49 「もちろん、花田などがかんがえているコミンターン式のインターナショナリズムと、それにともなう一国革命――ソヴィエト革命・中国革命の評価は、ソヴィエト一国社会主義擁護論の所産と思考法であり、本来的にはナショナリズムの変態にほかならない。ここにナショナリズムとインターナショナリズムについての日共的な理解を、まったく転倒すべき契機が存している。わたしたちが、インターナショナリズムというばあい、ソヴィエトや中国の一国革命の影響などによつて、時代を区分することではありえない。国家権力によって疎外された人民による国家権力の排滅と、それによる権力の人民への移行――そして国家の死滅の方向に指向されるものをさして、インターナショナリズムと呼ぶのである。一国社会主義指導部の成立を世界史の指標とするのではなく、それぞれの国家権力のもとでの個々の人民主体への権力の移行の方向をさしてインターナショナリズムというほかには、幻想のなかにしか、インターナショナリズムは設定できない。」 これはちょっと事情通でないとわかりづらいかもしれません。 花田というのは花田清輝という昔の評論家でどうでもいいんですが、ポイントはそこではなくて、 「インターナショナリズム」=国際的な協調を重んずる政治的な考え方による社会システムの状態は、学者や評論家の頭で考えるものではない。われわれ個々の人間が行動していく中で、作り出されるしかないものなのだ。 あるいはそれは作り出されないかもしれないけれども、その作り出し得ないことは何もしない評論家ではなく、われわれ個々の人間の問題なのだ。 という喝破です。 それまで、そしてそれからも、吉本の影響を受けたブント・社青同(という左翼の派閥)の一部以外にこのことが言えた人間は他にはどこにもいませんでした。今でさえそうです。 試しに今の「市民主義的」な人の政治(社会)的な発言を注意してみてください。そこにはこう書いてあるはずです。 「○○というのはこういうことだ。そしてそれを実現するのはわれわれ(市民)しかいない」 そうじゃない、先験的な=頭で人が考え出した「○○」というのは存在しない。本当の「○○」はわれわれが作り出す未来にしかないんだ。 それが吉本隆明の思想です。ただの「考え」ではなく、彼が生きたことの内省による彼の生き方です。 ただ注意しておかなければならないのは、ここで「先験的な○○」と呼ぶのは、現在や未来の社会の状態のことだ、ということです。そこには前提・限定がある。 たしかに未来の状態など誰にも分からない。あるいは理想の状態など誰にも分からない。分かる必要もない。しかし、そこに行く意思は存在し続ける。そしてその意思が存在する限り、そこに至る過程、そこにいくべき過程を生きる人間には、悪く言えば先験的な、いわせてもらえば科学的な道筋と倫理的な道筋が存在する、ということです。 未来の状態は分からない。しかし、その未来の入り口へ行く入り乱れた線路はある。どれに乗っても一緒だがそうしたいくつかの同じ方向へ向かう線路はある。そしてそれ以外の線路は、そこへはゆかない。 そして、そこへ向かう人々もいる。そして、それ以外の人々はそこへはゆけない。 この2点が吉本やその支持者が分からない、分かろうとしなかったことです。 誰でも自由のために行為する。そして彼のとるべき道は、彼が意思し、そして彼の隣人の存在も認める、というこの2点の前提のおいて存在するのです。 それにしても、なぜ吉本だけが正しいか、ということになります。 もともと理論なんて間違ったものが多い、あるいは百歩ゆずって理論家本人の趣味で作っていると書いてきました。(まあ、まとまって書いてはいませんが、まとめるのは次の本で、と思ってるので)。 で、理論の間違いはいろいろあるけれども作った当事者は別として、理論はそれを聞いた者が伝えなければなりません。その伝える者がなぜ間違えたまま伝えるか、ということです。 それは、理論の伝達や吹聴は吹聴者の賞賛と優越に規定されるからです。 吹聴者が世俗的であればあるだけ理論は間違ったまま、あるいは増幅されて伝達されます。 伝達する用途に合うように特徴づけられて短縮使用されるからです。 吉本は、敗戦による自分の価値意識の敗北を深く心に留め、自分を愛国少年にした一切の世俗から自分を切ることができた、その差異です。 ま、そういうことで。 次に挙げるのは、それに対して、本のシミとしての思想です。 本来的なのだけれども、今の平和な時代の我々から見れば当たり前なのだけれども、でも、それでは何もできない、という見本です。 鶴見俊輔は先ほどの吉本の対談相手で、そこにもそんな発想が垣間見られますが、それでは、戦争に巻き込まれていった良心的な感傷主義者たちと何も変わらないと吉本は思っていると、吉本自身は相手に失礼なので口にはだしていませんが、私などは推測します。 2.鶴見俊輔 同書p256〜257(野坂昭如と1971年の対談) 「鶴見 わたしが育った時期は軍国主義に入るところだから、国家が人間の本質規定をやるべきだということになっていた。世界はこうなんだ、日本の国家と国民はこうなんだ、小学生はこうなんだと、教育で全部決まっている。それではとても生きる席がないという感じが子どものときからずっとあって、それは自分のいまにもつながっていると思う。 ……つまり、権力によって本質規定されたくない。生きる席を残しておいてもらいたいということなんだ。もし、向こうに本質規定をやってもらうとどうなるかというと、戦後は、国家のかたちが変わったように見えても、戦前のように軍隊が中心でなくて、会杜が中心になるわげでしょう。機動隊も自衛隊も会杜だよね。そうなると、サラリーマソの本分というふうになってくるから、それが本質になるわけだ。勤務のときは、いつでも出動しなければならないし、日曜も出張しなければならない。機動隊員は成田空港に出ていって、学生の相手をしなければならない。それが、人間の本質としてとうぜんのことだという考えかたになってくるわけです。 そうすると、戦前の国家と戦後の国家はひじょうに違ったように見えていても、戦前の国家にたいへん似てくる。だから、国民大衆は、たとえば警察官が殺されると、ババはかわいそうだというわけで、学生は殺人鬼になって完全に孤立させられてしまう。わたしは、学生が警察官を殺したのはよくないと思います。けれども、機動隊員も選ぶことはできると思う。だいたい、機動隊員になるということは一つの選択なんで、ならないことはできるし、辞職することもできる。ところが、なった以上は給料をもらっているんだからしなければならないということになれぱ、結局、南京虐殺にまでいっちゃうし、ユダヤ人虐殺にまでいっちゃう。アイヒマンの論理と同じだと思う。 機動隊員になっても、学生をなぐることはとてもやりきれないから辞職するとか、あるいは成田で学生をどうしても敵にまわさねばならないから、きょうだけはサボるとかできるはずだ。 そういうことが広がっていけば、全体も変わると思う。」 長いけれども、ここで問題は最後の1行です。 「そういうことが広がっていけば、全体も変わると思う。」 実は今回のイラク戦争の時も鶴見氏はそういっていました。でもそうじゃない。なにがそうじゃないか。そういうことは広がらないのだ。 そういうことは広がらない、逆にそうでないことが広がる。 それが思想でなければ「ああ間違っちゃった」ですむ。オレお人好しだったね。 しかし、思想というものはそうじゃない。 良心的な鶴見氏には悪いけれど、それは思想家じゃない。あるいは評論的思想家かもしれないけれども思想者ではない。 もう1971年から30年もすぎた。前より悪くなった世界の中で、今更それはない。思想というのは掛け値なしに自分の生き方の問題なのだ。間違ったまま30年など絶対にあり得ない。それじゃあ、今まで何のために生きてきたのだ。思想者というのは自分の思想を抱え込んでこそ思想者なのだ。それが現実化することが基礎づけられてこそ思想なのだ。すでにここで、当初から吉本隆明が正しかったことが暴露されている。鶴見氏の思想とは、ただの「ものの考え方」にすぎない。思想というのはどうやって人は死ぬか、という問題なのだ。 実際、人が、特に若い人が、人間の生き方について思い悩んだときに、普遍的にマナ板に載せられるべきなのが鶴見の思想的考え方です。そこには人間が時代を越えて社会生活を送る上で重要な「人間への寛容」だとか「平等の希求」あるいは「権力の忌避」だとかが説かれています。それはそれで正しい。人間が社会的に生活する限り普遍的に正しい考え方です。 しかし問題はそうじゃない。 そんな正しい考えを持っていても、戦前の良識派は戦争になってしまったら負け犬のようにこそこそ生きなければならなかった、そこが問題なのです。鶴見本人はアメリカにいたから僕は知らないといえるかもしれない。しかし、鶴見だって日本にいたら同じことだよ、と吉本が面と向かって明言しているのに、それを感受できないところが全然思想者ではない、ただのお坊ちゃんインテリだ、と断定する理由です。 3.田川建三 最後に登場いただいて光栄ですが、他者のことも考えるので、(吉本と違って)言ってる内容まで正しい思想者を。 田川建三「イエスという男」三一書房、1980。 p29 「だから、イエスの言葉が発せられた個々の場面を厳密にとらえ返すのは不可能であるにせよ、その言葉の発せられた全体的な状況は知ることができる。そしてそれを知ることができるとすれば、実際には個々の場面についても、それが皮肉になっているのか、憤りを爆発させたものか、憤りを裏にひめたものか、といったことはかなりな程度まで想像できるものである。言葉は、このように状況に向って発せられる時には、明らかに、一つの行動なのである。そしてイエスの言葉を行動の一こまとしてとらえる者は、さらに、イエスの活動全体をも、その歴史的状況に立ち向ったものとして理解することができるだろう。そうしてはじめて、イエスは何故殺されたかが理解できる。イエスは、権カによって逮捕され、殺された反逆者だったのだ。権力の側に言わせれば、どうしてもつかまえて殺しておかねばならないような男だったのだ。その生と活動は、にこやかに説教しつつ語れるようなものではない。 だから我々は、イエスについての個々の伝承を歴史的な場の中へともどしながらとらえていく。魚を水にもどすように。それは歴史的想像力の問題である。そして、はっきり言っておくが、歴史的想像カは、決して、歴史家の勝手な主観の持ちこみというようなものではない。それはもはや、主観・客観という軸からではふれることのできない課題、歴史的真実にどのように肉薄できるか、という課題なのである。」 p66。(聖書の例の「迷える羊」に関して) 「実際にはやはり、一匹たりとも白分の飼っている羊が失せれば悲しい思いをするだろう。羊飼にとってこれは九十九対一という算術の間題ではない.九十九匹をいったんはほっておいても、何とか失せた一匹を探し出そうとするだろう。 現実の世の中は算術的合理性で動く。事実、もしも九十九対一を文字通りあれかこれかで選択しなければならない時に、九十九を捨てて一をとる人はいない。けれどもまた、そういう理屈で、実際には必ずしも絶対的にあれかこれかではない揚合にも、九十九のために一が犠牲に供されていく。そしてそういう場合ほぼ常に、九十九の方が強い者達であり、犠牲に供される一人は大勢の中でも何らかの意味で弱い者である。こういう現実に対して、理性の立場に立って反撃を加えるとすれば、実際には九十九人が少しずつ譲歩しあえぱこの一人を滅ぼさずにすむのだから、みなが平等に困難を分かちあいましょう、ということだろう。 けれどもそうおだやかに主張することによって世の中の不公平が除かれることはめったにない。世の中全体が算術的合理性を力をもつて強制して来る時に、それに抗おうと思えぱ、こちらも強引かつ単純にそれを裏返して主張するのでなければ、強い衝撃力を持てない。大切なのは九十九ではなくて一だ。こう主張するとき、もはや人は深く全体を見通す平衡のとれた理性を失っている。暴論ですらある。だがそのように叫び出さねばならない状況はしばしばあるものだ。これまた決して不動の真理ではない逆説的反抗なのである。 此の世で実際にこのようなことを、ある程度以上主張すれば、叩きつぶされざるをえない。実際には九十九の力に一が勝つはずがないからだ。逆説的反抗に立ち上れば、人は悲劇に突入する。しかし歴史を動かしてきたのはさまざまな悲劇だった。 イエスという人がさまざな場面で語り、主張してきた逆説的反抗を「真理」の教訓に仕立て変えてはならない。イエスは「真理」を伝えるために世界に来た使者ではない。そのように反抗せざるを得ないところに生きていたからそのように反抗した、ということなのだ。そして、もう一度言うが、だから殺されたのだ。」 これが思想の立場です。 あえて、間違っていてもよい。なにがよいのか。悪いと知っているからよい。知っているから絶望できる。ここまできたらここよりあとに道はない。 思想には真偽は関係がない、といっているわけではありません。 人間が生きるときに、真偽を表現できないことがあるのだ、といっているのです。 それは真偽を越えたところまで生きた人間にのみいえることです。 いえるというのは、わかるかなあ、宗教家のフリをして宗派のお先棒を担ぐことではありません。宗教家だからうそをついていいなど。大塚久雄のことですが。 そうじゃなくて、宗教家なら、宗教家だからあえて宗教裁判のウソを突く、ということです。 宗教家には宗教家の事情がある。カトリック教徒なら是非ともプロテスタントなど火あぶりにしなければならない。でもそうじゃないんだ、本当は神罰の対象なのはわかっている。でも、自分の死を賭けて今語らなければならないことがある。それが倫理というものだ、ということです。それが本当の個人主義というものです。大塚などにはわからない。 「自分の死を賭けるなんて。そんなの私には関係ない」という普通の生活者の意見もわかります。それはそれでいいんです。 でも、人の生死に関わる発言をする社会科学者にはそんな免罪符はありません。 社会科学者は常に他人の生命に関わっているのです。アジアの飢餓や難民のことではありません。アメリカの飢餓と寒波の下のホームレスの子供たちのことでもありません。日本で1年に何人餓死しているでしょう。何人自殺しているでしょう。何人家庭が壊れて子供は学校の授業からはずれ不良化し、何人会社をクビにされまた家庭が壊れていくでしょう。そんな社会不適合な人間は自業自得だ? なんとでもいえ。 社会科学者の発言は、彼が何を思おうと、これらすべての運命にかかっているのです。自業自得で結構。お前の考え通りにそいつは自殺するさ。めでたいじゃないか。祝杯をあげるか。 もっとも、そういう恥知らずたちではなくて、吉本も「そんなのしらない」というでしょう。それは彼の立場です。彼が生を賭けた自分の死に場所です。それで彼は十全に生きたのです。で、あなたたちは? それがあなたたちの死に場所でないなら、私に悪口を言われたって当然のことです。 じゃあお前はなんだ、ですか? 僕に言わせれば、田川にせよ吉本にせよ、それらはやはり思想の立場だ。思想の立場にすぎない。 私たちは新しい社会科学を持っています。絶望しつつも、言えば何かが変わる本当のことがある、そのことを語ることは何よりも優先する。私の生がどうだというのは余計なお世話だ。私が自業自得の不幸な人間に気を遣うことをなんのかのと理由づけられたくはない。理由なんてどうだっていいんだ。ただ、遊びでやってるかおまんまのためにやってるかしらないが社会科学者と名乗りたければせめて人を殺すんじゃねえぞ。 当たり前? 当たり前じゃないよ、そこのきみ。きみのことだよ。 それが私の死に場所です。それが私の思想です。 もっとも、たかだか人間関係の中では私は死にはしませんが。 【10月分】 《社会の中の社会情報》ーその1 〈情報発信者の立場について〉 さて、もう夏も過ぎ、次回作も書き出していかないといけませんので、このネット上の話題もそろそろ核心に入っていこうと思います。 先月までのように誰それさんがどう嘘をいったというのはほんとは大した問題じゃない。結局、知識人というものは何か大したことを言っているようでも実は何もしていない、わかっていない、それでもしゃべりようで世間は賞賛する、ということが明らかになればここではとりあえずよいのです。 なんていうときちんとお読みになった方に悪いようですが、私も涼しくなってさっきお風呂にゆっくり入り「あれ、貴重な5ヶ月のまとまった時間を無駄にしたか」とぞっとしたところです。なんて。 でもさらに無理に考えて、漠然とアホと思ってった議論がきちんとアホと分かってよかったと自分を納得させました。こういうことはいつかきちんとしとかないと。もうしないけど。 さて、じゃあ、その世間が賞賛するしゃべりようとはどのようなものなのか? が問題となります。 それにはいろいろな側面があるのですが、今月は,表現をする人たちのどんな努力の末でもできあがった表現の要素について考えてみます。 他には、表現をする人の主体的な努力の過程やそれを受け取る側の事情なんかがあるんで、順次見ていきます。それが終わると、ある「表現が持つ思想」というものが分かり、思想と倫理「その2」が提示される予定になってます。 商品経済下での評言(よる賞賛・優越の獲得) 1.商品販売の優位 (購買される情報) 資本主義社会では、情報は、多かれ少なかれ、購買過程を通ります。 まずは「多かれ」の出版情報を取り上げます。 わかりやすいところからいきましょう。 賞賛と優越は生理性から生まれますが、表現世界での賞賛と優越はもう一段社会の過程を経て現実となっています。 つまり、端的に言うと、ある人は本屋で売っている本について、 「この本はこんなに売れてるんだ。読んでないと他人からなんだ知らないのかと言われる。この作者は立派な人にちがいない」と思います。 そんな思いが、個人の段階に生じるわけですが、この裏に、生理的現実、 ・売れないモノは作らない ・作ったらもっと売れるように宣伝する ・売れれば作者である自分にカネが入るから売れるように書こう ・なにしろ出版社も書き手も売れないと死んでしまう ・売れるモノを書いてくれる人は先生様さ、せいぜいおだてて銀座でも六本木でも連れて行くさ 等々の「社会の」事情が存在しているわけです。 私のように「売れない作家」はぜんぜん賞賛されません。「本なんて書いてるから、もしかしてひょっとすると偉いかも」みたいな売れる作家のおこぼれの賞賛が出るくらい。いやべつに不満があるわけではありませんが。 というわけで、資本主義社会における表現に関わる賞賛は、「商品」になるかどうかにかかっています。たとえ莫大な売り上げにつながらなくとも、趣味的にでも「売れるか」、隙間産業的に表現会社(出版社)と表現者が生きていけるか、というところにかかっています。 (なお、賞賛は商品販売にフィットしてるんで商品生産にフィットしているわけではありません。書き手でも売り手でもカネのために生産するんで、賞賛のためと思うと苦痛がたくさんあるものです。売れたあとの賞賛が、まあ、生産者にとってはほんとの賞賛なのです。どっちでもいいでしょうが) ところで、ナイーブな人は疑問を持つかもしれません。 「でもそれは、面白いモノを書く、ってことじゃないの? 商品生産じゃなくたって、面白いモノを書けば賞賛されるんじゃないの?」 そりゃそうですね。べつにそうじゃないとはいいません。面白いものを書けば隣の人に賞賛されるでしょう。 でも、商品にならない限り社会に顔を出すことはありません。 そして商品になるのは「面白いモノ」ではなくて、「面白くて売れるモノ」なのです。 面白いモノを書いた潜在的な大作家は、その草稿を友人に見せただけで失意のうちに死に、あとでそれを発見した出版関係者が売りに掛けて、やっと死後賞賛を浴びるのです。 ついでながら、そういうナイーブな考えは社会を考えるときには間違いの元で、人間のことはナイーブに考えると全然資本主義とは関係なくなってしまいます。 「なんで経営者が権力があるっていうのかしら、べつにあたし性的関係を強要されたことなんてないし、無理言われたら辞めてやるんだ」 「なんだい、男一匹クビになったって生きていけるさ。」 まあ、その他もろもろ。 そうですか。じゃ、さよなら。 物事は自分の身にならなければ分かりません。 そして、世の中には幸せな人もいますしおめでたい人もいます。まだ20代のすねかじりもいます。ただ問題は、そうでない人が圧倒的多数だ、ということですが。 (補注) ところで、資本主義社会における情報は、すべて「売れなければ」動かないわけではありません。いつか購買過程も経ながらも、売買価値が「後から付いてくる」情報が存在します。 行為主体の次の一瞬の行為により近い情報です。 たとえば、地震速報。台風情報。そして暴動情報などです。 運動のアピールに関する情報は、各種出版メディアの購買物となりながらも、商品価値を問わずに入手要求を持つ側面が大きなモノです。「多かれ少なかれ」同じではありますが、視点によっては扱いを違わせた方がよいこともありますので気をつけてください。たとえば、関東大震災のときの朝鮮人暴動の大デマの存在は、「売れるから」だ、と考えるのは間違いです。 2 情報の出現がもたらす影響 というわけで、売れる情報が社会に現れ、これを人が買います。 このときの影響はまず、こうした表現が事実として存在することによって、行為者の「規制」認識が変化するということです。 そして問題は、それが事実認識として、どれだけ各種の制度の変更につながっていくか、つながっていってしまうか、ということです。なんですが、これはまだ他の要素を考えてからの事で、今回は「その1」で、すこし外堀を埋めていきます。 なお、「面白くて売れる」情報の社会への浸透には、さらにもう一つ、「賞賛する」ことによる賞賛、という賞賛の獲得の仕方が噛んでいます。 人は、ある表現が社会に賞賛されると言うことが判明したときに、これを賞賛することで自分への賞賛・優越を手に入れることができます。 「こんなこと知ってんだぜ、すごいだろ」みたいなもんです。 これは、重要な社会過程で、多くの評論家・批評家の存在意義はそこにあります。 ****** 出版情報の性格の変化の要素はいくつかあげられます。 それも、取り上げ方でいくつも挙げられるわけですが、人の行為の自由について同じ機能を持つものを「変化」と呼んでもあまり意味はありません。たとえば、その昔はスポーツの話題は野球だったが、一時サッカーの話題が多くなり、今はタイガースでもちきりだ。なぜか、等。 趣味がマンガでも小説でも個人の自由については同じことで、私(たち)の探求の意義は、世界に住む行為者すべての個々人としての自由の確保であるわけで、その視点から話は進みます。、 とりわけ、人間は行為の将来に関わらないものはどうでもいい。ところで、行為の将来に関わる行為の領域はこれへの対応メディアを持っている。ある時代、ある場合にはただの近隣の井戸端会議がそう機能するかもしれませんが、資本主義をも貫徹している生理性をめぐる行為領域に関わるメディアは、生産関係の大規模化に伴い、事実報道を司る新聞その他これに類する「報道」メディアをもたらしました。 なお、資本主義は、人間の行為について、生理性に関わらない行為領域と、この領域に関わる(広告という)メディアもたらしましたが、こメディアがその他の行為領域に関わることはありません。 (1) 出版総体としての必要な知識の変化 今の時代に、何が必要とされているか、についての変化が出版物を変えたり、出版量を変えます。 といっても、その内容は、 ・ 技術の変化に伴う知識 ・ 各種の利害集団(・利害の集合性)が欲しがる自分たちの正当性といったイデオロギー的知識 によるものなので、それによって制度の変更に向かうわけではありません。 社会的にコンスタントに必要とされているのであまり問題ではないのです。 (2) 媒体としての要求される知識の変化 表現される一般的な内容以外に、その媒体に要求されるべき内容が変化し、その結果、出版情報の性格が変化することがあります。 70年くらいまでは、高校生雑誌というものがありました。60年代で大学を受験する生徒は広く、「螢雪時代」なる雑誌を読んだものです。 あるいは、私などは覚えていませんが、月刊雑誌には各学年用のものが小学生から高校生まであったはずです。「小学館の小学3年生」の高学年版です。 これらは、少なくとも高学年には、今はもう形骸しかないですよねえ。 この例は、子供の生活姿勢の変化のようなもので、必ずしも大人の行為者の自由に関連は少なそうですが、問題が新聞その他の社会の規範づくりに今でも機能している媒体の変化ですと影響が大きくなります。 新聞その他の商業メディアは、これを購買する消費者の姿によって変化します。モノが売れるのは、まずは、買う人の条件によります。 当初、政治主義的な人たちの賞賛的知識の場であったそれは、政治主義者が国家を意識するようになり、国家政策を云々するようになりますと、それに歩調を合わせて、というか、現実にはもちつもたれつでデマ新聞化していきました。新聞は日清戦争や日露戦争で部数を拡大していきますが、要はその過程で、人民の国家意識ともちつもたれつの関係をとっていくわけです。 しかし、戦後、復興期からの一時期を除いて、政治主義者の凋落とともに新聞部数が相対的に凋落していくようになります。要は政治主義への賞賛が消えてしまったのです。 これは、新聞が反映していた武力性が消えてしまった、といってもかまいません。 ちなみに当初から読者に政治主義者を期待していない俗物週刊誌、マンガ週刊誌にはこうした変化は見られないのは当たり前です。 (3) 気晴らし=規制からの観念的解放 気晴らしなんて「趣味」にしかすぎないとお感じの方もいらっしゃるかもしれませんが、これはその社会が「何を解放する事が許されているか」ということに直接からむ問題です。 人は自分の行為の成就をもってはじめて満足します。したがって自分の行為をじゃまする規制は、なんであれ、まずは反感を持ちます。 逆に自分を羽ばたかせてくれる表現は、そこに入れる限りは入りたいものです。 小説を読み慣れた人間には小説はそうしたものですし、エロ・グロ・ナンセンスは、自分を最大限に自由にしてくれますので、社会的規制にストレスを持てば持つほどこの表現物を入手します。 この入手により、権力の圧力もなく表現会社が儲かれば儲かるほど表現会社による表現への規制は弱まり、その事実がしだいしだいに社会の規制を排除していくことになります。 まあたとえば安週刊誌のエログロナンセンスみたいなものの出現、ということになりますが、そのこと自体「思想的な」問題=規範的な問題であるには違いありません。 現代について言えば、こうした規範性を、人々は賞賛的(特にガキにおいて)、事実的に認知します。これは特に「少年少女」(〜18歳)に見られるようになるでしょう。 国家権力。商品権力の動向は、その、読者に合わせて、弱化を週刊誌に見、その進行方向を新聞等に見ることになります。 まあ元に戻って、個人の行為の自由は、彼がその他の社会構成員に頭を使う必要がなければないだけ、規制の解除を指向します。 規制の解除への指向に対抗するのは、彼の生理性と賞賛・優越しかありません。 たとえば、おめでたい大臣は現在はこのように主張します。 (朝日新聞3年8月31日付け朝刊) 「鴻池特区担当相は『教育は(学校経営に参入する)株式会社や都道府県、市町村が自由にやる。学校の先生は市長が気に入ったのを連れてくればいい。教育委員会なんか必要じゃない』と述べ、教育委員会不要論を展開した」。さらに 『教育委員会の存在を検証する必要がある。教育を行政から独立させることが必要な時期もあったが、教育もスピードが必要になっており、行政が速やかに教育に対応できることが必要だ』 と述べた」そうです。 私のようなスターリン主義者には大変同感でして、早く政権を執って、速攻、教育を牛耳って鴻池のようなバカな反革命が出てこないように教員は党員で固めたいと思います。 まあこれは鴻池のおめでたさ加減を知らせるための、半分くらいは冗談話ですが。教育にスピードなんか必要ないしね。、 (4) 権力的規制による表現 (権力による、別個の規制の解放、優越) まず国家権力は、法や法の解釈に基づく武力行使によって出版物の内容に介入します。 ・ 事実の歪曲 ・ 事実に対する評価の押しつけ ・ 外部(民間)権力への武力的支持による上記2種の強化 (要は資本主義社会であれば右翼暴力団の応援です。もちろん計画経済国家でもあることですが) こうした介入は、賞賛や優越の経路に組み込まれ、表現者・表現会社の方針へと変化します。 とりわけ、書籍出版社よりも権力に規制されても存在しうる発言業種にそれが歴然とあらわれます。 新聞・週刊誌のことです。 元々「国家的利害」が存在してはじめて国家なのですから、個人から見ればどんな理不尽なことであろうと、国家から見ればすべて意義あることなのです。 だいたい自民党なり民主党なりの政治家まで過去の戦争の反省がどうとかいってますが、個人を国家の名で制限しようとする考えを持つ者が戦争を批判するなど論理矛盾なのです。彼らには戦争賛美の立場しか残されていないのです。銃後で誰がどんな目に遭おうと全部必要悪なのです。 新聞というのは買われてなんぼの商売ですから、そのときに読者となっている社会階層に迎合するのは当たり前ですが、ある程度の選択幅というものがあります。いつの時代にも起こる例では、面白いことは書くけど、中には外部からの圧力のため書かないこともあるということです。それで平常時には国営放送が、戦時下には民間(アングラ)放送が、われわれ生きる人間としての個人にとってはかなり大きな意味があるわけですが。 たとえば、この前の戦争時には、新聞は一切軍部を批判するようなことは書けなかった。 まず右翼どもが不買運動を起こし新聞社を襲い、これを運動として、法律が後追いした。そして法律を警察や憲兵が補完した。 それで困ったのは生きる個人として良心的であった個人だけで、だからといって、新聞社は何も困りはしなかった。 ちょっと太平洋戦争時の朝日新聞社の大見出しを挙げておきましょう。 (41年12月9日朝刊) 【米海軍に致命的大鉄槌】 という大喜びの開戦の大見出しを経て、どうみても昔見た過激派の機関誌さながらの大言壮語を飛び交わせ、はじめの半年を過ぎればもう負けを勝ちと言い続け1年、 (43年5月31日) 【アッツ島に皇軍の神髄を発揮】 「山崎部隊長ら全将兵壮絶・夜襲を敢行玉砕 敵二萬・損害六千下らず 敵胆奪ふ大和魂」 有名な玉砕のはしりです。以後はもう負けを勝ちというすべさえなくなり、負け戦をどう美しくいい飾るかのみ、 (45年6月26日) 【廿日 敵主力に対し全員最後の攻勢】 「殺傷八万、撃沈破六百隻 皇軍の真髄発揮 米、戦史類なき出血に呻く」 沖縄決戦です。 安田将三、石橋孝太郎「読んでびっくり朝日新聞の太平洋戦争記事」リヨン社、1994。より。 この間新聞記者たちが何を思ってきたか。 (表づら) 「国民に正しい認識を与えることが真の戦力である。」 (44年11月10日朝刊) ▼かかる場合の情報行政の根基をなすものは、内外事態の正しい認識である。ある特定の事実を掩うて、国民の視野に盲点を造ることは、出来るだけ避くべきである▼むろん、それには、国民が好ましからぬ事実に直面しても、毫も動じない不抜の精神を養うことが必要だ。しかも、その不抜の精神たるや、人々がつねに、事実の正確なる認識を持つことによって、一層強く確保され得るのである▼要するに、国際政局に関する国民の知識水準は一段引上げらるべきだ。しかも、それこそ真の戦力の根源ではなかろうか▼ (腹の中) 終戦の日:「まあ、これからは一転してアメリカを誉めるわけだがそれもしょうがあるまい」 (45年8月15日朝日新聞編集局長細川隆元)(自著より) 「その日の午後、社長村山長挙出席のもとに編集局部長会議が開かれた。私はこう述べた。「仕事は平常どおりやっていこう。何も動揺することはない。今まで一億一心とか、一億団結とか、玉砕とか醜敵撃滅とかいう最大級の言葉を使って文章を書き綴って、読者に訴えて来たのに、今後はガラリと態度を変えなければならない。これはしかたのないことだが、それだからといって、昨日の醜敵が今日の救世主に変ったような、歯の浮くような表現もとられまい。まあだんだんに変えていくことにしようじゃないか。マックアサーが乗り込んで来ても、新聞に関するかぎり、日本が占領地でやったよ うなバカげたことはやらぬと僕は思う」 なにも悪びれるところもないのはエラい。 面の皮が馬の尻ぐらいあるのでしょう。 このスキャンした本にはもっとハレンチなことが暴露されておりましたが、この細川という男はさきごろまで「時事放談」なる日曜番組でまだいいたいことを言っておりました。 それはそれ、彼らとしては「嘘をついたのは大本営だ。我々は嘘をいったのではなく、国民を鼓舞激励したまでだ」ということだと思います。 (この件については、その後、大変適切な書物がみつかりました。 岩川隆「ぼくが新聞を信用できないわけ」潮出版社、1996。 先に引用した「読んでびっくり……」には、その後、占領下で豹変した新聞の記事がなかったりで、それだけではよくわからないところが多いのですが、この本はすべてそろって「新聞」世界の実情がそのままよくわかります。最近めったに見ない欠点のない良書。 どうせそのうち消えてしまう本でしょうが、なんとか資料的に残って欲しいものです。) 3.その他の表現媒体 こうした事実を伝えるための媒体に対し、その他の表現媒体として、いわゆる芸術の諸媒体が考えられます。絵画、音楽、劇、その他のものです。 芸術は、基本的にその媒体を使って人の情動を動かせれば、そこで「絵画芸術」なり「音楽芸術」なりと認められるものです。それらも「売れなければならない」モノではありますが、そこでの「売らすための諸変化は、表現形式の変化とまとめられます。 大衆が購入するようになった諸芸術は、たとえば宮廷での制作時間も作業人数も多大な大油絵画から(もっと前の時代もありますが)、1日で描ける印象派絵画へ(1枚半年かかったっていいのですが、安いからトータルで1年数十枚は書かないと)。筆の使い方も服飾のような流行に合わせて、キュービズムやら抽象がやら。 表現を受け取る行為者にとって、芸術の意味は中身です。こうした形式の変化は、行為者の次の行為へは関連しません。 それでも、絵画や演劇には題材がありますから、その題材への「規範的な」意味づけはでてきます。これは上記(3)が当てはまる雑誌と同様な事態となります。 ここでの(注)は、芸術の受け取り方には「自分でやろう」という受け取り方がある、ということでしょうか。大衆の労働時間の減少は、芸術への従事時間を増加させます。だからといって表現される内容に変化があるわけではありませんが、視点によって影響のある要素です。人間が生きていく上でつまらない仕事が資本主義で必然であれば、たとえば昔のフォークソングブームや今で言うと駅頭での音楽発表会などは、世界をトータルで見る場合には重要なことです。 4 社会への情報の発信 (シンプルな形態) 情報の発信者は、自然発生的な姿では、その時代で誰がなってもいいわけです。 人は、自分の社会階層を代表してしゃべるだけでいい。 とくに資本主義陣営には論者が掃いて捨てるほどいます。 第1に、資本主義社会は、その発展段階で、経済的に望まれる階層構成が異なっていますが資本主義の構成それ自体には違いがあるわけではないこと。 第2に、権力社会にあっては、その発言するイデオロギー内容は類型化されていること。 この2点のために、資本主義者の発言は通俗を越えてマンネリ化しています。 なんて左翼陣営も人のことをいえた義理じゃありませんが。 たとえば、昨今のグローバリズムという、大衆資本主義からの脱却のあがきは、戦後50年、ようやく競争主義者が陽の目を見られるようになった時代です。 戦後の資本主義経済成長は大衆への給料「上乗せ」によって、初めて現実化できたわけですが、そこで競争がどうのといっていたらこの大衆消費社会の進展がなかったことは、まともな「自由主義」経済評論家なら誰でもしぶしぶ認めざるを得ないことです。 その間、ずっと日陰で「競争、競争」「民主日本の悪しき平等」「平等というなの不平等」と呟き続けてきた人々がいました。 今、ようやくその体制が崩れてバカにもしゃべる機械が与えられたわけだが、今こそオレのしゃべるときと思い思いのカエルの合唱が始まっているわけです。 たとえばの例では、もう50年も同じ事を言っているはずの人間を挙げておきましょう。 もっとも私も若いのでそんな昔の「少壮学者?」のことは知らないのですが、私が高校生の頃はもう言ってましたから。 加藤寛「気概ある日本人 無気力な日本人」PHP研究所、1999。序章。 もっとも、こういう政治力だけの「学者」の引用をしても意味はないので、たとえば、の指摘だけにとどめます。 (4の補足) 世の中には人の発言を人の性格に当てはめて云々する人がいます。 たとえば、竹内洋という京都大学教授がいまして、その著書には、前回出た「吉本隆明が学問の権威者をやっつけたり大学紛争に肩入れするのは吉本が東京工業大学を出たのに大学教授になれなかったからだとしか考えられない」という旨が書いてあります。 竹内洋「教養主義の没落」中央公論新社、2003。 (くだらなくて図書館で見ただけで返してしまったので何ページか覚えてません。始めから2/3くらいのところじゃないかな) バカか。というよりは、バカだ。という断定ですね。 たしか故丸山真男東大教授なんかも30年以上前に吉本のことをそうケナしてました。バカだ。自分の人格の低劣さを暴露してるだけなのに。信じられませんが京大教授や東大教授って能なしのくせに自分のこと偉いと思ってんですねえ。バカだ。 なんていうと私も吉本の同類にされてしまいますね。「今は」なんでこんなバカが京大や東大にいてオレはいないんだ、と思いもしますから。ただね、自分が京大にいたいわけでもないし、竹内や丸山が番町幼稚園教諭だってやっぱりバカだ、と思います。まあ偉ぶってると思われてもイヤだから、バカだ、と明言はしないかもしれませんが。 こんなふうに情報の発信者には心理学的な評言もありうるところです。 こういうのがナイーブな発想というわけですが。 こうした評言はすべて間違っています。なぜなら、人は「状況の中で」発言するからです。「どんな人でも」といって悪ければほとんどの人は。 ある性格の人間は、ある場面でその性格通りに発言する必要はありません。短気な人だからといって平社員が部長の前で怒鳴り散らすわけではありません。それは短気な社長にはできても平社員にできることではありません。 または、ある考えを持つ人間がその考え通りに発言する必要もありません。共産主義者だからといって、面接試験でそう主張する必要はありません。 あるいは、あるメディアは、ある自分に都合の悪いことを発言すると思われる人間に発言場所を提供する必要はありません。 ある読者が、ある本の中で著者のある表明を目にするためには、表現者の元々の思いの外に、第1に、その表現者の発言理由と、第2に、そのメディアの発表理由の2つが、「ふるい」となっているのです。 竹内の真似をすれば、先ほどの加藤寛については下記のようにいうこともできます。 「こうした右翼発言者の志向は、本人にとってはいろいろな事情があろうが、社会的枠組みの中では、一部の「同情」感性の劣る人間の中で、同情の自己同一性も優越的自由を入手できない部分の人々によってなされる、と考えられる。 すなわち人は社会にあって、優越と賞賛を手に入れる必要があるが、社会の賞賛が、「自分だけよければいい人間」に集まらない戦後社会にあっては、同情的感性に満足を見いだせない生得的性格の人間にあっては、いちいち自分の行動が非難にさらされているという被害妄想的感覚にとらわれる。 「いいじゃないか、自分が偉きゃ」と言いたい人間のうち、若いときに「同情」を見いだすべき「自分」に出会わなかった者たち、たとえば(加藤のように昔の慶応大学で育ったような)坊ちゃん育ちの人間は、真理よりも「自由競争」という自分の性格の解放的思想に固執するようになる。まあ若いうちに偉くなって被害妄想を払拭できれば改善されるが」 実はほんとにそう思ってるんですけどね。だけどそれが真実とは限らない。人生なんていろいろなんです。だけど、どんな違った人生を過ごしていても、世の中で賞賛を手に入れようとすると、ある時代には選択肢はいくつもあるわけではないのです。 5.情報の発信源への社会の反応 〈武力的傾向性〉 シンプルな社会情報への対応は、もちろん「読んで面白がる」です。 そして、個人の行為上で面白い=個人にとって新しい賞賛や優越、あるいは事実認識を手に入れた読者は自分の行為へそれを取り入れるようになります。 ここまでは書くまでもないことで。 しかし、社会の権力保持者はそれを手をこまねいて見ているわけではありません。 権力の運動転換は、その対抗するイデオローグの消滅を意図します。 これはほっておけば生産関係がつぶしていくことになりましょうが、権力はそんな時間の流れにまかせるよりもこれを自分の手で即時に実現しようとする傾向があります。 そしてこれは、良心的なイデオローグ本人の消滅とともに「それが生ずる」という現実的認知として、イデオローグの賞賛の範囲にあるプチ・イデオローグの消滅につながります。 たとえば、戦前の自由主義教師のパージ、あるいは戦後の右翼戦争協力者の公職追放などです。 これは武力的傾向性であり、イデオローグの消滅効果は大きいものがあります。 先の戦前戦中の新聞の例ですと、まだ少しはいた良心的な記者たちに対して、反抗した記者はクビにしてしまうったり、戦争中は二等兵にして戦地へ送ってしまうなんてこともしていました。 でも、ここで重要なこと、みなさんに認識してもらいたいことは、そんなイデオローグをめぐる思想面での闘争の重要さではありません。 それはこの権力方針が出される過程が存在するというそのこと自体であり、その武力行使がなされる基盤が存在するんだという認識です。 イデオロギーが重要であると考えるたとえばレーニン主義者やボランタリストは、タイムマシンに乗って昭和15年の日本の軍国主義時代に行き、そんな権力行使ができないように主張してください。 タイムマシンはできても(できませんが)そんなことできやしない。 そうではなくてイデオロギーなどには主体的意味がないから、武力なんかに消滅させられるのです。 さらに、社会の2大規定因は、武力性(=権力性、暴力性)と生産関係です。 そうした武力的傾向性(=行為論的主体がたまたま武力を握っているというだけの事態)が存在しなくとも、生産関係上の傾向性によって、権力階梯にある対抗イデオローグは次第に追いやられるのです。 まあ、いずれにせよ、武力性の問題というのは大きいのです。いつも述べるようにそれは国家の一方の起源であると考えてください。(もう一つは生産関係) 武力性を担う暴力団、予備役、警察の存在は大きく、未来世界を考える際には、特に軍隊とその予備役の処遇は軍備の必要論者には特に考えてもらわないと困ります。 というわけで、もちろん、こうした指摘はアピールを発する立場に限った問題です。 実際は、このアピールを受ける者がいる。 新聞は、売れるから軍部の提灯記事を書いた。それではその元である「これを買った大衆たち」とは何か。 これは次回(以降)の問題です。 (どうもペースがゆっくりだなあ。いつ終わるのか、ちょっと心配) 【11月分】 さて、今月は「アピールを受け取る者」の立場に立ちます。 いってみれば、ウソつきがウソをつくのはそいつのせいではない、という認識です。 それはウソつきのせいではなく、そのウソを欲する者もいる、という現実ですね。 人は、情報に対して、別に牢獄に監禁されて無理矢理獄内放送を聞かされているわけではありません。 まあ世間に流れてくるものといえば前回のテーマのように商品化できるものばかりですが、それでも商品として購買するから商品化されるわけです。 で、購買は人間行為ですからやはり行為の原理と原則をクリアしている。今回はその説明です。(行為の原理と原則については、一番最後に説明をつけておきましたのでご覧ください) つまり、情報の動きには3過程があって、 1.情報発信者は、世間の状況と情報の受け手の状況を見て発信します。 2.発信メディアはこれを受けて、発信できるものは発信します。 3.受け手は発信者の状況を見て、これを主体的に受領します。 こんな過程を辿るわけです。 で、2は前回みましたので、今回は3。来月は1ということです。 アピールを受ける者は、まず「アピールを誰が出しているか」と「アピールの内容」とを認識します。 まず、「受け手にとっての情報の提供者」について考えてみましょう。 1.受け手にとっての情報提供者 あなたがお友達と話していて、お友達が伝えた情報があなたにはウソに思えたので「そんなのウソだよ」といいました。するとそのお友達は 「彼がいってるのに、なにいうの」 と怒りました。 ここで、「誰がいったか」が問題になります。 「彼」が「ボーイフレンド」だっとときと「天皇」だったときとはどうも異なります。また「天皇」と戦時中の新聞の「大本営発表」とも違うようです。朝日新聞と東京スポーツでも違うでしょう。 これはボーイフレンドである彼のお友達にとっての社会内の位置によります。 あるいは天皇・新聞のお友達にとっての社会内の位置によります。 <「情報提供者」の社会的位置づけ> 田舎であれば村落の寄り合いの情報が常に(他の都市に持っていけば間違っているかもしれませんがその村では)正しいように、現代日本においては(右左の偏向を考慮に入れた上で)、新聞やTVは社会的位置として本当のことをいうことが常識になっています。それは、田舎での「寄り合い」の情報が、生理性を確保する上で最重要であるのと同様に、サラリーマンであれ商店主であれ、マスコミ情報は信じざるを得ない位置を占めているからです。 こうした議論が、真であるか偽であるかは、私と同じに「普通の人」である読者の皆様の判断に任せます。 なお、さしあたって今日の論議とは関係はないですが、「みんながマスコミの記事を信じている。だからマスコミは重要なのだ」という「情報化社会」的発想の大部分の論旨は間違っています。マスコミはただの情報提供者の「今日的形態」にすぎません。100年前は自分のいいたいことしか載せないマスコミになどなんの正しさもなく、村の寄り合いの方が正しかった。それが生産関係の変化で、「マスコミ」は都市生産者に利益のある情報を載せざるを得なくなった、というだけです。 このように、情報提供者の位置は 1.環境に対し、自分がその通り真実と認知すべき情報の提供者 2.環境の反応について「生の」情報の提供者 との2通りで違います。 たとえば、1について、会社に行くときに通勤電車に事故があるかないかは朝のニュースが教えてくれます。だいたい朝のニュースは本当だと思った方が間違いがないようです。 でも、2について、情報がウソでもなんでも、自民党総裁が「年金なんてつぶれる。これからは私的年金だ」といったら、それはそれで権力者の言い分として考慮しなければいけません。 行為者は、自己のものとしうる情報について、その選択の余地があれば、提供者とその情報を選択します。(どうなると自己のものとしうるかどうかは、また次回) 人は自分の行為の原則に肯定的に関与すべく、情報を選択します。 ここで情報提供者も選択します。たとえば、年金制度の行方を聞くのには、酔っぱらいよりも大学教授に聞きたいものです。 このように、情報提供者の選択は、行為者の「選択」行為のありように規定されるのが論理の筋道です。 行為者は自己に係る「権力」と、共同性の「賞賛」「優越」を考慮しつつ、しかし、自己の本来に係る事実認知を見つめながら、情報提供者を「選択」します。 <情報提供者の持つ行為の原則への影響力> 行為者は彼の環境の変化に「認識的に」敏感です。生理的に嫌いだろうが、人は自分の環境に相対的に「大きな」影響を与える人物のいうことをきこうとします。この認識の優位は、犬だろうがゴキブリだろうが、同様です。 人は、女性が「社会的評判」「世論」に弱いと述べることが多いですが、これがもしも正しいとすると、女性の社会内位置の反映です。 もちろんここで問題は影響の「相対的な大きさ」です。 男は、攻撃的な問題解決策の展開の生理的順調さの認識により、別に一般論では他人のいうことを気にするわけではありません。 新聞が何を言おうが、「バカなウソをこくな」と胸の内で呟きながら、他人にはそれが権力者の意向であることを伝えようとして、そのことで自分の行為論的な自由を獲得します。 つまり、こんなとき人は自分で賞賛を手に入れるわけではありませんが、これを伝えるときに、「権力者Aの意見を言っている私」という権力的優越を手に入れるわけです。 これは一般的・普遍的な過程です。権力の媒介項となることにわざわざ否定的な賞賛を感じない限り(つまり権力のイヌなどくそくらえ、と思ってないかぎり)、まず一義的に生ずることです。 一方、権力の媒介項となることへの否定的な賞賛も、権力によって否定される意思がある限り、人は種々の幼少認識で手に入れることができます。 しかし、それは一方、別の権力対抗者の権力的優越を手に入れる、ということでもありえます。 両者は、「多くは」、社会内で自分があるべき位置への認識の違いにすぎません。 ここで「多くは」以外の少なさの一つは、「迎合」過程です。 支配権力を容認する人は、その自己認識度(分かってて嫌々やってる度合い)に従って、権力者の腰巾着であり、金魚の糞です。 自己認識度の高い、自立的な人間であっても程度問題なので、被支配者との対抗的な場面では権力者の立場に立つことになりますが、ここで他の腰巾着共と同じ行為をするわけで、まあこうした迎合は、第3者にとってさえ非常に醜いものです。 2.情報提供者と賞賛 人間は、できれば親のような先達に誉められた方がよい生物です。賞賛概念とはそういうものです。 さて、それでは、「新聞」は「先達」でしょうか? ここで、実は「情報提供者」とは仮の概念であることに気がつきます。 実は情報をくれる人とは単なるスピーカーではないのです。 ちょっと例で考えてみます。 社会の情報は、とりあえず、以下のようにいくつかの経過を辿ります。 新聞等に載った評論記事は、個人にとってそれが自分と同様の意見だった場合は「他者に対する」評論家である彼Aが持っている偉さ加減の優越を、彼も獲得します。 読者Bは、「自分に向かって」しゃべっている評論家Aを感じることはありません。 一方、評論家Aに自分と同じ意見をみたBは、評論家Aに反論する政治家Cに対して、自分にふりかかる危機を感じます。 ですが、政治家Cが自分に何かをいっていると思うわけではありません。「政治家Cは危険なやつだ」が残ったBの認識です。 さて、肝心の、行為者Bに対する賞賛は、社会の情報のうち、どこに存在することになるでしょうか。 <賞賛と優越は、行為者の内部的な社会認識(の変化)により引き起こされるということ> 当初において、社会の情報に存すると考えられる賞賛とは、「賞賛を探求する」行為者の身構えです。情報が(表彰状のように)本人を賞賛するわけはないからです。 ここで、探求する行為者Bに感知される賞賛は、行為者Bの裡に存在する賞賛過程への認識です。 ある2人の行為者のうち、ある者は朝日新聞が賞賛する左翼同伴者的評論家の賞賛への認識を自己のものとするでしょうし、またある者はサンケイ新聞が賞賛するヤクザのような右翼の行為に賞賛を見いだすでしょう。 ここで、行為論的にはどちらも同じ反応であるこの2者のうち、どちらが誰に賞賛を与えるかは、それぞれの人間の社会的性格によります。 評論性に賞賛を認識する過去のある行為者は、朝日新聞の論説に賞賛を見いだすでしょう。 この賞賛は、行為者の左翼同伴的行為の遂行に賞賛を与えます。 一方、単に評論の優越に反発を見いだす行為者は、自己の思いを強化するサンケイ新聞の論説に、対抗的な優越を見いだすでしょう。 この対抗的な優越は、左翼への反対行為の中の暴力的行為への許可を与えます。 これは実は行為者彼の社会内における位置の自己認識の結果です。 社会の情報のうち、「他人」とは、実は行為者にとっては「人間」という「生き物」ではありません。 社会を生きている他人を見て、ある行為者が他人を生き物だと思う理由を持つことは例外的です。 部長による叱責の現場においては、平社員彼は、なんだこのおやじ」とは思いながらも、彼が生き物だという理由を認識してはいません。 部長である彼は、タダの自分の行為の障害物Cにすぎません。 しかし生き物であれなんであれ、部長からは「賞賛」を受けることができ、その賞賛により「優越」をうることができます。平営業部員Dは、大企業との新規契約獲得について部長から誉めてもらったことがうれしく、同期平社員のEより偉くなった気がします。 これは、部長が人間だからではなく、彼自身が社会内においてどんな位置を占めているかのこれの心の内部的な認識の結果です。 ここで、賞賛とは、「誉め言葉」ですが、誉め言葉とは、結局、行為者にとっては行為の成就です。 人は、行為者が「賞賛を目指す」ことと「賞賛を得る」ことを混同してはいけません。 行為者は賞賛を目指して行為をするが賞賛を得ることはないことの方が多い。 これは牧師等の行為を考えれば分かります。彼が実際に神の賞賛を得られたら、世界はエヴァンゲリオンの世界です。 にもかかわらず、牧師だって誉められた方がよいのです。 <情報と権力> このように、権力者を経由する「提供情報」は、別に自分で認知に使用しなくとも、世間での認知として確定的な影響力を持つ素地があります。 一方、自分の認知に使用してもよい種類の、「権威的」提供情報というものがあります。 「専門家がいってるからそうだろう」という類の情報です。 これも先と同様に 「賞賛や優越は社会内の認識ですから、情報提供者の行為論的意義は彼の、行為者が思う社会内での位置に伴って変化する」 という文言が当てはまります。 両者を分かつものは、後者における生理性の(相対的)欠如です。 これは、従って情報提供者に対しては「言葉の本来の意味での賞賛」に近いものがありますが、提供を受ける者にとってこの伝達は、やはり優越の源泉です。 もちろん、ここでは、それを聞いた本人が聞いただけで終わってしまう社会的状況は問題外としています。 権力が絡む場合の特徴は、それまでの過程が事実の累積で作られるのに対して、権力がからむとそこで事実が確定してしまうことにあります。 自然科学においては、実験その他の主体的立場の移入(「じゃあ、私がそれを経験してみようか。えーと酸素と水素を混ぜて、、、、」の類)が必要なのに対して、権力世界では権力が決めたことに逆らわないようになっているのです。だから権力なのですが。 (賞賛や優越に関わる事実) 人は、ある情報について、優越や賞賛をそこにかぎ取りますが、直接権力に関わらずに認識することもありえます。 一般にそれは事実の認識の累積を得て生じます。 新聞で毎日「競争がいい」と報じられていれば、上司のいないお寿司やさんでも、カウンターでおしゃべりするときはこれでいこうと思う傾向を持つものです。 また、一瞬の事実で住むこともあります。それは制度的に事実の累積に裏付けられたものを背景に持つ社会事象の場合です。 たとえば、「勲章」というような社会的制度が有効的かどうかの累積です。勲5等の勲章というのはなんでも皇居の門をくぐれるかどうかという意味があるとか聞きましたが、勲1等だろうがなんだろうが勲章を持ってるから偉いなんて日本人ならだれも思っておりません(なに、よく右翼のいう冗談ですが)。でもどうもノーベル賞なら偉いと思っているようです。 それはこれを知った者が賞賛することを、当該に関わる人が知るからです。 かつ、その賞賛が、事実として一度にそこで、確定するからです。 <優越と賞賛の現実的意義の違い> 人は、社会生活においては、「普遍的な」価値文言を見つけることができます。基本的人権とか国民主権といったようなものです。 しかしそうした普遍性は静的な普遍性であり、みなに認められているのはよいですが、実際、権力下のそれであり、対抗権力のものにはなりません。 そうした普遍的な価値文言のようなものは、権力の追認であり、それに命を懸ける賞賛を含む要因もないわけです。 でも、権力が認めた普遍性では、優越性には焦点が当たるます。普遍的な価値文言を使用する人は、めったにはいませんが、今の自分の優越を確認して満足します。 一方、権力の対抗のためには、賞賛の動員が必要です。 情報の中には、それを使えばある種の共同性に認められると感じられる位置づけがなければならない。 人間が対抗する権力の中で得たい優越は、個々の、それより下の体系の中で必要が満たされればいいものです。 たとえば、当初自民党主流派に抗して「競争」を言い出した者は、シカゴ学派その他の流れを引く経済学主流派の学的な賞賛は得ていました。でも優越は、少数の企業経営者の饗応や大学内の主流というくらいなものでした。もちろん現実はいろいろでしょうが、概念的にはそうでした。 そのアピールがアメリカの攻勢によるバブル化(だそうですね)とその崩壊による経済失速にあって、アメリカの攻勢と、各種お先棒担ぎのマスメディア掌握により、普遍的な価値文言の位置を手に入れたわけです。 もっと左翼的なたとえ話ですと、フランス革命において、自分の共同性「だけ」のつてで(自分の共同性の戦闘力として)政府権力に参加していた下層商工業者において、自分が共同性を持つ中上層商工業者の発言は、本当かどうかはべつとして(あるいは正確に言えば本当かどうかはどうでもよく)行為を従わせるべき賞賛と優越の問題でした。 そこでは、賞賛の対象が、ほんとかウソかは別として、「自分(たち)の利害のため」を目的として、命を懸けてくれればそれでよいのです。 <情報と事実> 情報はこのように、社会でその情報を得る者の興味の問題ですが、そんな行為者の勝手気ままな性格の影響がある一方で、行為者の趣味に関わらずに社会の中で「事実」を形成することになります。 みたくもない記事ではあれ、生理性の確保のために経済情報を求める新聞記事の中にある見出しは、つい目に入ってしまいます。 たとえば、こんな記事: 日本には公務員労組として、いわゆる「親方日の丸」という倒産のない環境を生かして新社会の理念の実現を打ち出してきた「自治労」という存在があります。たとえば「労働に貴賎はない。家族の生活のために年齢の差はあるだろうが労働者は生活に必要な賃金を得られればよい」というのが昔の自治労の理念です。 その自治労が、役員に「経営倫理や企業統治の」研修、「全職員を対象に、中間管理職の心得や自己管理などのマネジメント研修を行う。さらに、書記職員の賃金は年齢で決まっていたが、やる気と責任感などを促すために、職務と等級を割り振って、昇級、昇格を制度化する。」 そうです。 (3年8月30日付朝日新聞夕刊) この記事により、このグローバル=アメリカ粗野資本主義化の流行は、もっと奨めるべき社会の流れとしてすべての読者に認識されます。 おお、利潤よりも人間が生きる質の方が大事なはずの自治労。今は亡き自治労。 世間の賞賛というのはこれに対抗する気がなければそのまま流されていく。流されてその代償に得ているものは、日本の平和です。 実は、こんな腐った労組でも平和を口にするから、私たちは日本軍の制度化を味あわないでいられる。こんな腐った労組でも、共産党系プチ労組だけになった社会では、誰も国家権力に刃向かうことはできない。 これは自民党その他保守政党支持者の方々にとっても同じ環境です。 小泉がいくら平和を願っても、大労組連合がなくなれば日本の平和は終わりです。 あるいはどこかにあるかもしれないラジカル左翼にとっても同じ環境です。そんなクズ労組がなくなれば俺たちの天下だ、なんてシアワセな夢は幻にすぎない。 ということが、3回位先には分かるでしょう。 3.情報の受容をめぐる副次的な問題 <情報の持つはずの意味と情報の与える意味の差異> 人間は情報を得るときは、情報を表現するすべての形態を感知します。そのため形式に流れる座業の学者を通すと、いくつかの誤解が生じます。 ・ 情報の内容と発言の内容 たとえば言語情報だからといって、それを運ぶ紙や人間の口調その他が無視されていいわけはありません。 感情的な同意を求めるための情報は、感情的な反応を得るための発言による必要があります。 たとえばある社会的規範としては正しくありません行為に対して、これを擁護するためには、単なる情報の内容の伝達ではなく、相手の感情移入をもくろんだ発言によらなければならありません。 相手の全生理性を喚起させる、神経の刺激、たとえば大きな声、大きな身振り、映像的な構成、その他です。 同一の歌の斉唱、その他。 生理的な反応は、感情的な同意を得る前提です。 ・ 情報の言語化の失敗 ある事態を言葉に置き換えるのに失敗すれば、当然誰にも伝わりません。これはとくに、自分(たち)の気持ちの表現の際に起こるのは、若い恋人同士の場合と同じです。 たとえば、私どもの世代には近しい「近代知性への反乱」です。 本来これは、偉い知識人の話すことが賞賛的であり優越的であること、あるいはその偉そうな言が実は他人事の第三者性であったことへの反乱でだったはずです。 非難されたのは、実は近代知性そのものではなく、偉い知識人心性であったわけです。 ところが、誰が言い出したものか、教授連中が怖かったのとしちめんどくさい勉強が嫌いだったのが反映したのか、反乱対象を「近代知性」にしてしまったおかげで、反乱グループはだあれも勉強をしなくなってしまった。 おかげで、その後は、体制派の「知性」的論理が幅を利かすようになってしまった。反知性はモダニズムに受け継がれその無力さを暴露するばかり。 まあ、どうせ大した心性も残ってなかったから、休んで頭を冷やすにはちょうどよかったかもしれないけど。 あんまりまとまってないですね。自主締め切り間際の論文のよう、ってそのまんまか。まあ、あとでまとめ直すし。 なんていっちゃあいけない。どうもリアクションがないと独り言になっちゃうんですよね。ごらんになったあなた、悪罵の一つもかけていただくともう少し改善されること請け合いです。「メールボックスコーナー」へ。 もちろん今回問題にしたのは情報を受け取る側の諸事情にすぎません。 情報が受け取られるためには、この情報が自分に関係があるかどうかが認識されなければなりません。 次回はどの情報が自分に関係あるか、というよりも、どの情報が他者に関係があるからそれをセットするんだ、といった主体的視点から眺めます。 アピールは自分にとってのアピールではありません。 という1行が、設定されないことを、余談ですが、実践的視点の欠如といいます。 認識と実践とは、巷間の哲学者にいわれているような科学主義的な立場というわけではありません。(巷間の哲学者とは実は皮肉で、哲学者なんて右翼も左翼も何も知らない者同士みんな一緒、ということです) 認識と実践とは、行為主体の実践行為への態度をいいます。別に実際何をしているかなどなんの問題にもなりません、一方、なにも考えようとしないやつ(自称哲学者)がNPOしようが選挙運動しようが、何がわかるわけではないのです。わかりづらいね。 まあそれはそれ、アピールは他者にとっての何かです。 なお、最後の本をお読みでない方への注の前に全員用の注をつけておきますと、 「賞賛」と「優越」という二つの概念は、それぞれ経験が教える行為の動因なのですが、そう分ける根拠というのは私の中では2通りにあります。 たとえば哺乳類、猫は自分の子猫にネズミを捕ってきてやってネズミの取り方を教えます。子猫は次に自分がネズミを捕れば、そこで母に見せにゆくでしょう。これが賞賛の生理性です。要は、成人になるために年長者の行為を受容し、年長者とこの同一性を確保することに自分の喜びを感ずる。 このとき、それまでの自分(と同様の他者)をバカにするという観念は働くでしょう。 また、イヌは、群の中で、ボスのイヌに服従するでしょう。そして自分がボスになれば他の者に服従を要求します。これが優越の生理性です。 ここではそれ以下の子分をバカにするという意識も発生するでしょうが、一方、さらなる大将への外見的服従的賞賛も結果するでしょう。それはみかけだけかもしれませんが、人間だったらその辺「本人はあのボスより過去はずっと立派なやつだったんだからお追従のハズと信じたいけれども、でもほんとにそう思ってんじゃないか?」って気になる人々も多いですよね。これが優越の持つ賞賛との近似性です。 ここで、じゃあ人間はどうなんだ、ということは私にはどうでもいいことなのです。 問題はあくまで、経験的にそう教える、ということなので、それが何に由来するかはそのうち誰かが明らかにするでしょう。私は悪いけど忙しい。 ただ、そう2通りがあって、それらが人間の観念というか脳神経組織の中で最後まで別個に分かれているものなのかどうかまで、多少ですが疑わしいところがあるけど、という感想があるだけです。 今現在の大脳生理学(心理学)では分かっていませんが、やはり賞賛と優越とは、遺伝的な差異の表現方法の違い、という問題なんだとは思ってます。 定義上述べてあるんですが、まあ、人間の対人的な生理反応で、賞賛といった方が適切な反応がずーっとあって、そのままずーっといくといつのまにか優越となってしまう、、、、みたいな。まあどっちでも、私の論理には影響がないことを確認しておいてください。 まあ基本的には「賞賛」は、多く神や自我、その他の抽象的な脳細胞の関連形成を前提としています) で、以下がほんとの引用の(注)です。 ************************************** (注;行為の原理と原則) 私の本をご覧でない方には、<行為の原理と原則>といっても分かりづらいはずですので、ここで、簡単に行為論の基礎を引用しておきたいと思います。 ‥‥‥‥ 人間が行為をする際に不可欠な、個人の主体的な行動の原理・原則をあげておく。 第1に〈状況の認知の原理〉 人間は、現在の自分の状況と将来の状態へ移行する手段とを認知しなければ、反射運動以上の行為をすることはできない。 これは優柔不断な人間や計算高い人間だけがすることのように受け取られそうだが、そうではなくて、どんな単純素朴な人間(や他の動物)のどんな行為にでも、不可欠なことだ。酔っぱらってビール瓶で殴りかかるような奴でさえ、自分が酒場にいることを認知しており、一瞬の間に、自分の前にビール瓶があることと自分が以前に殴る動作をしたときのイメージと、自分の相手が負けるイメージとが、将来のイメージとして神経組織を走るはずだ。 (もっともここで〈イメージ〉というのは、心に浮かぶ「イメージ」の根底にある作用のことで、現実には心に浮かぶ間もなく神経細胞を走り去っているかもしれない。) つまり簡単に言えば、人は自分がこうすれば相手がどうなるかを(誤解やマチガイはあるが)心の底で知って行為する。 第2に〈将来感覚の認知の原理〉 人間は行動する前に、かならずその行動を現実にしたときの自分を感覚してから行動するものだ。 人間の反射運動を除いたすべての行為は、頭の中で処理されるスピードにこそ違いがあるが、この将来の感覚を媒介として(多くの場合はイメージを現象させつつ)成立している。 さっきの酔っぱらいも、相手が負けたときの快感を認知して(予想的)期待とともに殴るわけだ。(もっともアルコールの作用もあるし、どこまで深く認知しているかは別だが。) 簡単に言えば、人は自分がこうしたときの自分の状況を心の底で知って行為する。 第3に〈確認の原理〉 人間は行為し終わった後に、その行為がどんな結果をもたらしたかを確認する。 これは、他の原理と違って、いつも生ずるというと言いすぎだ。でも、人間が生き続けるにはある行為を別の場所でも適合するように修正して再使用していかなければならないわけだが、この意識的な行為の成立には不可欠なプロセスだ。 相手が血を流して倒れていたのを確認したら、次の機会にビール瓶を手に持ったときに神経組織を走るイメージが異なるだろう。(それが快感で病みつきになるかもしれない。) 簡単に言えば、人は自分がしたこと結果を知らないと満足しない。もっとも忙しい現代、「こうなったはずだ」と信じて次の行動に移ることも多いが。 人間行為の原則 これらの原理をもった行動の中で、人間が何かの行動の選択を行なう際の原則をまとめよう。 第1に〈論理性の原則〉 人間は、たとえ子供でも、つじつまの合わない行動はしない。そもそも「考える」という行為は論理の道筋を必ず持っており、「考えて」する以上は、必ず何らかの意味で論理的な行為の選択だ。更にこの「論理」とは、以前に自分が行為した経験と今の状況との間で、どこが同一か(同定の原則)、を高速にイメージすることだ。 つまり、人は行為をするときは、自分の経験を通して、こうなる「はずだから」として考える。 第2に〈好悪の原則〉 人間は「好き嫌い」によって行為の選択をする。 これは別に愛情の有無をさすわけじゃない。人間が生物学的な存在であるところから、すべての行為について生理的な判断として「好悪」があり、この生理的な感覚が積み重なって、複雑な好悪判断がなされる。 つまり、人は、較べてみて、より好きなことをする。 第3に〈経験の将来感覚の原則〉 今述べた〈好悪〉は、具体的には、自分が過去に経験した生理的感覚の直接の記憶によって判断される。山に登って得た快感は、人に「僕は山が好きだ」と思わせる。 ところで、この「山に登れば快感がある」という認知は、この快感の記憶とは別に、生理的快感の存在する場所として「よかった」イメージ、「うまくいった」イメージを保存させる。そして、自分と快感との関係を保存したこのイメージは、後になって別の行為の判断の際に刺激され、使用される。 たとえば、山を削って道路を作る計画は、先に得た快感関係のイメージを刺激し、僕はこの計画に反対するだろう。(これは、僕が「山を好きだ」からではなくて(山には「性」もないし一般的に僕に対して対応をもつ主体でもない)過去の山との関係の認知を刺激するからだ。) 「価値判断」と呼ばれる判断は、この好悪によって判断された経験上の記憶のイメージによるものだ。 つまり、人の快感は具体的なモノにくっついて残る。そのモノは快感を呼ぶものとして人には大切なものになる。 第4に〈優越的自由の原則〉 人間は、行為の完成、つまり、一連の行為の流れを自己の意思のままに経験できたときに、自己の行為に満足を覚える。 そのため、この行為を邪魔されずに自己の自由の下に行なえる担保として、他者に負けないことないし優越していることを望む。 これは、日常的には最も重要な選択原則だ。 要は、人は自分の好きなようにしたい。 第5に〈賞賛(ー規制)の原則〉 人間は、他人から教育されて初めて一人で生存できる人間となれる。そこから、人に賞められることを望み、かつ、そのためのひとからの規制を甘受する、というより内在化する心的機構を持たざるをえない。 これは幼少期には重要な選択原則となる。ある年令の子供は(他の問題がなければ)人に賞められるように行動を選択する。 また、潜在的には、大人になってもいわゆる「自我」として重要な感覚を形成する。 要は、人は誰かに褒められたい。 人間の自発性 これら原理と原則は、いわば人間の環境的事情、人間が行為する際に受動的に神経活動を行うときの諸側面だ。人間の存在それ自体を考える際には、これら以外に、これらの環境性を身につける人間自身の問題を一つ考慮に入れなければならない。 つまり、人間の自発的事情、身体的な諸要請(欲求)と、身体性に裏付けられた行為の自由だ。人間は、生物学的個体として自己の生存を自分で確保していかなければならない。当然至極のことだけど、指摘だけしておく。 さて、行為の原理・原則はこれだけだ。重要な点は、ここでは誰にでも思い当たる当り前のことを羅列しているわけではなくて、「これだけだ」と主張している点だ。以下の行論でもこれ以上の素材は使わないし、その必要がない。 人間は、これらの原理原則の下で、自己のある行為の完成を求めて行為する。従って、行為の本来は個人の自由であり、種々の後発的環境的制限からの解放への志向だ。 もう少し簡単に言えば、人は好き勝手なことをしたい。もっとも、都会の人間が砂漠の真ん中で「さあここならお前は自由だ。好き勝手にしろ」といってもふつう楽しくはない。人は、環境によるいろいろな制約の中で、自分の認知に沿って思い通りの行為ができたとき、生理的に満足する。 ‥‥‥‥ 【12月分】 今月は、「行為者が、どんな情報に行為の原理・原則をゆだねるか」について、です。 われわれは、ある情報が行為者である我々に対して、10月分として、商品経済の中ではどれが「情報と化しうるか」、11月に、商品経済の中で「購買しうる情報」と化された情報が、しかし、売れるはずの行為者の間でどう扱われるかを見てきました。 ついで、ここでは、実際に情報を発する、これこそが私たちなのですが、が、どういう情報を作成・構成しようとするか(あるいは、しがちか)について見ていきます。 人がこういう理由でこれこれのイデオロギーを採用すると説明するには、シンプルに行為者の事情を説明するやりかたがあります。 まあ、当たり前のことです。 しかし、それだけでは、じゃあ今はなんでそういう事態が起こらないんだ、と聞かれたときには「行為者にそういう事情がないからだ」というだけで終わってしまいます。 そうじゃなくて、行為論が科学として、つまり人間の実践に寄与し得る価値を持つものとして存在するにはそれではなんの意味もありません。 行為者のそういう事情はこういう関係によって生じているんだ」「じゃあその関係を変えればいいんだ」という展開がなされて初めて、行為理論は科学となるのです。 というわけで、まずはシンプルにいってみます。 《イデオロギー採用の意識的側面》 従前のイデオロギーの改変は、まず現実の変更要求から始まります。 行為主体はまず自分の環境に即した未来を得るために、現在の事態に対して他人にとっては従来と異なった行為をすることがあります。 これに反対する人間は実力的に阻止できない場合は、言語表現を使ってまわりの者その他の協力を得ようとします。 これに対し、当初の行為者は、他の言語表現で他の者の協力を得ようと対抗します。 この2様の言語表現というものは、賞賛や優越を含んでいる(いわゆる価値観を含んでいる)もので、これをイデオロギーといいます。 これらのイデオロギーは、それ以前と同一の賞賛のもちながらも別の効果をあらわすようにその使用者によって変えられます。少なくともどちらかには、改変があります。 具体的な現実では、このどちらかの側の立場におかれた人で権力のない方が、「不自由」や「不平等」や「権利の侵害」を感じることになります。 表現はいろいろですが、要するにそれまで当然に到達していた自分の行為の将来が確保できなくなる事態を指しており、第1に。それまでの「社会の常識」であったはずの枠組みに対して、社会はこれを支持するはずだ、という表明がまず第1の潜在的なイデオロギーです。 これはほんとうに「社会の常識」であったかどうかは別です。 端的には、小学校で正しいものと習った道徳に基づいての思春期の行為は、資本主義社会ではまず通りません。まあいまはそんなものも教えられない情けない教師が多いですが。 いずれにせよ人は、とりあえずは旧来的行為規範の維持を訴え、これが通らない場合に種々の試行(本人にとっては本番)をしていくことになります。 1.賞賛と優越 さて、まず、人が使用するイデオロギーの範囲は、同一の賞賛を持ちうる範囲です。 人は使用する表現によって自分が賞賛や優越が得られるように、表現の対象を把握し、表現の内容を彫琢します。とりあえず表現の内容は、すでに流布されている「価値観」になります。それらが社会に存在することが、同じルートで表現する行為者にとって、それを真似することで自分の賞賛や優越となるのです。 ここでは、表現に対象となる範囲があることを説明しておきます。 (注;表現者の理論と世間) さっそくですが、注をつけておきますと、このコーナーの前半をごらんの方はおわかりと思いますが、表現は、「理論」なるものでさえ、書く人の思うがままです。 端的に「理論」についていいますと、表現者も行為者であり、この表現体系に登場する者は、彼の頭の中で彼の思うとおりに動いて欲しい。 こうした表現者の行為環境は、彼の「理論」の中に、自分の頭の中にできる「操作概念」を作り出します。 「操作概念」という概念自体は「本来実在しないが、理論の透明性のために設定される理論上の概念」のようなものですが、と、同時に理論の透明性のためではなく理論の恣意性のために、実在しない概念を世間の実在する人間たちとして呼びかけるのです。 いわく「民衆」であり、「プロレタリアート」であり、あるいは「臣民」です。 およそ売文業者は生きている「個人」などに大きな興味を持つものではません。そんなものは操作できないつまらないものです。 個人が興味の対象となるのはやっと印税を手にして、儲かったとか、飲みに行こうかとかおもうときだけであり、それで充分なのです。 こうした概念は、しかし、世間をよく見た売文的表現者が使う限りは、世間の人々も誇らしげに使うわけであり、誇れれば誇れるほどさらに概念自体が「売れる」ようになるのです。 もちろん表現者の手に落ちるものはその他「国家」でもよいし「日本」でもいいでもいい、さらに「自由」でもいい。 閑話休題。 人は行為の原理原則にのっとり行為をします。このとき重要なことが人は自分の行為の将来のイメージを、意識するとしないとに関わらず、神経内に思い浮かべて行為すると言うことです。 このため、人は自己の行為の可能性を認識しえない事物を自己の行為環境に取り込みません。 人は自分の世界を持っていてそのテリトリーの範囲においてしか行為しません。 すなわち、行為には行為の対象となる領域があるのです。 <賞賛> まず、ごく一部の不幸せな人以外は、人は賞賛され、あるいは行為により人を優越できる将来イメージを持ちうる社会的なテリトリーを持っています。 これは具体的な人間による、経験的な関係範囲となります。 これについて、家族の役割は根源的に重要であって、家族において賞賛のパターンを取り入れられなかった者は、不幸にして、社会における自分の位置を手に入れることができません。端的にいえばこうした人は非社会的な行為者となるわけです。 ついで、人は世界を自分の中で組み立てている児童期思春期に、社会によって設定された賞賛の主体の存在がある、という抽象的な賞賛主体の位置感覚を形作ることができます。 「天にまします神」とか「(世間的に)尊敬されている優越者=感動した東郷元帥」知らないか、、、みたいなものです。 こうした行為の「観念的対象領域」は、具体的人間の諸関係を飛び越えてある程度長期的に行為者の世界に位置することができます。 ・時代的な賞賛の具体化 一般に世間の人々の優越や賞賛は、一般に流布されている事実認知の乗り物に従って、それ以前に社会の規制的な枠組みとして認知された優越や賞賛を共有しています。まあ、それが「一般」ということですが。 これが通常の賞賛や優越としてイデオロギーが組み込むものとなります。 それ以外の優越や賞賛は、自由の束縛が一般に認知された時点で生じます。 自由の束縛の認識は、その後の時間的経過を支えるコミュニケーションの中で、一般にこの束縛の解除の共感をも認知させます。つまり、その時点での、権力の否定・粉砕を賞賛と優越の対象にします。 この両者はいずれも行為者の主体的な社会領域に応じて生じます。 つまり、ここでは他者の情報は、ヒマつぶしにしかすぎず、他人である行為主体のすることといえば情報を弄び加工することです。たとえば「井戸端会議」がそれです。 ・抽象的な賞賛の対象の範囲 とりわけ抽象的な賞賛においては、賞賛の対象(賞賛してくれる主体)と賞賛の対象の有効な範囲(「何をしたら」賞賛してくれるか)というものが分裂しています。 具体的な人間においても分裂はしてはいます。「母に誉めてもらおうと思って洗濯したけど間違えて母の絹のブラウスをクシャクシャにしてしまった。お父さんに誉めてもらおっと」が、普通は各人に合わせてセットされていますね。 でも抽象的な賞賛の対象は、特に何でなければいけない、という規制はありません。 (なお、なぜ「ありません」なのかは、大脳生理学(今はそう呼ばないか)等にまかせます。) 人は、神の座に国家をおくこともでき、マルクス主義をおくこともできます。 この自由度のために、失われた「神」はいくらでも新しいものと交換できます。 なお、具体的な人間と抽象的なモノとの間に、中間的な存在もあります。 「憧れ」という感覚です。 憧れは自分の将来イメージの実現要求です。賞賛・優越、好悪その他の行為の原理原則により、人は将来のイメージを設定し、同時に自分を将来へ向けて「投企(自分という存在の投げだし)」をします。 具体的な人間との違いは、行為の充足が普遍的満足感にしかないこと。 抽象的なモノとの違いは、コロコロと対象が変わるわけではないことです。 (注;娯楽) ちょっと注をつけておきますと、本論ではいつものように賞賛・優越・生理性・事実認識を取り上げていますが、要点は行為の原理原則ですから別に賞賛と優越だけが話題になるわけではありません。「快・不快」も関係はします。たとえば娯楽です。 娯楽とは、少ないエネルギー消費によって確保される肉体的快感への状況移行をいいます。 これはその大部はわざわざ社会科学的に解明される必要はないが(たとえば、パチンコはまだしも、将棋・プリクラ(古すぎ)などの純娯楽)、そのある部分は、生理的快感のうち、賞賛・優越に係る事実認知を含んでいる。これが運動的アピールの素材となることはあります。 <共同性のありか> これら賞賛と優越を取り仕切るのは生理性のあり方ですが、とりわけ「共同性がどのように生理性を取り仕切っているか」によっています。 賞賛も優越も純粋に人間の間に生じる問題なので、単なる趣味的な、子供のような権力行使に関わる問題ではないし、ましてや生産の自然条件そのものに関わる問題でもないわけです。 共同性というのは、何回かいいましたが、人々の間で同一の境遇と同一の境遇による文化の一致をもった事態をいいます。 境遇とは行為者主体Aに対する社会的規制のことですから、例えば、刃向かうと会社をクビになり死に至る可能性(致死可能性)、暴力で殺される可能性(殺傷可能性)、権力の階段、その他の同一のことです。 この「その他」については、生産関係的規制、たとえば、親方子方的な生産技術の伝承と、生産過剰に陥らないための諸規制もあるし、同様に、米作り等の共同作業上の規制もあります。 抽象的に言えばそういうことですが、でもこうした個人内部の超歴史的ー普遍的規定がある時代ではどのような形をとっているかという点では、そのときそのときの歴史的時代において必ずしも客観的に把握できるわけではありません。それにはある程度の「逆立した」把握が必要です。 共同性は、個人に翻訳してみれば、個人の意識においては、自分が代替的に陥る境遇の存在をいいます。アメリカの白人に「社会生活での取り扱いで黒人と同じか」と聞いてみればみな否定するでしょう。(まあ95%の人は、とでもいっておきますか) これは意識調査で明らかになるレベルです。 同様に、具体的な賞賛や優越は、個人に翻訳すれば自分が行為を同一にする相手の存在を指します。 賞賛や優越の根拠は、自分の行為であり、従って相手の行為です。行為の如何が賞賛や優越の現象形態なのです。 これも、「あなたは誰を目標にしていますか」とかの意識調査ができます。もっとも多少表現に工夫がいるかもしれませんが。 抽象的な賞賛というのは典型的には宗教信仰ですが、これも注意は必要ですが意識調査できるでしょう。もっとも、お正月に初詣に行くのも信仰になってしまうと、かなり疑問ですが。 2.生理性 <生理性をめぐるイデオロギーの創作> 生理性をめぐるイデオロギーを作ろうとする者は、これを聞くであろう者についてその利益になるであろう事を考えます。 しかし、行為者の知能範囲は自分の環境を出ることはありません。 およそ、すべての「生理性」は言葉にしたら何ほどのこともありません。「飢餓」は生理上ではなによりも重大な現象ですが、「われわれは腹を減らしている」という言葉が運ぶモノは、せいぜい生理性のレベルをクリアした上で越えた「好悪」の部類のものです。 およそ生理性は今日明日の問題であり、それ以外の生理性とは「予想」の問題です。「このままでは我々は飢えて死んでしまう」といった表現です。 すべての告知すべき予想は、予想自体において生理性を含んでいなければなりません。 「こんなことが」という表明の明らかにすべきイメージが、自己の生理的危機を、実感として描けなければならないのです。 たとえば、満腹の時に次にくる氷河期の話をしても何のイメージも湧きません。 一方、大震災の時に石油の輸入危機の話をすれば多くの人間がこれを実感します。そういう意味です。 <生理性をめぐるイデオロギーの採用> 人間にとってこの上もなく大事であるはずの生理性については、しかし、イデオロギーによって手だて化する必要がありません。 人間の生理性は、眼前にある食料その他の生活必需品の有無の神経的認知を除いては、事実認識に属するものです。 明日の米が手にはいるか入らないかは人間には関知ができないものであり、それは米屋の発言か会社の給料担当者の言を信ずる(ないし疑う)しかないのです。もちろん信じても裏切られるときは裏切られますが。 したがって、ここでは生理性をめぐる「事実を装った言いふらし」が問題となります。 必需品をめぐる生理性に関する「言いふらし」は、多くの場合直接的というか即時的な性格を持っており、あまりアピールの科学的分析の対象になるほどのものではありません。 「米がもうないぞ!」「小泉は蔵に米を隠し持っているぞ! 小泉を襲え!」のたぐいのデマは、旧来通り社会心理学者が「分析」なり評論すればよいものです。 そうではなくて、 第1に、現在のように、物資がカネを経由して手に入る時代には、生産関係をめぐる事実認識が生理性をめぐる論点となります。 論点なのに誰も何も言わないのは、デマさえいえなくなった左翼のテイタラクをバカにすべきでしょうが、そうではなくて、もう左翼がいなくなったのです。 真理は何も変わってはいません。 マルクス主義が間違ってたといっても、間違った部分については昔からのことです。間違ってても正しいとと強弁し続けた人種が消えただけのことです。おかげさまで正しい部分さえ忘れられてしまった責任をどうにかしろといったって、そんな責任感のある奴らじゃないから平気な顔をして民主党の世話かなんかやいているのです。 昔から変わったことは、第1に、爛熟期資本主義の次の一歩について具体化できる昔だってごくごく少数だった人間が少数さえいなくなったこと。(私が隠れているようにインターネットのどこかに隠れているのかもしれませんが) 第2に、そんな具体化について「いいたがる」やつがいなくなったこと、この2点です。 人は、思想者だってただの行為者です。 生産関係の主流からはずれる思想者の思想行為は、生理性によっては支持されません。これを支持してくれるのは、賞賛と優越をもった読者等です。 ここでも賞賛や優越の方が大事なのです。 <生理性の第2;権力> しかし、そうした問題を越えて重要なのが、権力問題です。 生理性が生産関係という自分の行為に直接対応できない種類の現象に捉えられてしまった資本主義的現在、行為論的主体は、実際に目に見える権力で、自分の行為の自由を現実化せざるを得ません。 つまり、自分を規制する何者かに対して、権力をふるうことでいわばストレスを解消する対応です。 運動にとって重要なのは対抗権力に乗っかる対応ですが、いったん自由から疎外された行為者にとっては、その権力が対抗的か支配的かどうかはなんら問題ではありません。問題は単に自己の「これからの」行為論的自由です。 ここで問題となる権力とは、武力的暴力のことです。 生産関係に対しうる武力的暴力は、資本主義以前のそれが、武力的収奪を指しているのに対して、国家に収斂されたそれ、という、われわれ個人主体にとっては進んだ「疎外」形態をとっています。 人は家庭内暴力に対して国家の武力を期待できます。 国家の武力は、国家内人間の事実認知に即して、生産関係に接触するまでは、動作しうるのです。 かつ、生産関係に余裕のある世界にあっては、国家的武力は、事実認知の赴くまま、生産関係を変更操作しうるのです。 すなわち、生産により7割がうまく生きている社会にあっては、残りの3割がどうであろうと、その生産関係の残余の統制は国家的武力の思うままです。 残りの3割まで関知するかしないかは、共同性の所在如何であり、この共同性を規定する生理性は、充分国家的武力が規定しうるのです。 具体的に言えば、合衆国アメリカの有色人種は、連邦法により奴隷にできるのです、事実認知如何で。 ここで生産関係という関係とは、個人にとっては、単に生理性を確保すべき道筋にすぎません。 それは資本主義社会にあっては一つの道筋に違いないのであるが、爛熟した資本主義が壊れようとするとき、生産関係もその唯一たる力を捨てるのです。 <現実的方策> 一方、人は、そこに行為の諸原則が立ち働かない限り、自己に否定的な行為などしません。 人はそれを他人にさせたければ、代わりに権力者の否定、その他の代替的賞賛・優越を確保させなければなりません。 ここで、その賞賛の対象領域は制限的です。どんな賞賛でも設定できるということはありません。 さらにその対象が大衆全般であるならば、「既存の」大衆の生理的・優越的・賞賛的基盤に働きかけなければなりません。 権力者の否定は、権力の行使が日常的行為を暴力的に制限する事態が必要です。 情報をめぐるシンプルで原始的なポイントの一つは、権力の認知の様式です。 権力が存在するといったところで、それは常に人間の背中にいるわけではません。 人なり国家なりが自分の意思を権力で行為者個人である人間に押しつけるには、それを認知させる必要があります。 いってみれば、権力の認知は暴力の現前と、その経験による創造的認知によるのであり、かつ、それは1個人に属するものです。 ある人には身に沁みた権力の存在は、他の人間には伝染しない。 権力の認知への対応も、それゆえ1個人に属するものであり、賞賛の支えなくては、国家官僚群といえども瓦解の道を辿るものです。 それでも通常、生産関係をめぐる権力の認知は、生きている人間にとって見ればすでに制度化された関係をめぐる「生きにくさ」を通して認知の一歩手前にあり、これに背いた場合の「法」という明示的な権力行使の手段によって認知されます。 これに対して、対抗する権力の認知は、いくつもない不確かな経路を辿る他はありません。 いわく、権力者への直接的肉体暴力の脅威の世界と、その他に思い描きうる、しかし、「脅威」以上でしかない世界です。 もちろんその脅威は、どちらもいずれ個人しか襲わない暴力として生産関係の脅威と同様の潜在力をもつが、その潜在力が同等だ、と知れるための条件がいくつかしかないのです。 こうした事実認知を除けば、それ以上への対抗権力の拡大は、賞賛を通じる必要があるのです。 行為主体の原則の一つである優越も、同様の、非常に認知的な事柄なのであり、その意味では、(それゆえ)非常に個人的なものです。 かりに賞賛も対抗的な権力も設定できる状況であれば、優越は存在するようになります。 これらの「個人的なもの」という規定性は、要するに、権力や優越が個人の認知に依っているということを示しています。それはさておき。 この賞賛の対象領域の制限が、支配的なイデオロギーは支配者の思想であることを決定づけます。 生理性を基盤とした賞賛・優越は、それで大衆を巻き込もうとする限り、国家支配者のコースと同一となります。 大衆自体に矛盾がある場合にのみ、対抗的なイデオロギーが、新しい共同体のコースを作ることができます。 何度か確認したことですが、本質的に重要なのは、人は個人的に生きているということです。 その中で、弱者への同情から左翼になり、あるいは利己主義から右翼になるのです。 どちらも同じことです。 個人的な諸行為の原理・原則が社会の幸せを向いていない時代には、トータルとしてどこまでも資本主義的生産関係のなすままに連れて行かれるのです。 それじゃあ何やってもしょうがないだろう、って? そうじゃなくて、「ウケねらいの表現は」とりあえず右翼の勝利に終わる、と言っているだけです。 それ以外に、生産関係を動かす表現も存在するのです。 一般論から言えば、それは、たとえば資本主義的消費様式を動かすための表現ですが、これはあまり大きな論題ではありません。 そのことではなくて、 しかし同様に、第2に、「関係」が実はただの生理性をめぐる優越と賞賛の織物にすぎないことからの、生産関係への「自由な」アプローチ ついで、第3に、「関係」が実は権力と合体した関係であることから (これにより第2の点については制約ができるのですが)関係を権力により変化させるための、体権力への表現のアプローチ といった道が存在するのです。 3.事実認識 さて、少し話が入り組んでいて申し訳ありませんが、以上の話の中で、実は込み入ってきそうなときに問題となったのが、行為者による事実の認識ということでした。 とりわけ、権力の認識・優越の所在には、事実認識が大きな役割を果たしています。 また、共同性や賞賛は具体的な人間関係の認知があればとりあえず住むわけですが、権力という目に見えないモノは認知過程を経ずして自己のものとはならず、同様に、社会的な人間の中での個人行為者の優越には、権力の認知が不可欠なのです。 (人間にとって事実認識は大切だが、単なる事実の提示は意味がないこと) ところでしかし、人が自分の将来について認識を行うとき、実はそれは小学生が九九を習うときのような経過を経るわけではありません。人は自分の行為論的将来について、「面白さ」「やりがい」をほんの1.2秒の猛スピードでその展望の底に見いだしつつそこからの発展的展開を受け入れます。すべての人間はそのぐらいに賢い。 この人間の賢さは、もちろんその他の動物に当てはまるほどの「大したことのない」賢さですが、人間個人の、そして共同社会の、将来を規定しています。 人は、第1に、自分の行為に関係がない、と感じたことに、その後の人間存在によって新たな別個の行為論的将来を提示されない限りは、それ以上の関心を持ちません。 すなわち人は、たとえば自民党内の政争に関心など持ちません。 同様に、政治にかかる自己力操作を行ったことのない人間は、自民党と民主党の確執に何の興味も覚えません。おせっかいで大嫌いな創価学会員に自民党支持の説教をされるまでは。 人は第2に、自分の行為の将来に関係がない、と感じたことに、それ以上の関心を持ちません。 自民党が政権を執ろうが民主党が取ろうが同じだな、と思った労働者は それ以上の関心を持ちません。それが同じでは自分の明日の食料が手に入らない、と認識するまでは。 かくて、人間の行為は新たな事実認識の提供よりも先に、賞賛と優越(にかかる事実認識の提供)が優先します。 情報の採択を決定するこうした権力的関係について、それらの認知について、また来月のテーマといたします。題してしまえば《イデオロギー使用の無意識的側面》 なんか一月一月あまり進んでませんが、その割に筆者としては、トータルにはかなり時間を使っています、ということは、まだ先に中心部分があるんでしょう。それでは。 【1月分】 今月は、 《イデオロギー使用の無意識的側面》 情報の採択を決定するこうした権力的関係について、それらの認知について、です。 これに関連しては、人間の行為は新たな事実認識の提供よりも先に、賞賛と優越(にかかる事実認識の提供)が優先することだけお話しました。今回問題にするのは、そんな賞賛と優越の中で権力関係をどう認識していくか、ということです。 この認識の仕方で、「変えられるだけの」権力構成は変えることができます。 0.「変えられるだけの」権力構成 制度改造は、革新を望む者を含めて、当事者にとって不本意なものばかり、と考えたほうが実際的でしょう。そうでなければ不利益部分の人たちは、そのまんま死んでしまうことになるからです。変革期においては「痛みは分かち合う」しかありません。 しかし、また、それらの不本意な制度改造が歴史過程にとっては一番最短な道筋であることも理解しなければいけません。 なんて知ったところで、人間に変えられる事柄は限定的なものです。 まず、「身分」の構造というものは生産手段が決定することを忘れてはなりません。人は生産手段を与えられそこにしがみつかざるを得ないことで「身分」が歴史的な確定を得ます。 逆に言えば、個人の持ちうる生産手段が外部的に決定されない社会においては、身分は社会運動を経て解消しうるのです。現在の日本がそうです。改悪がもくろまれている教育改革が実現する前の日本の教育制度においては、身分は「変えられるだけの」権力構成に当たります。 また、経済的階級構成もシンプルに、あるいは「隠蔽」的に暮らすこともできます。 本来資本家とプロレタリアは同一ではありません。しかしこれが同一と見なされうる社会が存在し得ます。 プロレタリアと資本家との間にあっては、対立点が明確化しない限り、その他の、たとえば住居の取得、子女の教育、新しいIT機具の修得等の「同一の」状況をもって、同じ「日本人」認識がなされ得ます。 私たちが住んでいる社会は、5階建てのビルだと思ってください。 そのビルの屋上と地下に支配層と被支配層があります。 このたび問題にしうるのは、その間のビルの1階から5階間での部分を引っかき回し、吹き抜け構造にしうるか、といった問題になります。 そんなことをしても社会に支配層と被支配層があることには変わりはありません。社会の中の「階層」がはっきりしなくなり、社会の風通しがよくなるだけです。 ただ、そんなことでも、不幸な人間がぐんと少なくなることは確かです。 もともとシンプルな権力社会には、政治権力者と経済的政治権力者しかいません。 政治権力者とは、政治プロパーの専門家であり経済的政治権力者からみればただの下僕でありますが、政治プロパーとして、それまでの支配権力を握った「正当な」権力者でもあります。 これが資本主義のシンプルな姿です。 かつ、そのまま崩壊する資本主義の姿でした。 しかし、「没落せざる資本主義」すなわち大衆を巻き込んだ商品経済の進展は、資本主義に内在する階級性を隠蔽し続けました。 消費の大衆化による経済権力者たちの自己喪失は、経済政策の脱資本家化を目指さざるを得ず、経済政策の非目的化によって政治権力者の自己喪失を結果しました。 さらに、普通選挙制によって、政治権力者は、権力者たる自己意識まで危ぶまれています。 一方、「非知識労働者」は、教育の「大衆化」「普遍化」により、支配権力者との意識的「同化」を進展させました。「インテリ」は、権力者の権力意識の自己喪失のあおりを受け、シンプルにもともとの姿である売文業者の姿をあからさまにしました。 もっとも、ここで、間違えてはならないのは、「別に大衆が権力を持ち始めたわけではない」ということです。 「幻想がいきわたり始めた」のです。 といっても別に大衆が権力を欲しがってそれを得た、という幻想ではなく、「自分にもなにかできるのではないか」という幻想です。 いわく、西欧の幻想であり、西欧への幻想でもある、「市民社会」です。 1.情報の事実の認知と賞賛 前置きはこれくらいにしましょう。 賞賛は、ある具体的な行為から見れば、他者の一拍おいた反応を間に介在させています。 「この規制を辿る者は」 の次にあてはまる〈正しい〉〈美しい〉〈勇気がある〉その他「なんと呼ぼうが同様の」賞賛が外界の「行為者」に予定されていることを認知してから、行為者は賞賛的行為を行います。 この外界にいる他の行為者、あるいは抽象的・潜在的な「行為者」の規定性が問題となります。 「賞賛」は、いいかえれば「行為の実現に対する庇護者による評価」ですが、これは「感謝」と「称揚」とに分かれます。 すなわち「ありがとう」という言葉および態度と、「えらいね」という言葉および態度とです。 感謝の体系は、特に社会的な支配関係を含みません。 人に対する感謝と、感謝への感受性は、普遍的に推進されるべき体系です。 もっとも個人差と、ある個人においては幼少期の庇護者からの「感謝」表現の欠如。代わりに感謝されるべき行為結果への「裏切り」等により、望んでも得られない場合がありますが。 支配関係に関連する賞賛とは、称揚の体系です。 生誕後、庇護者の持つ社会的規制は、行為者の行為結果への「称揚」という形式をとって行為者に伝わります。 天皇にお辞儀ができれば「えらいね、この子は」といわれます。 ここで、行為者にとって行為は2通りに分かれます。 個別的な行為と、複合的な行為の累積=未来の行為者本人です。 人は、消費物資の生産方法から距離をとった時代には、個別的な行為以外に、遠い将来の自分の位置を想定しなければなりません。 「今日は狩りに出て獲物を捕ってこなければ」「今日は田んぼの雑草を抜かなければ」 といった直接的な生産手段を手に持つ時代では、賞賛は個別的な行為、「ライオンをやっつけてきたぜ、えらいな」「あいつの田んぼの稲はきれいに実を付けたな、すごいなあ」といったものに限られます。 一方、賃金労働者の子は、自らの消費物資生産を社会の職業から選択することで得なければなりません。こうした行為者の未来の存在は、「称揚」を将来の行為者本人のありように結びつけます。 「総理大臣はえらいのよ」「陸軍大将におなりなさい」 この2通りの行為について、称揚は社会の規制を行為者に伝えるのですが、とりわけ未来の行為者を巡る称揚は、権力的地位の事実を行為者に伝えます。 その社会で「偉い」人は子供にとっては何の批判もなしに偉い。 子供にとっては、ここで、「偉い人」の存在と、彼に向かう自分という、二人の関係がセットされ、以後の子供の「社会対自分」の認識を形作ります。 一方、庇護者に社会的規制の認識が薄い場合には、賞賛の持つ権力的地位の事実の伝達はままなりません。 ここで、だからといって、権力的事実が消えるわけではないことに注意しておきます。 今議論しているのは単に社会構成の認知方法と、認知した社会構成への行為者の対応方法についてです。 権力は、認知していなくとも行為者に襲いかかります。 ぶ細工な男の載ったポスターを破っただけなのに、驚いたことに警察官が来ました。それが選挙候補者のポスターだったら。 2.情報の事実の認知と優越 一方、優越は、ある状況から把握される、行為者の具体的な状況判断です。 人が動き回る外界の姿から、直、人は優越的規定性を自分の行為に反映させます。 優越は、生理性の確保の第一義的必要から、まず生産組織上の権力行使に現れます。 これにより、行為者にとっての「事実」、すなわち「彼に刃向かってはならない」「あいつが反論するのは許す必要がない」という、要するに「支配」の実体が発生し、ここから個人のイデオロギー事実が再生産されていきます。 もちろん、これらは行為の結果でもありますが、行為の結果そのものではありません。 ここでの行為の結果は、たとえば「上司がオレにひどく怒鳴りやがる」とか、「農村の寄り合いで一人反対意見をいったら誰も田植えを手伝ってくれなくなった」という状況です。 ここで、それらは社会の事実ではあるが、個人の行為の指針となる事実ではありません。 自分にとっての事実は、「だからオレも早く偉くなろう」、上司に刃向かうやつは『とんでもない』やつだ」、「誰も村の一致を乱してはならない」であり、かつまた 「会社のために献身するのがわれわれのつとめだ」、「村を守れ」というイデオロギーへの傾向的参加です。 生産組織といっても、生産様式により、従って「時代により」、様変わりをします。 第1次生産的地域共同体における固定した地位の権力行使、その構造によって、行為者が差別的優越を身につけるのは、戦後来、いくつもの告発的論考の示すとおりです。 当然に、といっては社会科学にならないがとりあえず当然に、差別に批判を持てない全体社会にあって、差別的イデオロギーが世にはびこります。 そして、戦後の歴史が示すとおり、人口の8割の農民社会から2割を切る産業化の歴史過程の中で、差別は糾弾されることになっていきます。 これに対して、8時間労働上の労働組織におけるサラリーマンにおける権力行使にあっては、たかだか、たまたまその会社でカネを得る間だけの拘束であり、ここでは行為者間の権力の相違は単なる組織上の優越の認識になります。 もちろん、と同時に組織上の優越が「存在してしまう」、ということはあります。 どうやら他に優越の根拠を持たない多くの人間にとって、上司の権力は魅力的なものらしいです。 本来たかだか事務分担であるはずの組織分化は、この権力行使の構造によって、賃金その他の格差の温床となります。 (もちろん資本主義の生き残りにとってこの格差が絶対的窮乏化の法則を逃れる重要な要因であることは別に述べました) 3.社会全体としての賞賛・優越の認知と行為 <生理性からの脱却と「思想」性、あるいは賞賛・優越性> 最低限の生理性から離れていくと、そこに賞賛や優越の根拠が生まれます。そうした賞賛や優越が「権力行使」と結びつくとそこに大きな運動が生まれます。 権力行使は行為主体にとってはできるだけ国家的規模の権力であることが望まれます。これに単なる暴力行使である個々の行為が合体します。 その根拠は賞賛や優越を「体内化」している若年層の存在です。 若年層に内在する既成高年層への反発は、シンプルに暴力性と結びつきます。 さらに同様に保持する賞賛・優越の自己内根拠の薄弱さは、世間の賞賛や優越の波に容易に呑まれます。 一方、生理性から離れた高年層は自己が有していた既存の規制に刃向かうことに、「賞賛と優越の上から」立ち向かうことができません。 ある個人において、その社会的時代において自立すべき規範が強制された場合には、彼個人は、自己の中に権力を見いだし、同様に自己の中に賞賛を見いだします。 なぜこれが「同様に」かといえば、自己の中に権力が存在するには、自己の生をあるいは同じ事ですが死を賭けた未来が存しなければならないからです。 もちろんここでの「賭けた」の意味合いは、観念的諸観想に過ぎませんが。 あるいは、諸個人において、他律的な賞賛によってしか自己の未来を描けない場合、たとえば権力的な規制の欠如により母親のいうがままにしか未来を構築できない人間にとっては、彼の自由な未来には、権力というものへの、見知らぬ憧憬が立ちはだかります。 ここで、たとえば50年代労働運動〜60年世代に関して言えば、 小学生その他で具体的に権力規制された賞賛の存在により、彼らは 具体的なスローガン呼びかけに対して乗っていくことができた、ということです。 具体的な人間や村落・企業に対する賞賛は、具体的な賞賛を身につけた者にしか対応できないものです。 それは個々のエリートだけではなしに、相当量多くの「大衆」にとっても乗ることができた課題でした。 一方、自立すべき規範は、社会の具体的規制の中には見いだし得ないものです。 70年闘争は、多かれ少なかれ、インテリに近い層の運動であらざるを得ませんでした。 さらに現在においては、権力の行使を自分でする、さらに命を賭けてするという社会層は存在していません。 (もちろん述べているのは社会的性格なのであって、すなわち、そうした人間のカテゴリーが作り出す(擬似的に集団的な)集合行動のことです。個別的に生き残った人間はもちろんあくまでも存在します) 現在の当該層は、自分が痛い目に遭わなかった権力の行使については、憧れしか持っていません。 ここで重要なのは憧れを持つのは普遍的傾向であり、それは別に何らそれ自体自由に反していないということですが。 4.権力的関係の認知 さて、それでは普段は隠れていて、いったん法に反抗するときに被支配者の前に突然現れる権力関係とはどう認識するものでしょうか。 行為者に関わる行為論的原則は、生理的条件に関わる社会的規制を除いては、先に述べた賞賛と優越に関わるものだけです。 したがって、これ以上のことは個人単位での行為者には認識ができません。 生理的規制はそれぞれの社会的位置によって異なります。 たとえば行為者が生産方法から距離のある社会での若者は、自分への規制が少なくとも「社会」に属することを認知します。(行為者が直接に生産方法と直結している社会では、社会的規制が共同体の中にありますから、かえって「全体社会」はそんな規制を規制してくれる「良い場所」であることもあります。) そんな若年層は、肉体力よって規制突破=自由を認知することになります。まあそれが正しいかどうかは別として。 私たちが知っている(と思っている)権力に関わる諸関係は、あとはその他の情報媒体から得た「知識」にすぎません。教科書や新聞に書いてあることを「信じ」たり、そんな事実から類推して思っているだけのことです。 学者が書いているからそうだ、ということは批判する者がいない学者に限って正しいかも知れませんが、そんな学者はいません。 だから昔ルカーチというマルクス主義者が「労働者階級は自分の状況を認知することが社会の仕組みを認知することになるから、唯一正しいことを認識できる階級だ」といって大方の批判を浴びましたが、これは他の階級の人には社会的規制を認知できる生理的条件がないという意味から、マルクス主義が正しければ形式的には正しい発言ということになります。 そうするとお前が科学だとかいって書いている議論はなんなんだ、ということに当然なります。 これも間違っているかも知れないことは否定するものではないのです。理論の提出者はとりあえずは表現し、他の社会関係の中に位置する人に批判されさらに理論を彫琢する、この作業を経て、普遍性に近い理論となるわけです。 5.情報の事実の他者への伝播 人の、他者の意見への対応は、行為の必要があるかないかです。 行為の必要といっても、その他者の発言が緊急に生理的危機の回避を要求するもの以外は、感情的憤激なり感情的笑い等の直接的表出であり(怒ったり笑ったり)、それ以上ではありません。つまりどうでもいいってことです。 一方、それら意見は、次に使用できそうな場合は準事実として記憶に整理されます。 ここで、ストックされる準事実は 事実として使えそうな立言と表現すればよいことがありそうな立言です。(もちろん整理されない、忘れた方がいいが忘れられない意見がないわけではありません。) 前者の例は 第1に、根拠のありそうな、権威のありそうな、その他、事実認識的に納得できる発言 第2に、根拠のありそうな、権威のありそうな、その他、事実認識的に納得できる人間の発言 後者の例は 第3に、多少根拠がどうでも、自分の利害に合っている言 第4に、「他人に面白い」話 です。 5−2. 情報の事実の社会内での伝播 こうして、賞賛や優越は社会内の認識ですから、情報提供者の行為論的意義は彼の、行為者が思う社会内での位置に伴って変化します。 事実それ自体の伝播とは異なり、賞賛・優越は、他者への規制を介して伝播します。従って、それらは社会総体で規制を伴う水路を通って他者に受け継がれます。 賞賛・優越を伴うある事実を認知したある行為者は、その事実の彼の社会的位置での行為への適用をイメージしますが、この時行為者が生産関係において顕著な権力的位置にいた場合、彼の行為への適用は、彼の「組織」への適用を促します。 そして、組織が生産関係=権力関係に規定される限りにおいて、この組織内での適用が実質的に社会全般への適用になります。 一方、生産組織以外での情報の事実の社会的有効性はどうでしょうか。 ここで、資本主義社会においては、自立的構成のある組織の減少/脱落が生じていることに注意してください。 資本主義社会においては、商品関係から独立した、たとえばお布施で成り立つ宗教組織、結社的な労働組合のような自立的・自律的構成は存在しなくなっていきます。 商品関係とは関係ない組織、すなわちPTAの類の組織、すなわち他者への規制の微少な組織では、定義上当たり前のことですが、そこで何をしゃべろうと、他者の行為への規制力は、よもやま話以上の意味をもちません。 5−3.情報の事実の世代間の伝播 親から子へ、成人から児童へ、人は、文化を受け継ぐのではありません。 文化とは、(時代によって異なる)賞賛や優越を持った人間と(時代によって異なる)社会的必要の所産であり、時代を越えて受け継げるものではありません。 人は知識を受け継ぐ。 しかし、それは単なる知識ではなく、社会の中の彼に即した知識です。 すなわち、人が受け継ぐものは、権力による関係の(立)場であり、共同性内での(立)場であり、要するに規制の関係であり、従って、賞賛の関係です。 この関係が不変に近く存在する限り、事実の認知は閉鎖的な親子、共同体の中で受け継がれていきます。 6.情報の事実の認知と権力の実際的行使の事実 さて、権力の関係は、自分の権力的位置の中で受ける他に、支配されているという認知と梱包された知識として「他」からもたらされます。 被支配人民にとって、(民主主義的環境における)政治権力を行使したという事実認知は、実は個人の恣意では動かしようもない経済関係も含めて、権力行使者の責任となります。 本当に権力行使者の責任であるかどうかは、この際、何の関係もありません。専制的権力の中では実際、権力行使者として、民主主義的環境においては、自分ならできるから選んでくれというホラのツケとして、それは当然である一方、人民も単に環境への反感を述べているに過ぎないからです。 たとえば、従来型零細商店の構造的衰退は明らかであるにもかかわらず、田舎に生じたそうした事態は、そこでの町長が公共事業費を減らして福祉産業を育成した経済貢献にも関わらず、従来型選挙権所有市民に、ウケが悪い。選挙ではこういう善意の町長はつぶれます。誰がやったってつぶれていく町の役員はなんとか昔日の反映を取り戻したく、お門違いの政治に奔走します。濡れ手で泡の新保守町長。 といって、それは必ずしもその田舎の町民がとりたててバカなわけでもなく、事実認知というものはそういうものなのです。 一方、政治権力行使者はといえば、自分が権力を振るわなければならないという認知のもとに振るえるだけの基礎知識を総動員しています。その総体性は学者などとてもかなわない。 たとえば、初めての代議士立候補者は何も知りません。種々の社会的位置にいる人々には、全体的な利害を知ることが困難です。 新人代議士は、実際の政治的決定の場にあたり、そこに集約されるかぎりでの社会認識を得ます。 もっとも、政治権力行使者といえども、国家場面に集約された利害しかみることはできません。 それらの限定された利害について、彼らの賞賛と優越のもとにこれを決定しているわけです。 問題はそこに何が集約されているか、です。 国家の歴史的成立上、そして現状にいたる構造上、それは「現状の維持」です。 資本主義社会においては、それは当該資本主義の基幹産業の維持であり、国民が反乱を起こさない限度の維持であり、それらの行為のための財政の確保です。 7.国家による情報の運動 国家は、その行為者への規定力により、恣意的に事実としての情報を押しつけることができます。 経済的には国家は恣意的になにができるというものではありません。資本主義は自分の経済的意思を持っていないからです。 しかし、それでも国家にできることが情報による大衆変更です。それは「操作」という生やさしいものではなく、権力が内在する生理性・賞賛・優越を通じて、大衆それ自体を主体的に変えるものです。 それはフランス革命でもロシア革命でも明治維新でもそうです。 人間構成員の意思を操縦していくものは国家の(経済措置ではなく)権力です。 政治権力行使者と一口でいっても、政治家が、実はたいした知識もなく、ただ口伝えのプロパガンダを唱えるだけだ、というのは古今から同様です。それに対して官僚はとりあえず必要なだけは知識があるといえますが、実はそうした知識量はたいした問題ではありません。官僚は知識はあってもそれを使うことはできないのです。 国家による権力の行使に必要なのは、知識ではなく不退転の暴力機構なのです。 暴力を行使したくない者はなにもできはしません。彼らができることは権力がカスカスに最低限作り上げた「法律」による罰則行使だけです。そして平常はその罰則の行使により情報を運動させてゆくのです。 資本主義においては、実は国家が経済にタガを嵌め、資本主義の没落を救っています。現在の日本で言えば、ここで逆にタガをはずすことが新たな運動になるのです。それは行為者にとって、逆生理性を発動させるのです。 社会学において重要なのは、そうした運動による情報の勝利敗北の過程です。 そして個人行為者の勝利には、人民による、力はないが比較的に容易な過程と、権力による、力はあるが、それを国家意思にするには「官僚制」のような知性と、左右の差別のない(資本主義という)経済機構とが必要なのです。 8.情報の事実の認知とその使用への志向 (世界についての認識と資本主義) さて、こうして得た事実によって、人はどのように環境に働きかけるでしょうか。 日本は資本主義の社会です。しかもグローバリズムというように、資本の「自由貿易」=帝国主義的侵略(だーれもいわなくなりましたね)によって、アメリカのナマの資本主義が世界レベルで文化を破壊していくさなかにあります。こんな激動の時代には社会を変えようとする人もたくさん出るでしょう、、か? 私には残念ながら、そうはいきません。世界を動かす認識と意図は、資本主義におけるような「儲ける」という認識・賞賛とは別の世界のものなのです。 世界への働きかけは、いわば支配ー被支配の系譜に生ずるものであり、権力の行方を誰が掌握し、その階梯に誰がいるか(どんな種類の人々がいるか)という問題です。 いわば、商品経済社会プロパーの問題としては、世界を変更させる人々の輩出する余地がないのです。(もちろん、変更志向者に従った方が都合のいい人々は、他の支配社会と同様に、輩出します;プロレタリアート) (法的規制ではなく)社会的規制の弛緩の認識は、資本主義爛熟期においては、自由を志向する個人行為者としての諸商行為者をして、生産販売活動に係る法的規制の撤廃を志向させます。 以前において共同体的配慮(=社会的責任、その他の賞賛の存在)があったものを、好き勝手を体現できるようになった個人商行為者は、その権力的位置をわきまえることなく、自由に資本主義活動を遂行できます。(=市民的個人主義) 一方においては、資本主義活動が主張する、つまり、地位的に同じであるはずの商行為者が得ようとして実際得続ける自由、をめぐる社会的賞賛は、「革新を唱える」ということに社会的賞賛を覚える、社会的位置・個人的信条をもった者たちについて、同様に資本主義活動を「革新」の内部に取り込ませることになります。 といってもそれは商品経済がうまくいっている(先進)国家の場合に限ります。 そうした先進国家では後進国家の犠牲の上に、社会で生理性が問題にならなくなっているだけなのです(なんてこともだーれも言わなくなりました。今回はあまり好きでもない共産党のような発言が多くなりましたね、って共産党でさえ言わないか)。 生理性が人間の行為方式を規制・決定する重大な要因であることから、生理性が問題にされない社会とそうでないごく一部の社会においての諸認識は、あまりにも違うものです。 われわれ日本国家人はすでに忘れかけているところですが、50歳以上の人間ならそれは思い出しうる範囲にあるでしょう。(なお、こう書いている筆者は書いている現在50歳未満です。どうでもいい?) これは、しかし、事実認識の次元の問題です。 過去日本人は、生理性の欠如に思いを及ばし得る「共同性」の下で、自己の賞賛と優越を磨き得ました。しかし、それは一般の社会と同様に、社会の認識に過ぎません。多くの日本人はすでにそんなことがあったことさえ忘れています。なぜなら、われわれないし彼らは、今も生きているからです。新しい状況の中にあって、我々個人は、今、生きていかなければならないのです。 【2月分】 さて、私がこの場所で言ってきたことは、私の心の中では、運動アピールの本体についての解明、つまりそんなものがどれだけウソで、でもウソなりにどれだけの社会への働きがあるか、ということでした。 みなさん方には、本論のテーマは、人がこれは正しいと語る言葉とはどんな性格のものか、というふうにあいまいに考えてもらうようにいいました。 最後に、今月は思想と倫理の違いを述べます。 人はよく自分の倫理を表明して人を説得します。だって自分にはそれは正しいのだから。 しかし、それは正しくない。 自分の倫理は正しいはずなのに、人に話した瞬間にそれは正しくなくなる。でも自分は正義を述べていると思うから彼らは人を殺しても何とも思わない。 このことを述べて、この場所は少しお休みします。 1.思想とはなにか 思想とは、人生や社会への「知識」ではありません。 知識はただの行動の素材ですが、知識を教えてくれる者は「先生」でしょうが思想家ではありません。 また、思想は哲学ではありません。 哲学は物事について、ああも考えられる、こうも考えられるだのという、いってみれば有閑マダムの遊び事です。(そんなマダム、いまどきめったにいないか) 人間は、ああだこうだのという可能性をいってのほほんと生きていられるわけではありません。 有閑マダムのような哲学者は「世界は存在するか、本当は存在しないか」などと問題を立てます。しかしわれわれは「本当は存在するにせよ存在しないにせよ」われわれが直面する現実について、日々、一瞬一瞬決断しながら行動しなければ生きることはできません。「本当であれウソであれ」、人生の「役に立つ」知識群によって、これを明らかにしてもらわなければなりません。 思想とは、人間が生きるに際しての行為と社会との関連づけを他者に教えるものです。 おまえのこの行為はこういう意義があるのだ。(だから、しろ、だから、やめろ) そう他者に告げていくものが「思想」です。 個人の賞賛を活性化させ、優越を活性化させる知識です。 いや、だからそういうものは「知識」とは呼びません。 一方、倫理とは、それが現れる個人の年齢の中では、あくまで自己に帰属するものです。 自分にとっての自分の行動が、自分の内部に蓄積された賞賛(と優越)を呼び覚ますものが倫理です。 このため、自分の内部に賞賛がない者は倫理を持てません。 従って、「自分はこうしている」は倫理ですが、「人間はこうしなければならない」は倫理ではありません。それは思想です。 2.思想が持つ賞賛の社会的権力の保持層と被権力層における差異 ここで、思想や倫理が持つ賞賛は、社会の中でその人がどんな位置を占めているか、によって異なります。 「どんな位置を占めるか」というのも微妙な言い方で、その人の親のいた位置、その人がこれから占めていく位置、といった概念も含みます。ある個人は本人にすれば子供から大人まで大して変わりませんが、その個人の社会の中での位置は成長に従って変わってくるからです。 まずその社会的に権力のふるい方を知っている層において、思想は、 (1)言語的論理構成において、論旨の通じる構成と (2)これにプラスして、時の権力または対抗権力にフィットする言語情報と (3)さらに、時の権力または対抗権力にフィットする賞賛と を持ったものです。 彼らにとって思想には、社会的支配権力をめぐる言語的道具、という実用性があるのです。 一方、被権力層といいましたが、要するに権力をふるう地位とは関わりのない人たちにとっては、思想は日常的実用、つまり、現在自分をめぐって生じている権力関係の「始末」においてのみです。 すなわちここでは (1)時の権力ないし対抗権力が指示する情報をコピーする言語情報と (2)それによって共同的日常の賞賛を得られるべき、時の権力または対抗権力の賞賛の一部とを持ったものです。 両者の違いは、 (1)真理的構成の努力が必要かどうかという違い (2)そして思想的表現が持つ賞賛が、社会的に大状況的か、ローカルな個人的なものかという違い、だから同じ言葉を使ってもそれに賞賛を見いだすかどうかについて、社会的意味府よがなされる時間的ずれが存在する、ことです。 3.思想と宗教の違い よく人は宗教もイデオロギーも同じだ、といいますが、そしてそれは大部分正しいのですが、大きく異なる点は、宗教の命題は常に普遍的通時代的命題であることであり(そしてそれにそぐう思想材料であり)、イデオロギーの場合は、今現在の特殊的命題であることです。 早い話、宗教はいつの時代にも正しい「人生」や「人間」や「真理」を語り、イデオロギーは、今この世界での人間が生きなければいけない生き方や「この時代での真理」を語るわけです。 ま、当たり前ですね。 しかし、これが私たちの日常では異なる対応を引き出す。と同時に、日常的には異なった運動的価値(無価値)を生じます。 本来的な宗教においては、その普遍性から、運動的賞賛を持ちません。 宗教がもたらす運動の賞賛は、それがあり得る場合は、組織的・幼児恐怖体験的恫喝による宗派的賞賛でしかありません。「そんな政策はバチあたりだ、ほっておくと神罰が下る」という評価において、宗教組織上の賞賛を動員するか、あるいは運動しない連中に神罰があたることを実力的に言いふらすか」という意味です。 運動における本来的な賞賛は、本来、今現在の(生理的)利害がもたらすものであり、これは世俗的思想が受け持つ役割です。 この例外は、独立した「武力国家」がない、大昔共同体宗教が存在した時代だけです。もっとも人間の歴史では、この例外期間のほうが今のところ長いのですが。 4.表現の3局面 言語表現では、自分の思っている意味と、それを聞いた人が受け取る意味とで異なっていることは多くの言語論者が述べてきました。 とはいえ、それが大きなトピックになる事態は、コミュニケイトする二人の人間にとって、ある言語表現は同じ価値を持つ意味を運ぶはずだ、という信仰的確信に基づいています。 こうした議論を読んだ人々は常に「それがどうした」と思ってきたでしょう。 我々は学者に説明してもらわなくとも他人がどんな意味で「私」にしゃべりかけてくるかをその時々でほとんど正しく解釈できます。 でも、社会生活にとってさらに大きなトピックとしなければならないことは、その先にあります。 すなわち、それ以上に社会にとって意味が大きいのは、 (1)誤解であろうと正解であろうと相手から受け取った意味が、自分にとっては必ず概念的空無を意味すること、 そしてさらにそれ以上に、 (2)行為者にとって主要に考慮しなければならないのは、受け取った言葉の意味ではなく、相手がそれを発した、という現在この瞬間の社会的現実である。 ということです。 「彼」が他人のことを「Aのやつは馬鹿だ」といった意味をわれわれはその場に応じて解釈することができます。「彼はAとケンカした」「Aは仕事で失敗した」「Aという男とつきあうときは少し気をつけた方がいいかも」 それらの解釈のほとんどは、そのときは現実に正しい。 しかし、我々の頭に残った「Aのやつは馬鹿だ」という表現は、それ自体としてなんの意味も持っていません。 さらに、我々にとって重要な意味があるのはそんな言葉の解釈ではなくて、そういった「彼」と私との関係です。Aが社長の場合、私は社長とケンカした彼を慰めなければならありません。Aが新入社員であれば、まあそういうなよと新入社員をかばってやるでしょう。 言語表現が指し示す現実と それを受け取った人間が思い直す作業と それを受け取った人間が対応すべき表現者(たち)との関係という現実、 表現には常にこうした3局面があるということが重要なのです。 5.表現と賞賛 しかし、他人が言った表現は論理的な真実としてはなんの意味も持たなくとも、賞賛はここにセットされています。 すなわち、記憶の中に整理された賞賛とそれにセットされた優越は、「伝えられた言語表現」とセットされている、という事態です。 我々は、自分に意義深い表現を頭の中で転がすときには、具体的な状況から離れて、「現実のない」言葉とそれがもたらす生理的ホルモンの快感を味わうしかありません。 6.表現と現実 さて、現実のない言葉は自分の頭の中でも反芻されます。 そして、すべての人間の行為を伴う思考には、すべて、具体的な人間という存在に伴う「不可能性」があり、したがってすべての頭で考える行動規範は「虚偽」を伴う。 人は「本当には」生きることはできません。 (例示:「自己否定」論の正しさ) ある左翼である商社のサラリーマンは、自分が資本主義の走狗であることを否定することなしに左翼ではありえません。 しかし、それを否定した瞬間に、つまり商社を辞めた瞬間に彼はルンペンプロレタリアに成り下がる。したがって、分析論理的には「自己否定」などという「論理」はありえないのです。 にもかかわらず、自己否定なしに彼は左翼であることはできません。 さあ、どうする? 自己否定論を否定する人間は、この矛盾を自ら感じたことのない人間です。 何も感じ得ずに自称倫理学者になり「自己否定論」なる「論」を否定します。バカが。 人は自分の矛盾した立場を問題にする限りは、過去若者がやったように「自己否定」する他はありません。 自己否定などしてもしょうがないではないか」という論はまた正しい。その人々は私がそうだったように、やはり、論理上の自己否定を行ったからです。 ただ、前者と後者との間の差は、やはり」正しさの差でもある。 どちらが正しいかと言えば自己否定を行動した方が正しい。 人間は、行動できない「生」を持っていてもしょうがないのです。 しかし、話は複雑です。 自己否定を行動した人と同じ行動をしたからといってその人々が正しいわけではありません。 彼らはプロ野球の観客と同様に、観客としてプレイしたにすぎません。 「自己否定」という言葉が示すように、問題は論理です。 常なる屈辱、常なる口元の歪み、そして解放への要求が、自己否定しそこなった人間たちのありようです。 もちろん屈辱は、連帯によりある程度の「文学的表現」に変わる。 といってもわかる者は数百人しかいないでしょうが、「銀行員私は、今日も職務としてこんなことをしてしまった、畜生」という歯ぎしりは、他にも同じ彼がいる、という認識で、ずうっと軽くなるのです。 ちなみに私に限ってはそんな連帯を認識することもなく、「皮肉屋」担っていくにすぎないのですが。 ここでおそらくポイントは、ブルジョワ倫理学者の「行為論」にあります。 彼ら観念論者は、行為とは、1秒後の将来を得るために存在しているとしか思っていないのです。 かわいそうな貧乏人に寄付するのは1秒でできます。 かわいそうな貧乏人のために投票するのは1秒でできます。 そんなブルジョワ思想家。 たしかエンゲルスが指摘したように、プロレタリアはそうではありません。 プロレタリアは自分の未来を手に入れるためには、何年も何十年も百年以上も待たなければならないのです。 その間、文学的に言えば、彼は唇を歪めて毎日を過ごさなければならないのです。その間彼は自分に満足するわけには行かありません。自己否定の倫理とは、舗道のブロックを壊して投げつけたぐらいで実現するものではないのです。 あれから30年、私の想像によれば、それを日本で今現在知っているのは、自己否定を闘った(という3万人のうちの)300人と、「そんな倫理はくだらない」といった(5千人のうちの)百人と、合わせて4百人くらいでしょう。 この人数計算は、どれだけ人が論理を無視しているか、ということと、どれだけ組織が論理を無視しているか、ということを表現しています。 「人」とはどこでも1%です。 論理が勝利する限りいつの世にも自己否定論はよみがえる。 問題は、しかし、論理が勝利する日は、日本ではあと30年はない、彼ら自分が通ったと幻想を抱いている開き直った人々が生きている限りは、再びこない、ということです。 というわけで、人間がこさえる規範を表現する言葉と現実はそもそも異なる、 昔の人がいったように、人は観念と肉体とが引き裂かれています。 にもかかわらず、観念を扱う者だけが動物を含めた他者を幸せな方向へ運ぶことができます。 人の虚偽は戦いの理由であり、そして虚偽がどれだけ自分にとって社会にとって透明なものとなったかが、人が戦い取ったそれまでの戦績です。あるいは、その認識が勲章です。 7.社会と思想 「たとえば、子供は勉強するものだ」という命題は資本主義現代における「支配的な思想」です。昨今の日本の労働は、勉強抜きに成立しないからです。これを「子供が労働から遊離している」と述べるのは認識不足です。 ただし、多くの母親の観念は現実の要請とはたしかに異なっています。個人としての代表的な母親は、家庭内の労働なんてどうでもいいし、いわんや社会の労働など、それこそどうでもいい。金持ちの(社長とは言わないが)重役にでも偉い官僚でもなっておくれ、みたいなものです。 現実の要請は、そういうものはほんの何千人かいればいい。日本の代表的な子供は、新しい携帯機器を作る技術者やそれを海外に売るセールスマンができればいいのです。 そうした個人の観念は、個人の立場に翻訳されるが、しかし「子供は勉強するものだ」という認識は変更されることはないのです。 これが本来の支配的な思想のことでなければなりません。 9.倫理とはなにか 「倫理」とは、個人にとっては、社会における他者の対抗を「無視」する根拠となる、行為の賞賛のことです。 社会において他者が対抗しない位置にいる人間に倫理は不要です。 利害の不一致のない社会においては、倫理は不要です。 家庭と従わざるを得ない会社とテニススクールへ通うものには倫理は不要です。 しかし、リストラの手が近くに及んだとき、想定される上司への抵抗をする自分や想定される次の会社を探す自分、という状況において、他者の対抗を「無視」しうる自分が必要となるのです。 上司へ抵抗し職場の他の者の冷たい仕打ちに対抗するには、上司や職場仲間以外の賞賛が必要なのです。 これが他者に向けられるとき、それは他者が従ってもらわねばならぬ自分の「正当な」主張であり、また、その主張は次の自分の行為も縛らざるを得ない主張となるのです。 もちろんこのとき、その自分の縛り方はご都合主義かもしれません。あるいは3年も経ったら忘れ果ててしまうものかもしれません。しかし、それは賞賛の自己への巣くい方の深浅にすぎません。 およそ、キリスト教の共同社会で育ったものでさえご都合主義のキリスト教解釈をする世の中で、そんな基準でけなされる必要もありません。 自分の力で賞賛をやっと見つけ、やっと見つけた賞賛のかすかなロープを3年も大切にできたことのほうがよっぽどえらい。 「なんだ、共同体教も自分のものにできもせず」とバカにしてもいいぐらいです。 10.倫理と賞賛 児童期の賞賛とは、賞賛のうちに優越が内在しています。これは成人の権力的地位による優越と、同一の地位を(心の中で)占めています。 ある、倫理的にフリーな、児童期に賞賛をセットされていない人間は、それ以後の時期においては周囲の共同性がもたらす賞賛に十分満足します。 それは人間にとって、とりあえずどちらがどうという問題ではありませんが、人間はそういうものだということは重要な認識です。 ついで、「とりあえず」といいましたが、それではどちらが究極的に個人にとって大事な賞賛であるかといえば、それは児童期の賞賛です。児童期の賞賛が個人にとって行動とセットされた「自由な」構築の要素とされるのに対して、成人の賞賛は社会の制度にとらわれた賞賛であり、また社会における「地位」が左右する優越だからです。 情けないにもほどがある、、、と思うのは昔気質の人間だけだとは思いますが。 思いますが、ポイントは、個人としての自己の人生を賭ける(近代的な)自由は、自分が目的を構築した中にある、ということです。 もともと、南洋諸島のような人間的な暮らしを望めない近代社会においては、せめて、自分らしい生存を実現するのが、ある種の幸せです。 さらに重要なことは、成人の賞賛・優越を追求する者は、他人を拘束することで存立するその社会の制度を維持すべく活動するほかはないということです。 一方児童期の賞賛は、長じるに従って社会からの自分への拘束への抵抗を内在化した規範を確立させ、それが人間全般を規定しようと襲いかかる近代的拘束への抵抗の砦となるのです。 11.社会と倫理 共同体的社会に当然あるはずの社会道徳、すなわち、上位権力者による賞賛と優越の独占は、 資本主義社会における上位権力者の権力行使の離脱、すなわち権力の生産関係への移譲により、賞賛と優越の模倣を下位構成員にもたらしました。 しかし、一方での資本主義的個人主義は、個人倫理、すなわち「評論でない倫理」を下位構成員に要求します。 これが「お前はどうするんだ」の問いです。 「お前はどうするんだ」の問いかけに対しては、自分にとって「あしたのジョー」が存在すればいい。 すなわち、自分がどんな存在でも、そうした賞賛される同一性の展望が彼を救う。 一方、この過程は基盤的な社会道徳によろうとする者を拒否する過程です。 もともと共同性のないところに賞賛などありはしません。運動家の組織共同性を除いて。 賞賛を見いだせなくなった人々は、あたかも自己に倫理的根拠があるかのごとき幻想と「論理」構成の元に、利己主義、正確には単なるホルモン的行き当たりばったり主義を標榜するようになるのです。 12.倫理と思想 およそ自分だけのものである倫理を他人を含めた規制原理として他人に告げる者は、その告げる行為において「権力」の萌芽とみなされ、さらにこれを受領した者を含めた複数の存在は、自分の行為を自分で律するはずの倫理とは似ても似つかぬ、事実上の行為への権力となります。 これが自分にとって正しいはずの倫理が、他者にとって行為論的に正しくなくなる理由です。 もちろんそれが社会的に悪いわけではなく、社会的にはそれは「思想」として、権力を扱う場面の観念的武器となるわけです。 倫理は論理的には個人の生き方であり、個人が自分の一瞬先の未来を、自分の生理性等に抗して設計する過程です。 一方、自称倫理信奉者の倫理とは、お前は個人なのだからこうするのが当然だと他人を規定する過程です。 大きなお世話です。 てめえの世話になることは倫理とはいわねえや。 他者にとってそれは「社会の道徳」です。 もちろん、個人の倫理は彼が社会生活を送ってきた結果ですから、別に社会的だから悪いというわけではありません。 そうではなくて、それは社会の中で育った個人の持ち物なのです。そこでの社会=他人たちとは彼の心の中の他人にすぎません。 他の個人にとってみれば彼とは関係のない、他人が設定した他人たちです。 そんな他人に左右されてどこが自由か。 他人のない個人はないが、他人に束縛される自由もないのです。 13.その他の「倫理家」の例 自称倫理家という評論家はこのようにおしつけがましいものですが、自己倫理もないこんな時代です、中にはこれに対抗する「倫理家」いないわけではありません。 しかし、それは対抗のための発言であって、倫理ではありません。ちょっと例をあげてみますか。 内田樹「ためらいの倫理学」角川書店、2003。 これはまさにその題に反して「思想」です。 それは「倫理」ではありません。百歩譲って「倫理についての思想」です。 26章のテーマでできているこの本で内田が発言していることは、極端はやめて「ナカをとって」話そう、ということです。 読んでみればわかりますが、私の友人には穏和な人間が多いので、多くの友人は「この本いいねえ」というでしょう。 たしかにそれはそうかもしれありません。しかし、人間の世で思想というものはそういう機能をするものではないことが私のテーマです。 この本の時代的な思想的価値は、庶民の救済的思想がなくなった後の、支配者の思想への反「倫理」の位置を、牙のないつぶやきで埋めるものです。 国家や社会的圧力集団の思想に対抗するのは、「そんな極端なこというなよ。それも正しいかもしれないけどこちらも正しいよ」という庶民的感想を述べることでは、まったく無力です。 それは「国家」に反抗しようとする思想にも同じことを告げるだけの機能しか持たありません。 そのうえ、そういう人間の社会制度への無知がある場合においては(この内田の場合)、もう救いようがありません。 たとえば内田は「性差のもたらす弊害を実質的に廃絶することを人々がほんとうに望んでいるのなら『性差については語らない』というのが、一番効果的な方法だろうと私は思う」とのべる(P219)。こんなことを常識人の顔をしていわれてはたまりません。黙ってて婦人参政権が勝ち取れたのか? こんな低レベルな話はフランス文学や冬弓舎ではあるのでしょうが、思想の世界であってはなりません(彼はフランス文学者です)(冬弓舎は単行本時の出版社)。 したがって「ためらい」は「倫理」と相容れない概念なのです。 14.その他の「思想」の例 本当の思想家については、「その1」で述べました。 ここで、戦後日本の民主主義について扱った本を3点あげましょう。 別に大したものではないのですが、たまたま図書館にあったもので。でもさすがに引用はみんなの無駄だと思いますのでやめます。 まず、 高橋秀実「からくり民主主義」草思社、2002。 日本各地の問題状況のルポルタージュです。最近の若いおじさんは思想なんてないものだと思っていたが、やっぱりないのです。 でも本人は民主主義への批判だか警鐘だかとででも思っているのでしょう。 社会を日常そのままに表すものは思想ではありません。 「思想の暗黒」というものが全然わかっていません。 そういえば、最近社会学的実証研究という論文を覗いてないのですが、もしかしてこんなふうに思想もなにもない研究がバッコしているのだろうか。と思ってしまいました。 ついで、ちょっと有名な 呉智英「危険な思想家」メディアワークス、1998。 これは一口でいえば、民主主義に恨みでもあるただそれだけの人です。自分の思想があるわけでもありません。 他人が発言した、どうせその場しのぎの「ことば」にケチをつけてるだけで、それだけでは反民主主義の雰囲気を流しているだけの意味しかない。 呉がいっているのは「人権思想家と民主主義者の思想はいい加減だから反人権、反民主主義の私が正しい」ということだけです。驚いたことに人権思想への批判も民主主義への批判も書いてあるわけではありません。あくまで思想家への批判なのです。 ところがどっこい、思想家などというものは、「誰であれ」差別なくいい加減なのです、呉自らもそうです。その証拠に彼の結論にはなんの根拠もありません。結論もただのヨタ言葉の続きとしか思わないから誰も(私も)再批判する気にならないだけです。 残念ながら人は自分が非難を受けてもそういうルートから真実に近づくことはありません。 もともと思想とは、いい加減な思想家の言葉にも関わらず、したがってそんなケチ付けにも関わらず、ある事象が読んだ人間の将来に思い描く行為の結果について、どう関わっているかをしめすところに意義があるわけです。 まあ、だからといって呉が悪いとかいうわけではありません。誰でも売文業者というのは文を売らなければ生きてはいけません。そんな文にケチをつけるのは私としても大人げない。吉本喜劇を見て感激したり週刊新潮の記事を信じたりするようなものです。 ただ、いまどき「思想」なんぞはそんなもんしかないんでちょっと触れてみただけです。 最後に、 斉藤貴男「日本人を騙す39の言葉」青春出版社、2003。 これは呉や高橋にいわせれば、叩けばいくらでもホコリの出そうな本です。社会批判の書なのですが、ちょっと日常の感覚から外れているから。そして人間というのはどんなに虐げられていても平穏な日常を持っているのです。 が、思想というのはこういうものです。 思想は憂さ晴らしのテレビや競馬ではありません。平穏な日常からまた虐げられた社会関係に入ったとき、さあどうする、と問いかけるものです。高橋君、わかるかね。 15.最後に 思想と思想家 このように思想には、優越と賞賛のファクターがある。 と、わざわざ記さねばならないか、というと、これも思想をめぐる誤解を避けるために期しておかなければなりません。 人は、労働者だから労働者「的」思考ができるわけではない、という、戦後、われわれにはそう昔ではない時期に「理論と実践」という名の下に、逆に「労働者たれ」というインテリゲンチャの(!)かけ声とともに主張された影響の撲滅のためです。 もちろん昨今は、日本ではすでに残っている主張ではないですが、私は、すでに目を国外に向けています。(逃げてる?)昔からこれだけはなんの反論もなく信じられている命題そのままに、永続革命は世界革命以外ではありえず、こうした混乱した論議は、支配階級の大衆化の過程ではどこにでも生じうる現象だからです。 人は、労働者の上位に位置する者として、労働者に益する思想をその他の社会構成員に流す。 それを拒否するかどうかは個々の労働者の勝手です。その場面で、労働者と思想表明者が手をつなぐ必要などさらさらありません。 これも実はいっておいたほうがいい。 人は共闘しなくとも社会に存在することができます。 共闘しなければならないと考えるのは、古い日本的=農村地主(エリート)的思考であるにすぎありません。 資本主義国家においては、人は個人主義的見地を貫くことができます。これは資本主義が個人たる人間に与えた重要な利益です。 もとより、人は個人で生きることはできません。 だからといって、人は「自分が志向する人々と」協同しなければならないと考えるのは、机上で学生や、幼少期の「自分の」小作人のことしか考えたことのない人間の思考です。 人は共闘する人間とのみ、協同しうるのです。 空語はやめなさい。 誰が共闘してくれるか。 空語でない人間は、自分の周りを見渡したときに誰がそうかを知るのみです。 |
|
![]()
| ・ 隈の紹介 | ||
| ・今回のトピック | ||
| ・ 本の紹介 | ||
| ・ 隈への問合せ | ||
| ・ 隈からのお答え | ||
| ・ ホーム | ||
| ○(旧)今月の話題(その1) |